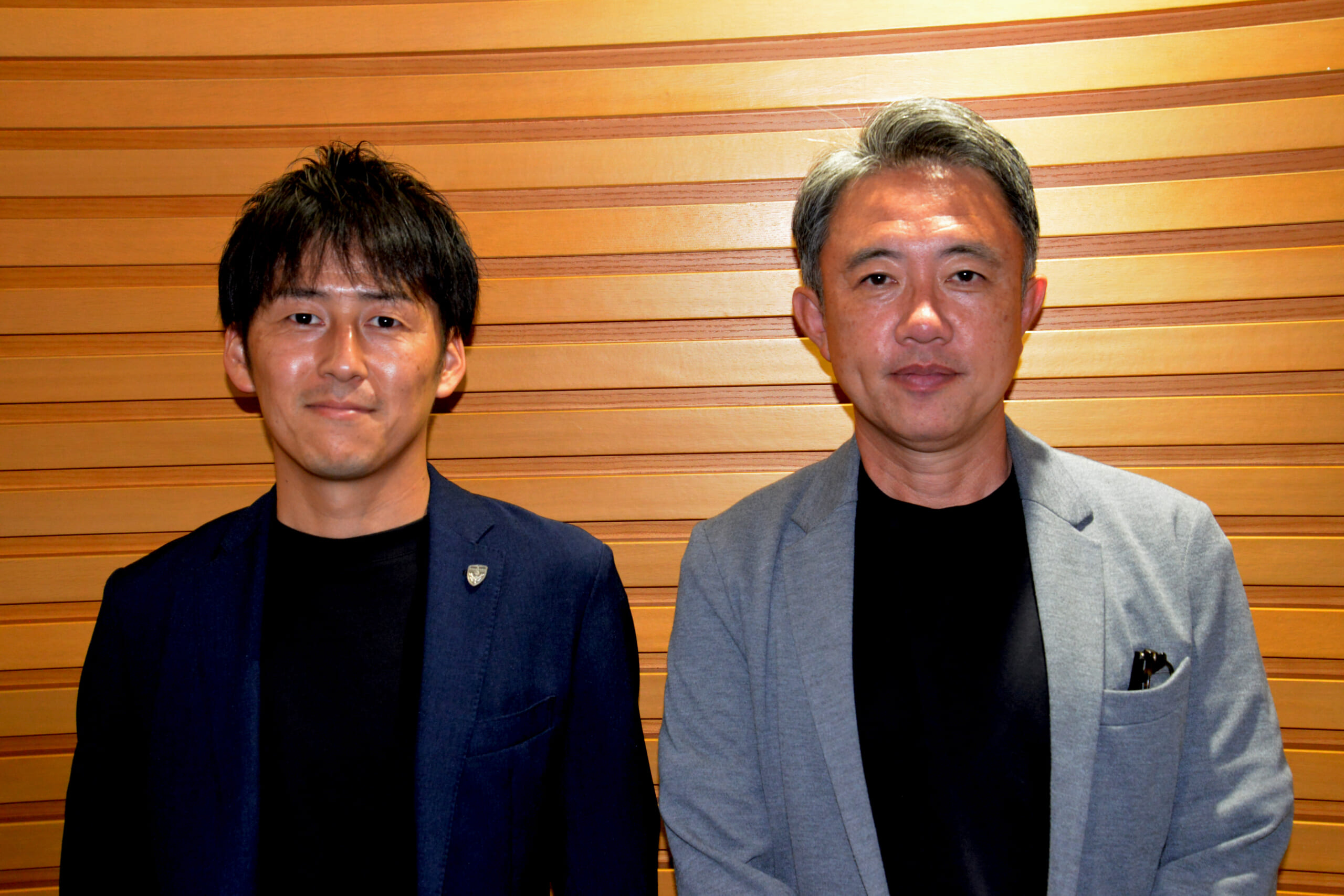九州の3/4の小国ベルギーがFIFAランキング1位になれた理由

2015年11月、ベルギーはFIFAランキングの首位に立った。それまでW杯の最高順位は1986年の4位、EUROでは80年に準優勝の経験もあったが、今から30年以上も前の話。その後、表舞台で彼らの名が語られることはなかった。そんなベルギーが14年W杯で8強に入り、翌年“世界ナンバー1”の称号を得るまでになったのだ。九州の4分の3ほどの小国が“小さなサッカー大国”として代表シーンに風穴を開けるに至った過程には、一体どのようなストーリーがあったのか。関係者の話を交えながら解き明かしていこうと思う。
『ビジョン2000』に始まる協会の育成計画
1980年代の隆盛を支えたのは、元マルセイユ監督のエリック・ゲレツや“リトル・ペレ”の異名を取った至宝エンツォ・シーフォ(元U-21代表監督)がいた、ベルギーにとっての第一黄金世代だった。しかし以降はW杯に出場はしても「いち参加国」以上のインパクトはなく、EUROに至っては84年大会を最後に予選通過も叶わなかった。
そんな彼らに格好のチャンスが訪れた。EURO2000の、オランダとの共催である。そして、この大会の実行委員長に任命されたミシェル・サブロン氏こそが、今のベルギー代表を作った“育成の父”だ。彼は86年W杯でA代表のアシスタントコーチを務め、その後ユースチームの育成を担当、96年にEUROの責任者に選ばれた。大会に向けた代表育成プログラムは『ビジョン2000』と名づけられ、主に指導者の強化や指導方針の見直しが行われた。
ところが努力の甲斐なく、代表はグループステージで敗退。最低目標だった決勝ラウンド進出を逃し、サブロン氏は「プレー内容ばかりにこだわって、実際に勝ち抜けるチームを作らなかった」と非難された。だが、すべてが無駄だったわけではない。開催国として得た収益をもとに、育成のためのインフラ設備を整えることができたからだ。

のちに協会のテクニカル・ディレクター(TD)となったサブロン氏は、新たに長期育成プラン構想を立ち上げる。02年W杯でマルク・ウィルモッツ、ヨアン・ワレムらの世代が引退。世代交代期を迎えていた代表にとって、それは必要に迫られた改革でもあった。彼はオランダ、フランス、ドイツといった近隣諸国の代表や、アヤックスやバルセロナなど育成に定評のあるクラブを視察して回り、メソッドを学んだ。そうして06年、現在でも下地となっている協会主導の育成プログラムを完成させた。
サブロン氏が柱としたのは、異質とも言うべき2点だ。
1つ目は、フォーメーションの徹底。それまでのベルギー代表は[3-5-2]、あるいは守備的MFを2人置く[4-2-1-3]が主流だった。彼はそれを中盤が逆三角形の[4-3-3]に変え、さらにディフェンスは「ゾーン」というシステムを基本として、それに基づいた指導を各クラブ、サッカースクールに徹底させた。指導書の中には、1対1の時はどうプレーするか、といった細かな指示まで書かれていた。U-21代表を率いている元代表MFのワレムも証言する。
「協会が打ち出したフォーメーション通りに指導は行った。[4-3-3]というシステムだけじゃない。ベルギーではパスより先にドリブルするよう教える。とにかく前で走って攻撃しろ、と。それを基本に、あとは年代に応じてチームプレーやゲームの進め方といった点を指導していく」
[4-3-3]が機能するとサブロン氏が判断したのは、各国の状況を見てのことだった。やり方を徹底することの利点は、ベルギー中の選手が子供の頃からこのフォーメーションに馴染んで育ち、その先トップクラブに進もうと、代表に選ばれようと、ともにプレーするのが誰だろうと、自分のポジションでやるべき仕事が体に染み付いているようになること。小国だからこそ可能だった方針とも言える。
彼がこの指導書を持って各クラブを回った際には、猛反発を食らったという。しかし、それまでの方針を貫きたい、という指導者たちを説き伏せ、指導書通りのトレーニングを依頼。メディアからも批判を受けたというが、3年、4年と経ち、周辺国との対外試合などで目に見えて結果が表れ出すと、次第に反発も消えていった。
サブロン氏がもう1つ徹底したのは、若い世代のチームに「結果」を求めないよう指導することだった。クラブやスクールを訪問した際、まず彼が施設長に頼むのは「壁の順位表を外してください」ということ。勝ち負けにこだわるのではなく、選手一人ひとりの技能の向上にフォーカスすることが、若い世代では何より大事だと説いて回った。
彼が定めた中にはこんなルールもある。「一度ランクを上げたら二度と逆戻りさせないこと」。下の年代カテゴリーの選手が、たまに上のカテゴリーに混ざってプレーすることはよくあるが、一度引き上げたらそのまま元のカテゴリーには戻さない、という決まりを作った。これは「常に先へ進む。後退はしない」という意図を選手本人に身をもって体験させるためだった。
御年70歳のサブロン氏は、シンガポールサッカー協会に招かれ、現在はそこでTDを務めている。ベルギーで成功させた育成方法で、今後は他国に貢献するのが彼のライフワークだ。
エリートスクール『Topsport』の設立
この育成プログラムでは他に、スカウティングシステムの整備やコーチ育成の強化など具体的な改革も行っているが、その中の1つが『Topsport』と名づけられたエリートスクールの設立だ。
全国8カ所に設置された同施設では、地方リーグや下部クラブの育成所→エリートクラブの育成所、と順にセレクションを経て選出された毎年およそ300人がトレーニングに励んでいる。スケジュールは、朝8時半~10時に授業、それから昼まで練習、午後の授業をこなして夕方からまた練習、そして土曜日は試合を行う。コーチ陣も国家資格を持った指導者がそろい、トレーニング内容は充実。スクール生は自動的にユース代表の候補にもなる。クルトワ、デンベレ、ウィツェル、デフール、メルテンスらがこのエリートスクールの卒業生だ。
そして近年、現TDのクリス・ファン・ピュイベルデ氏の主導で、プロクラブの育成システムに「ポイント制」が導入されるようになった。

資格を持ったコーチの数、学業の充実度、施設の質、トップチームでプレーする生え抜き選手の数、プロに昇格した選手の数……などでポイントが加算され、上位クラブは上位クラブ同士でプレーできるよう2部リーグ制を導入し、毎年審査を行って管理する。こうして各クラブが育成に力を入れるようになると、若い選手がすぐに海外へ出て行こうとする風潮にも歯止めがかけられる。エデン・アザールが14歳でフランスのリールに渡ったのは、当時は国内クラブの育成の質が低かったからだ。
実際、ティーンエイジャーのうちに国外クラブに行ったところで毎試合プレーできることはまずない。ならば国内リーグで若い年齢から実戦経験を積み、活躍をアピールして国外クラブから誘いを受けよう、というパターンが定着しつつある。現代表の9割はイングランド、スペインなど強豪リーグで活躍しているが、彼らが「ベルギー選手はトップリーグで通用する」というイメージを浸透させたおかげで、今ベルギー市場は大注目を浴びているのだ。
そうして移籍が実現すれば、国内クラブにも大金が入る。それを資金にまた育成を強化できる、というように、良いサイクルができ上がっていったのである。
移民系プレーヤーの台頭
ベルギーは欧州内でも珍しい外国人枠がないリーグで、以前はアフリカ大陸から多くの選手が来ていた。コートジボワールにユースアカデミーを設立し、優秀な若手を育ててから引き抜くKSKベフェレンのように、アフリカ選手にとっての欧州の登竜門となっていたクラブもある。トゥーレ・ヤヤやジェルビーニョらがそうして世界に羽ばたいた例だ。ここ数年やや風向きが変わり、ポーランドやセルビアなど中・東欧からの選手流入も目立ってきたが、併せて顕著なのが、移民系プレーヤーの台頭だ。
ベルギーの、とりわけブリュッセルやアントワープなどの都市部には、この国に移民として来た人々の子供が大勢いて、彼らがサッカーコミュニティを形成している。コンパニ、ルカク、ベンテケはコンゴ、オリジはケニア、デンベレはマリ、ウィツェルはマルティニーク、フェライーニとシャドリはモロッコ、ナインゴランはインドネシア系と、国際色豊かだ。

「このような他民族の集団は、まさに現代ベルギー社会の縮図でもあります。そして、こうやって人種が混ざり合うことはプラス以外の何物でもない。なぜなら持っているものが違うから。フィジカル、メンタル、プレーのアイディア……違うものが混ざり合うとユニークなものができる」
前出の協会TD、V.ピュイベルデ氏はこう語る。4部リーグには150もの違う文化的バックグラウンドを持つ選手が集まったクラブもあるというから驚きだ。選手だけではなく、現在はベルギー人が中心である指導者に関しても、今後は他民族の人たちを増やして新たなアイディアを取り入れようという案が実現化に動いているそうだ。
「ワロンvsフラマン」の争い
ベルギーという国を語る上で外せない、ある政治的な問題にも言及したい。「ワロンvsフラマン」紛争だ。
ベルギーは自国の言語を持たず、フランス語圏(ワロン)とオランダ語圏(フラマン)、ごく少数のドイツ語圏に分かれている。サッカー協会を表す名称も3通りあり、その略称はKBVB(オランダ語)、URBSFA(フランス語)、KBFV(ドイツ語)と、まったく別の団体みたいだ。過去には互いの言語を話すことが禁じられていた時代もあり、その名残でいまだに自分の言葉しか話せない人も多い。
人種的にもフラマン人はオランダ系、ワロン人はフランス系と異なる。選挙で決着がつかず、無政府状態が1年以上続いたこともあった。問題となるのが経済格差。フラマン圏にはアントワープ、ブルージュなど財政的に豊かな町が集結するが、ワロン圏は州都のナムール以下、商業的に栄える町が少ない。しかし同一国である以上、税制や福祉などで同一条件が課せられるため、フラマン人からは「自分たちがワロンを養っている」と不満が噴出し、NVA(新フラームス同盟)のような政党が独立を叫んでいるわけだ。
日常でこの対立を目の当たりにすることは少ないが、例えば国立トレーニングセンターも「ワロン部」と「フラマン部」に職員の部署がきっちり分かれている。「仲は良いし、まったく問題はないのですが、中には言葉の通じない人もいます。そして、それぞれのエリアで実行しているプログラムが完全に一致しているわけでもありません」。ワロン部の職員はそう言って少し寂しそうな顔をした。
「ワロン人とフラマン人は、メンタルもフィジカルも違うので物理的な面で共存が難しい背景があるが、加えて両サイドの協会の仲が悪い競技もあって情報交換も乏しく、国を代表する選手の育成が進まなかったのです」と話すのは、ワロン州のスポーツ記者ジャン・フランソワ・デュエズ氏。サッカー界はリーグが分裂するには至っていないが、予算が豊富なフラマン側のクラブが上位を独占し、AとBの2リーグに分かれる3部では、Aの全18クラブをフラマン圏が占めるという偏りが生じることもある。
以前に話を聞いたフラマン圏の日刊紙『ガゼット・ファン・アントウェルペン』のデ・ランテール記者は、「フラマン協会はフラマン側だけ、ワロン協会はワロン側だけの強化に予算と労力を注いでいる。結果、小さなプロジェクトはいくつも立ち上がっているけれど、国全体として大きなことを運営するのは難しい。互いにライバル心がむき出しとなり、常にいさかいが絶えないのです」と憂いていた。
代表チームでは、ワロン圏出身のウィルモッツの前はフラマン系の監督が続いていた。その場合、例えば先発イレブンの6人がフラマン系、5人がワロン系となると「フラマンびいきをしている!」とワロン圏のファンから声が上がり、また選手たちも同系で固まる傾向があるなど、チームをまとめるのも一苦労だったそうだ。
移民系選手が台頭したことは、代表内の「フラマンvsワロン」の緩和にも役立ったわけだが、育成面に関する現状をトレセンの職員に尋ねると、「目標はすべて同じプログラムで進めることです。実現へ向け、少しずつ改善はされていますが……」と話していた。この問題は根深そうだ。
これについてV.ピュイベルデTDは、「同じやり方をする必要はないと思っています。そもそも文化や考え方に違いがあるのですから。大切なのは、根底のところで同じプランに基づいてやっていくということ」と語る。彼によれば、今後のサッカー界に必要になってくるのは、チーム内での個人バランスやセルフ・アセスメントだという。
「クリスティアーノ・ロナウドを扱うように全員を扱ってもうまくいかない。それぞれの選手の個性に適した指導、接し方をすること。そして、チーム内に違うタイプの選手を配置して、それが全体として機能するようバランスをうまく取ること。これが強いチームを作る鍵でもあります」
後者に関しては、すでに成功させているがゆえ、現ベルギー代表の躍進があるのだろう。これに加えて、『ヘット・ラースト・ニュース』紙のルディ・ヌイエンス記者は「ウィルモッツの存在は大きかった」と指摘する。
「彼はもともと豪快な人柄で求心力もあるが、選手時代にドイツ(シャルケ)やフランス(ボルドー)でもプレーしていたことで、常に違うアイディアや感覚を持っていた。この多国籍軍を束ねる指揮官として、まさにはまり役だったのです」
アシスタントコーチだったウィルモッツは12年5月、突然辞任した前監督レーケンスの後任選びが難航する中、半ば協会にとって苦肉の策で任命された。ところが着任まもない8月、隣国で最大のライバルでもあるオランダを親善試合で4-2で下すという快挙をやってのける。この象徴的な勝利によってチーム、そして国民の信頼を勝ち取り、ウィルモッツ体制が軌道に乗るきっかけになった。
振り返ると、ベルギー代表の今日の成功は『ビジョン2000』の失敗から始まっていた。日韓W杯後に長期育成プログラムを立ち上げた頃は、13年後にFIFAランキング首位に立つ姿など想像していなかったかもしれない。ただ、今後も好調が続く保証はどこにもないと、V.ピュイベルデTDは慎重だ。
「確かに協会の取り組みは実を結んだ。現在の代表メンバーは、それによって収穫できた特級のフルーツだ。しかし毎年、特級を収穫できるとは限らない。素晴らしい建築物を造る技術は習得できたとしても毎回、最高級の木材が手に入るとは限らないようにね」
将来へ向けた取り組みとして、彼は2つのポイントを挙げた。1つは、選手を取り巻く環境を「プロ化」すること。例えば指導者だけでなく、実体験からアドバイスをくれるような元選手を選手の身近に置く。そうすることで迷った時や壁にぶつかった時も、正しい方向に導くことができる。もう1つは、時代やサッカーのトレンドの変化などに対応して、方針やシステムも柔軟にどんどん変えていくことだ。
「仮に、子供だった頃の私が父親に祖父の写真を見せられて『おまえのおじいさんはこの国の首相だったんだよ』と言われたら、素直に信じたでしょう。でも同じことを私が9歳の息子にやったとしたら、彼はすぐにネットで調べて本当かどうかを確かめる。前は機能していたやり方が、今でもするとは限らないのです」

V.ピュイベルデ氏は育成を“川”にたとえた。
「選手は水。いろいろな源流から流れてくる。そうして一つの川に集まる。その川が、我われ協会や指導者、両親などです。川は集まって来た水を、正しい方向へ導こうとする。しかし中には途中で逸れて支流になったり、近くの池に溜まって終わる場合もある。最終的な目的地は大海です。そこに到達した後は、どこにでも羽ばたける。我われの使命は、水が大海まで流れ出せるよう導いていくことです」
ベルギー代表の、様々な人種が協力して一つの作業に取り組む姿勢は、本心では統一を望んでいる国民のシンボル的存在となっている。彼らが活躍すればするほど、国民は、ベルギーの一体感を実感するのだという。彼らの使命は偉大だが、このメンツ、簡単にひねられるほど、ヤワではない。
Photos: Getty Images, Yukiko Ogawa



Profile
小川 由紀子
ブリティッシュロックに浸りたくて92年に渡英。96年より取材活動を始める。その年のEUROでイングランドが敗退したウェンブリーでの瞬間はいまだに胸が痛い思い出。その後パリに引っ越し、F1、自転車、バスケなどにも幅を広げつつ、フェロー諸島やブルネイ、マルタといった小国を中心に43カ国でサッカーを見て歩く。地味な話題に興味をそそられがちで、超遅咲きのジャズピアニストを志しているが、万年ビギナー。