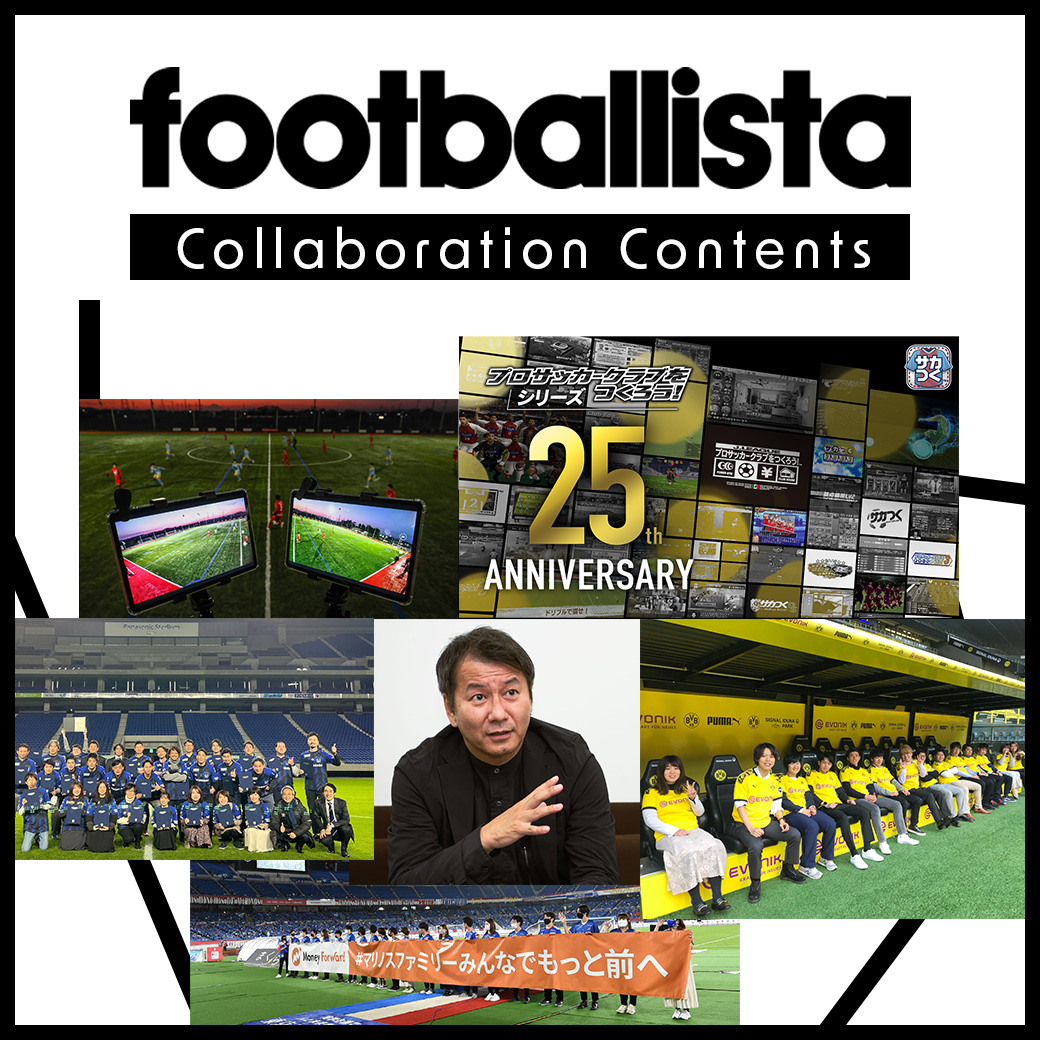清水エスパルスの公式YouTubeチャンネルのなかで更新される『カイのカイセツ』が人気を博している。ホワイトボードを使った丁寧な解説がわかりやすい。この動画で松崎快が戦術に詳しく、海外サッカーの戦術にも造詣が深いことを知ったファン・サポータ―も少なくない。そこで今回は本人に直撃。
後編では、参考にできる戦術やプレーの自身への落とし込み、指導者や解説業への興味、戦術と感覚のバランスなどについて、サッカーライターの清水英斗が深堀した。
<清水エスパルス公式SNS一覧>
<「カイの解説」>
中間ポジションは「5」ではなく「3」
――『カイのカイセツ』は色々面白い内容がありましたが、個人的に一番面白かったのは、中間ポジションの考察でした。縦方向の立ち位置を0~10という数字で表して、0が相手ボランチ側、10が相手センターバック側とすると、中間ポジションは5ではなく、実際は3だと。そういう説明の仕方をした選手は今までいなかった気がします。
「感覚的には持っていたんですよ。中間ポジションって、真ん中よりも手前側だなと。ただ、それを外に説明するとき、数字を使ったらわかりやすそうだ、という感じで使いました」
――中間ポジションという言葉を真に受けると、間は5だけど、守備側の身体の向きがあるから、実際は相手ボランチの背中に近づいた3くらいが有益な中間ポジションだと。選手目線が感じられ、面白かったですね。これは自分で感覚的に気付いたのか、それともお手本となる選手を見て気づいたとか、何かきっかけがあったんですか?
「これは自分である程度、色々なものを見つつ、大体こうだろうと思っていました。それを一番確信できたのが、東京五輪の日本対スペインですね。スペインのインサイドハーフ(ペドリ、ミケル・メリーノ)がそんなふうにプレーしていたので、これでいいんだと。3の位置からスタートすると、日本の最終ラインに管理されず、中盤のラインも届かず、フリーで前を向ける。でも5の位置だと、最終ラインに感知されて前を向けなくなってしまう。背後へランニングするつもりなら、深く立ち位置を取ったほうがいいですけど、その辺りはスペインのポジショニングを見て、確信しましたね」
――スペインはそういうお手本になりやすいですか?
「そうですね。『配置で語るのは好きじゃない』と言ったことにもつながりますが、配置で語るとうまくいっているように思えても、意外とはまることが多くて。そこから2メートル動かすとか、ピッチの中では可能なので。
さっきのスペインの中間ポジションもそうですが、当時の試合で一番インサイドハーフに多く見られたのは、アンカーに前を向かせるプレーでした。センターバックが日本のプレッシャーを受けたとき、インサイドハーフがライン間から下りて縦パスを受け、アンカーの選手に落として前を向かせる。このシーンがすごく多くて。これを配置論で語ると、初期配置で日本とかみ合っているからインサイドハーフは消されているんですけど、実際はライン間から落ちることで、味方で前を向く選手を作れる。そういう個人戦術のレベルが高いところを、すごく参考にしましたし、自分のプレーもこれでいいんだと確信を持てました。全体像というよりは、そういう細かいところを見ているかもしれないですね。今の僕は」
――なるほど。逆にシステムみたいな全体像は、実際に試合をするときはどれくらい意識するんですか?
「ある程度は意識します。守備だったら[4-4-2]とか、[5-3-2]とか、[5-4-1]とか、[4-5-1]とか、それで相手のやり方は大体は決まってくるので、それに対して空くところを探しつつ。そこから、誰が自分のところに来るのか、誰が自分の近場の味方にプレッシャーをかけるのか、人に食いつく傾向が強いのか、ゾーンを管理したいのか。ただ、個人の能力はそれぞれ違って、足の速い選手もいれば、そんなに速くない選手もいるし、ボールを取り切れる選手もいれば、できない選手もいます。そういうものを見ながら、それぞれに対するギリギリの距離を探ったりしますね。どこまで出て来られるのか、みたいなところは見ます」
スタニスラフ・ロボツカなどバグを起こせる選手が好き
――なるほど。これは選手としての試合の入り方でしたけど、欧州サッカーを含めて見る側になったときは、どんなところから見ていくんですか? たとえば、キックオフ直後にどんなところから見ていくのか。……



Profile
清水 英斗
サッカーライター。1979年生まれ、岐阜県下呂市出身。プレイヤー目線でサッカーを分析する独自の観点が魅力。著書に『サッカーは監督で決まる リーダーたちの統率術』『日本サッカーを強くする観戦力 決定力は誤解されている』『サッカー守備DF&GK練習メニュー 100』など。