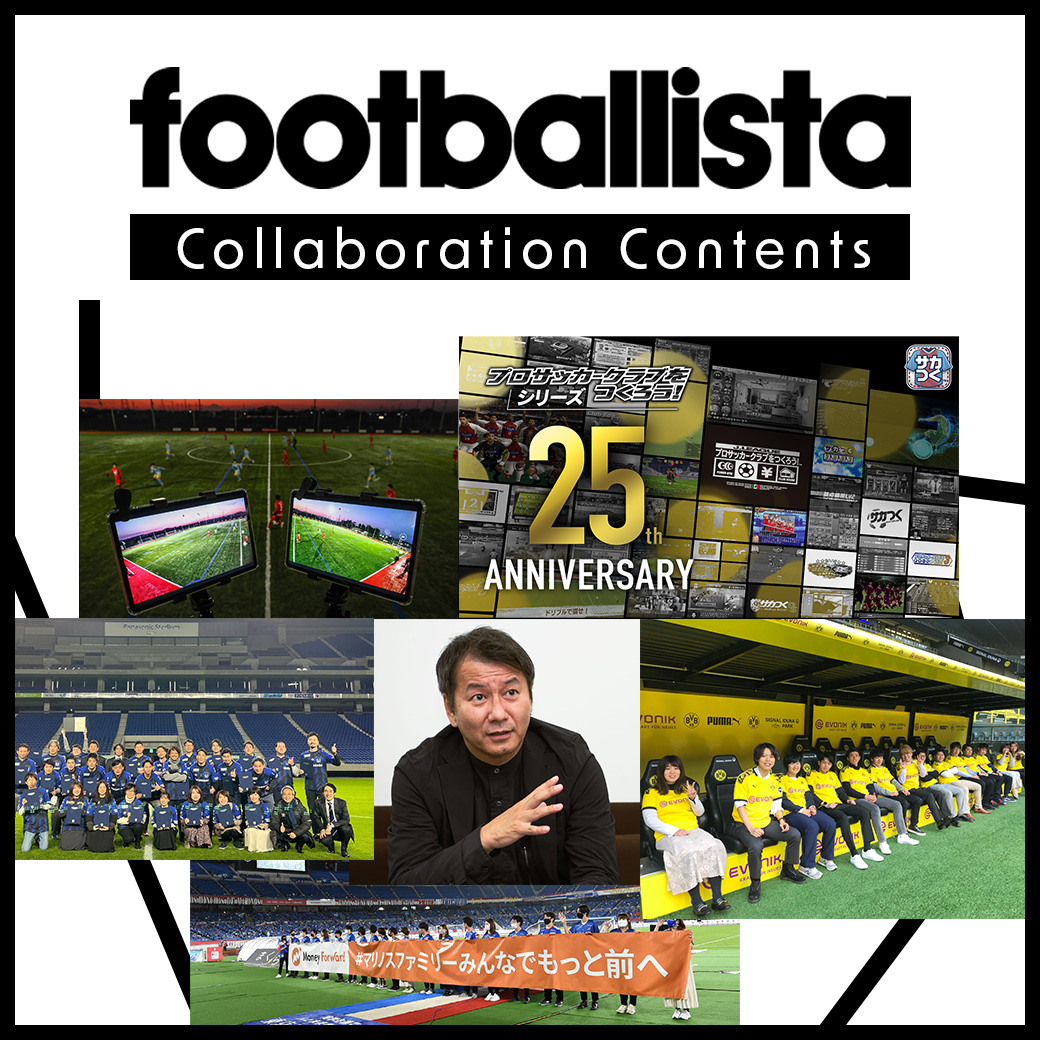「2024シーズンを最後に川崎フロンターレを卒業することになりました」——数々の思い出が詰まった1000字近い別れの言葉をクラブ公式サイトに残し、“ドゥさん”の愛称で親しんできたサポーターから惜しまれつつも、川崎Fを去った二階堂悠コーチ。マスコットのカブレラいわく「7つのタイトル獲得には、絶対に必要不可欠な存在だった」名参謀に、鬼木達体制を支えた8年間を振り返ってもらった。
「引き出しがないといけない」鬼木監督を支えた準備力
——2017年に鬼木達監督の就任とともに川崎フロンターレのコーチとなり、J1リーグで初優勝しました。主な仕事に対戦相手のスカウティングがあったと思いますが、鬼木監督との仕事の進め方はどんな形だったんですか。
「そこは最初から意見をすり合わせました。毎試合相手の分析レポートをスタッフに出してるんですけど、それは1枚にまとめています。予想メンバーと攻撃と守備の特徴やデータを載せたり、セットプレーはこういう形ですという内容ですね。
例えばモンテディオ山形での石﨑(信弘)監督の場合は、それを選手も見れるように拡大してリラックスルームに貼っておく形でした。気にする選手がそれを見ておく感じですね。オニさん(鬼木監督)の場合は『それは選手には見せなくてもいいや』と言って選手には見せなかったです。選手に相手の情報を与える時は、試合に向けたミーティングで統一していました」
石﨑信弘監督、高橋健二コーチ、二階堂悠コーチ、内山俊彦コーチ。
次の舞台での活躍もぜひみなさん追いかけて頂ければと思います。
本当にありがとうございました。#montedio pic.twitter.com/dtfM9QCEKS— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) January 9, 2017
——スカウティングは平均何試合ぐらい相手を分析するものなんですか?
「最低ラインが6試合というのは自分の中で決めてやってはいましたけど、本当に勝ちたい時は7、8試合。ACLでわからないチームに関しては全試合を見て分析してました。だからACLの9月開幕はやめてくれよと思ってました(笑)」
——大会によっては相手の全試合ですか。その分析をミーティングでは10~15分ぐらいの映像に編集して選手に伝えてるんですよね。
「なるべく10分以内にしたかったんですけど、オニさんからは『無理に短くしないでいいので、強調するところもしっかり強調してほしい』と言われていました。なので12、3分が多かったです。僕はちょっと長いかなって思っていましたが、選手もそれで慣れてましたね。その後にオニさんが説明する流れでしたし、そんなに説明もなくこのまま練習に行こうという時もありました」
——鬼木監督は相手の情報を選手に与えすぎないように制限していた印象もあります。
「そこは風間八宏監督の影響もあるかもしれませんね。風間監督のいいところは取り入れてっていう感じなのだと思いますし、そこは本人も言っていました。スタートとして、相手はあまり関係ないっていうところが考えにあるかもしれません」
——相手はあまり関係ないって言われると、分析担当としては複雑な思いもあるのでは(笑)。
「最初の頃は『ドゥ(二階堂コーチの愛称)は相手のことをこう言ってるけど、実際は自分たちだから』って選手に言って説明し始めていました(笑)」
——何試合も分析して情報がたくさんある分、あれもこれもと伝えたくはならないものですか。
「ポイントは攻守それぞれ2つか3つに絞って、プラス、今はこの選手の調子はいいかとか、FWのシュートの仕方だったり個人の映像を入れていました。最後の方はオニさんが言いたい部分もわかってたんで、それを優先的に持っていくようにしていましたし、ミーティングには出さないけど、予備を自分で持っておくようにしています。もしオニさんから『こういうシーンはない?』と言われたらすぐ出せるように、こちらも2段構え、3段構えで準備していました」
——準備したものをストックしておく、と。
「そうですね。例えばオニさんに『フォーメーションは何枚?』って聞かれた時に『3枚です』とか『前は4枚でやってましたけど、何試合前から3枚です』とかすぐに答えられる引き出しがないといけない。監督よりも多く試合を見て、映像も含めて、情報やいろいろなことを頭に入れておかないといけないというのは常に心がけていました」
まもなく搭乗。家族と通話中のユウにケンゴとショウタも参加。
鬼木監督と二階堂コーチは早くも戦術ミーティング⁉︎中山通訳からはボードゲームしているだけですよと突っ込まれていました。1人、落ち着いて座っていたのはタツヤ。現地でも可能な限り出しますね。【広報】 #frontale pic.twitter.com/xY0soshMWW— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) March 12, 2017
「サッカーはテンションのスポーツでもある」
——相手の情報を伝える際に、客観的な情報と自分の主観を入れた情報のバランスってどれぐらい意識するんですか。
「オニさんは『ドゥはどう思う?』とよく聞いてくれていたので、例えば『リーグの中だと堅守って呼ばれてる失点が少ないチームですけど、実際はそうでもないんですよ』みたいにデータ+僕の主観を含めて伝えたりしていました。サッカーは一概に、データでこう出ているからここが弱いとか強いとか言えない側面もあって、そこが分析の面白さでもあり難しさでもあるかなっていうところですね」
——なるほど。
「最近のJリーグって、クロスに強ければ失点を防げる流れがあるんですよ。クロスの時はキーパーも含めてCB、SBが中に絞って、サイズのある選手が多くいるから誰かしらがクリアできる。あとはコーナーキックも含めてゾーンが増えてきて、中に人が多いので横からのボールに対して失点を防げれば、全体の失点数が少なくなる傾向があったりします。逆に攻撃する側も最終的にクロスを選択するチームが多い。でも、フロンターレは中から攻められるので、そこの違いが他と出るのかなって感じますね。相手はクロスで失点をしていなくても、自分たちがボールを動かして、クロスではなく中から攻めたら意外と得点を重ねることができたりとかも結構あるので」
——分析を試合に生かす上で大事にしていた部分は?
「結局、分析は相手の強いところ、相手の弱みのところになります。それと同時に相手の分析を伝える時には、それが自分たちの強みと弱みに噛み合っていないと意味がないのが分析だと思ってます。
川崎フロンターレはロングボールを使うのがあまり得意ではないのですが、でも相手がロングボールの対応が弱いとする。それでロングボールであそこを狙え!という伝え方になって、チームが意図していることとちょっと違うとなると、それは相手しか見てない分析になりますよね。そういう意味で、自分たちの強みや今の課題を相手の分析とリンクさせるのは意識はしていました。例えば前の試合、ワンツーの対応で自分たちが何回かやられていた場合は、次の相手もワンツーはそこまで多くはないかもしれないけど、こういうの時々あるよとか。そこの課題はつなげられるようには常にやってましたね。相手の分析だけど自分たちも課題克服だったり、成果を積み上げていかないといけないですから」
——選手の分析に関しては、どういうところに注視しているのかは気になります。
「戦術やどういう配置なのか、噛み合わせがどうこうというのは、専門的に見ている人ならわかると思うんです。もちろん、分析担当はそういうところも見ないといけないのはあるんですけど、僕が思うのはそれプラス、サッカーはテンションのスポーツでもあるので、疲れてくるとこの人はこうなっているとか、選手個人個人の性格や仕草をTV映像で見ています」
——テンションを見ている?……



Profile
いしかわごう
北海道出身。大学卒業後、スカパー!の番組スタッフを経て、サッカー専門新聞『EL GOLAZO』の担当記者として活動。現在はフリーランスとして川崎フロンターレを取材し、専門誌を中心に寄稿。著書に『将棋でサッカーが面白くなる本』(朝日新聞出版)、『川崎フロンターレあるある』(TOブックス)など。将棋はアマ三段(日本将棋連盟三段免状所有)。Twitterアカウント:@ishikawago



 (@kawasaki_frontale)がシェアした投稿
(@kawasaki_frontale)がシェアした投稿