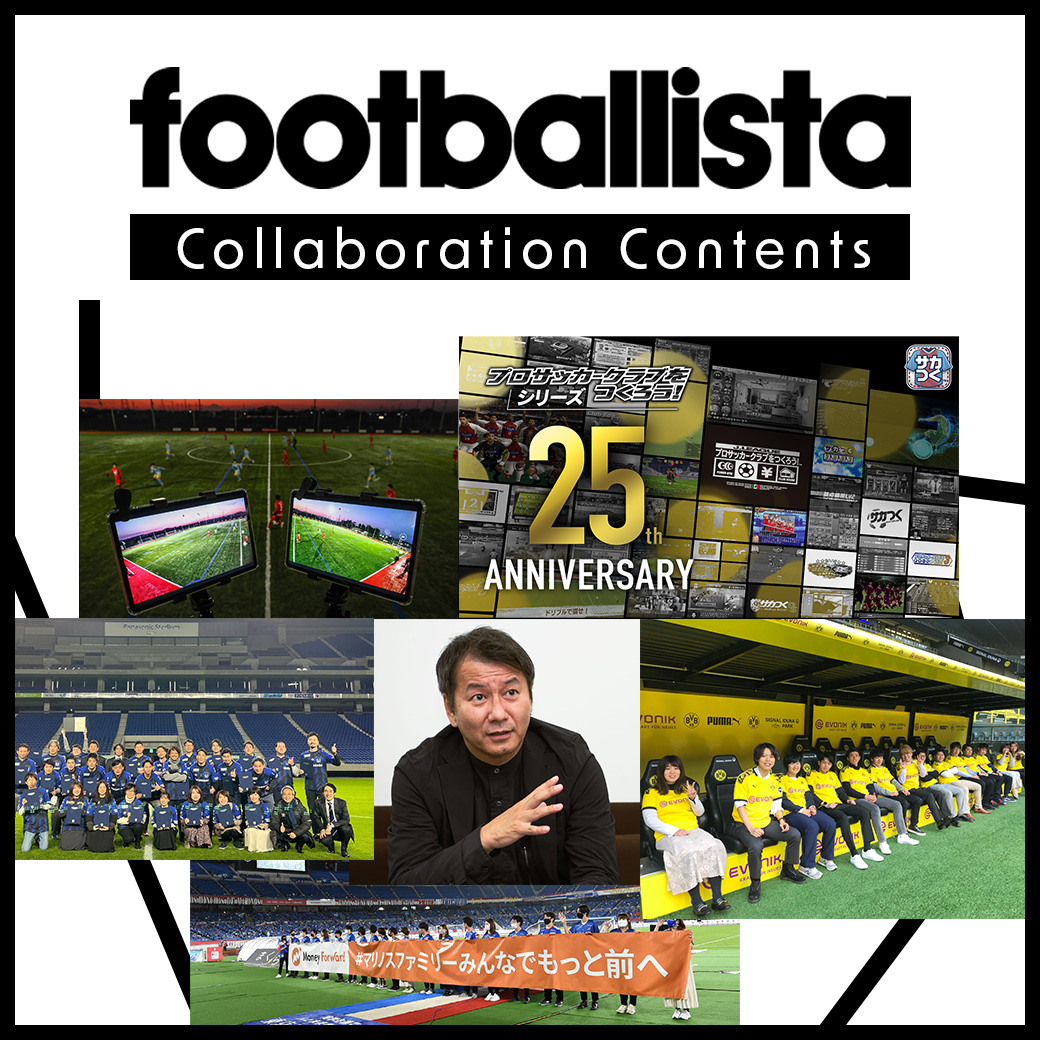埼玉スタジアム2002でオーストラリアと激突した北米W杯アジア最終予選第4節は1-1で終わり、連勝と無失点は「3」で途絶えるも無敗を維持した日本代表。堅守をこじ開けて追いついたミラーゲームで見出した答えを、『森保JAPAN戦術レポート 大国撃破へのシナリオとベスト8の壁に挑んだ記録』の著者、らいかーると氏が分析する。
アウェイのサウジアラビアまで倒して3連勝と、最終予選らしさをますます感じさせない順風満帆の日本。唯一の“らしさ”といえば、ターンオーバーをほぼ封印していることだろうか。オーストラリアを迎え撃ったホームゲームでの先発も体調不良で欠場の遠藤航に代わって右ボランチに入った田中碧の起用は例外として、左シャドーの鎌田大地を久保建英に入れ替えて右に回すくらいであった。その理由は最終予選のクオリティに対抗するためなのか、[3-2-5]の積み上げを狙っているのか、はたまた[3-2-5]をこなすための選手層が足りていないと考えているか。答えは森保一監督の頭の中にある。
𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘
LINE-UP
1 #鈴木彩艶(GK)
3 #谷口彰悟
4 #板倉滉
5 #守田英正(C)
7 #三笘薫
8 #南野拓実
9 #上田綺世
10 #堂安律
16 #町田浩樹
17 #田中碧
20 #久保建英𝐒𝐔𝐁
12 #大迫敬介(GK)
23 #谷晃生(GK)
2 #菅原由勢
6 #藤田譲瑠チマ
11 #前田大然
13 #中村敬斗
14… pic.twitter.com/CZLJQY3pCF— サッカー日本代表
(@jfa_samuraiblue) October 15, 2024
ミラーゲームの打開策はミシャ式の[4-1-5]
オーストラリアのキックオフで始まった試合は、左ウイングバックの三笘薫方面を狙ったはずのハイボールで幕を開ける。しかし、その行方は3バック中央の谷口彰悟の周りに飛んでいった。両チームを通じたキックの精度を考慮すると、ピッチコンディションにも問題があったのかもしれない。興味深いのは、高さで勝てそうな右ウイングバックの堂安律とは逆サイドを狙い撃ちにしたこと。おそらく揺さぶりたかったのは三笘の立ち位置で、守備を意識させたかったのかもしれない。
そんな流れから、オーストラリアのプレッシングの意図がはっきりする。日本の[3-2-5]に対して[5-2-3]を基本としながら敵陣から果敢に前へと出てきた。いわゆるミラーゲームだ。ミラーゲームでは配置を噛み合わせることで守備の基準点が明確になりやすいものの、逆にボール保持でどうズレを生むかという問題が出てくる。そこでオーストラリアは、GKジョー・ガウチを使って擬似的な4バックを形成してCFの上田綺世を牽制するという解決策を提示した。同じく前線からボールを奪いに行きたい日本だが、パスが回ってきても慌てないガウチまで行くかというどうか迷いが出てくる。深追いした結果としてロングボールを浴びることに少しばかり嫌な思い出を抱えている日本からすると、オーストラリアの策は至極真っ当な対策と言える。
そんな開始2分の段階で動いたのは左ボランチの守田英正。3バックが同数のプレッシングを受けた時に4バックへと変化する。サウジアラビア戦と同じ流れの[4-1-5]となった配置が彷彿とさせるのは、Jリーグでお馴染みの「ミシャ式」だ。このミシャ(ミハイロ・ペトロヴィッチ)監督の代名詞である可変の特徴は、ウイング化したウイングバックが質的優位を見せやすいこと、1トップ&2シャドーがコンビネーションを発揮しやすいこと、SB化するCBが攻撃参加できることにある。
3バックの雰囲気を見せると必ずプレッシングに出てくるオーストラリアに対して、日本はボール保持の安定を優先しているように見えた。まずはウイングバックの質を示せるかどうかの我慢比べと言ったところだろう。象徴的だった場面は、トランジションから堂安がカウンターに出た3分前後。オーストラリアはためらいもなくファウルで止めている。日本が最も警戒されていたのはカウンターであり、攻守の切り替えの連続だったのかもしれない。
守田を下げる[4-1-5]には[5-4-1]のミドルブロックに移行するが、通常の[3-2-5]には[5-2-3]でミドルプレッシングからハイプレッシングへと仕掛けてくるオーストラリア。おそらくはすべて準備されていたのだろう。5分までは噛み合わせが目まぐるしく変化する攻防が繰り広げられていた。
/
最初のチャンスは日本
\今日先発の田中碧のパスから
久保建英がシュート
AFCアジア最終予選
日本×オーストラリア
#DAZN ライブ配信#代表みようぜ #サッカー日本代表 pic.twitter.com/3zbA69j32H
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 15, 2024
[3-2]+GKでボールを循環させるオーストラリア
日本が[4-1-5]によるボール保持の安定を優先したので、オーストラリアは[5-4-1]で構える形が多くなっていく。両脇のCBを守備の基準点とするウイングは、中央に絞ってボールをサイドに誘導したため、左シャドーの南野拓実や久保が相手のライン間でボールを受けるシーンはなかなか訪れない。
堂安とのポジションチェンジでボールを引き出すことを狙う久保は、オーストラリアのボランチの脇というよりは、そのウイングの脇に出てくることが多かった。一方で南野は相手の中盤に影響を与える場面が多く見られていく。ボール保持を落ち着かせるために、裏を狙うより敵を動かしてスペースを作ることを重視したのだろう。見方を変えれば上田に3バックが集中するので、残る9対7のどこかで粗が発生していく仕組みになっているが、問題は中央の枚数が足りなかったことだ。……



Profile
らいかーると
昭和生まれ平成育ちの浦和出身。サッカー戦術分析ブログ『サッカーの面白い戦術分析を心がけます』の主宰で、そのユニークな語り口から指導者にもかかわらず『footballista』や『フットボール批評』など様々な媒体で記事を寄稿するようになった人気ブロガー。書くことは非常に勉強になるので、「他の監督やコーチも参加してくれないかな」と心のどこかで願っている。好きなバンドは、マンチェスター出身のNew Order。 著書に『アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます』 (小学館)。