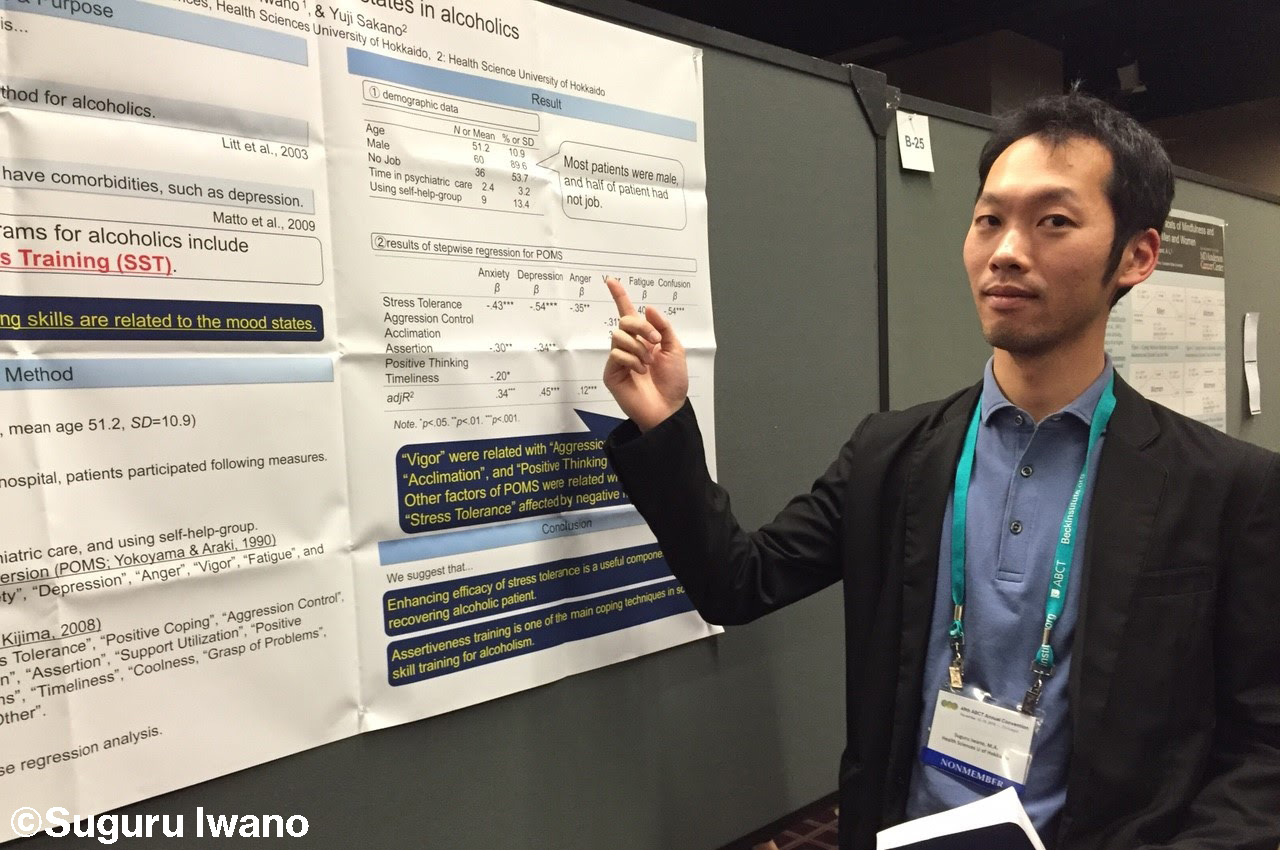11年ぶりの“再会”は、1万3244人という凄まじい観衆の中で果たされた。J1でも、J2でもない、J3の1試合にそれだけの熱量が集結したのには理由がある。AC長野パルセイロと松本山雅FC。長野県に本拠地を置いた両者が激突する『信州ダービー』だったからだ。では、この一戦にはどういう歴史上の経緯があり、どういう意味が秘められていたのか。それを紐解く適任者は、この人しかいない。長野県出身ではないのに、長野県に家を買い、生涯を過ごすことを決めてしまった男。松本山雅FCを2009年から取材し続けている大枝令が、“傍観者”の視点と、“当事者”の視点から、信州ダービー“第2章”について振り返る。
「信州ダービー・新時代」の幕開け
5月15日、長野Uスタジアム。
川中島古戦場にほど近いこの地が、令和の合戦場となった。対峙したのは武田と上杉ではなくAC長野パルセイロと松本山雅FCで、雌雄を決するツールはサッカー。互いの地域から付託を受けた両チームの選手たちがピッチで見せるパフォーマンスは、「圧巻」の一言だった。長野のホームゲームで史上最多となる1万3,244人による物言わぬ熱気も大いに後押し。「信州ダービー・新時代」の幕開けを十分に予感させた。
Jリーグ30周年に重なる記念すべき日に組まれた一戦で、野々村芳和チェアマンが視察に来訪。後日にはYouTubeのJリーグ公式チャンネルで、バックヤードに密着した16分26秒の動画も公開された。Jの最下層リーグにありながら堂々と胸を張れるだけの熱量を備え、なおかつ後日に問題化するトラブルも報告されていない。カテゴリーが上がれば上がるほど、そして声出しが解禁されれば、その熱量はさらに跳ね上がるだろう。
しかし実際に蓋を開けてみるまで、関係者は手探りだった。なにしろ11年ぶりの顔合わせ。互いに地域リーグやJFLで我先にとしのぎを削っていた2006〜11年とは状況が異なる。選手も、フロントスタッフも、サポーターでさえも入れ替わっている。Jリーグに参入してからたどった道のりも、鮮やかなコントラストを描く。その歩みが重なることは、幸か不幸か一度もなかった。
「正直、どうなるかわからない」
「どういうテンションで行けばいいのか」
松本の古株社員やサポーターは、やや戸惑った様子でいた。無理もないのだ。アマチュア時代の松本にとって信州ダービーとは、一つしかない(と信じ込んでいた)Jリーグ行きの切符を先に入手するための生存競争の場。同じ県で覇を競うライバルとして――という意地やプライドは当然ありながら、別種の抜き差しならない理由が根底に横たわっていたのだ。
崩れた「生存競争」というキーファクター
長野側はしかし、受け止めが違ったようだ。今回の信州ダービーに際し、長野は過去に携わったキーマンをピックアップする6回の特設インタビューを企画。当時を知る人間が数少なくなっていることから、新たなサポーターに向けて発信していく試みだ。その第1回で、前身の長野エルザSC創設者・丸山朗氏と現代表取締社長の町田善行氏が当時を回顧している。以下、そのやり取りの一説を引用する。
「松本はサッカー人口もサポーターも多いですし、アルウィンもあるから。(中略)『何をやっているんだ、早く上に行け!』という気持ちで、山雅が上にいるのが当然だと思っていましたよ」(丸山)「特にライバル心はなかったですよね。私たちは『一歩ずつやっていくから』と話していましたし」(町田)
「どうぞお先に」と言わんばかりの、鷹揚としたスタンスがにじむ。長野県サッカー界のパワーバランスを解説すると、歴史的にも松本を中核とする中信地方がサッカーの熱源であり続けた。全国的に後進県ではあるものの、例えば横浜F・マリノスと名古屋グランパスでJ1制覇を経験した田中隼磨は松本市出身。サガン鳥栖で長年プレーした高橋義希氏は、北信地方の須坂市出身ながら松本市の松商学園高を選んだ。
長野市を中心とする北信地方は、後進県の中でもさらに「不毛の地」と目されていた。上記リンク先の述懐に、その機微が記されている。外から見たらドングリの背比べなのかもしれないが、当事者たちには切実な問題で、それを外から興味深く覗くのもまた楽しみの一つ。だからこそ映画『クラシコ』などを媒介として、このカードがじわりと知名度を獲得したのではないだろうか。
松本が2012年にJ2に参入し、時は過ぎてJ3が2014年に新設。長野はそこに加わり、人口210万人(当時)の信州に2つのJクラブが並立することとなった。要は、松本からすると「生存競争」というキーファクターが崩れたのだ。切符は実は2つあった――というよりは、思いがけない方向からもう1枚の切符が降ってきた。「なんかちょっと、釈然としないですけど」。松本のあるスタッフは、そうこぼしていたが。
ただ、敵愾心だけでも相当な熱気を帯びていたことは想像に難くない。今回の「新章」はまさにピュアなライバル意識をぶつけ合える、幸せなビッグゲームと言えるだろう。

歴史が語る松本と長野のライバル意識
では、ライバル意識とはどのように醸成されてきたのか。関係者の証言を丹念に紐解いて総合すると、やはり松本のサポーターがまず熱源となった――とみていい。丸山氏は上記の対談記事で、こう述べている。
「地域的に見ても、長野市民が松本市民に対してライバル心を持っていたかと言えば、そうではなかったと思います。あくまで、みんな同じ長野県の一つの町だと。でも、松本は違うんです(笑)」
実際に長野市出身の知人・友人に聞いても、「松本に敵対心はない」と口をそろえる。おおらかな地域性なのか、県内において最も「ヒト、モノ、カネ」が集まる無意識の余裕なのか、そもそも松本が眼中にないのかは判然としない。ただ仮に自分が長野市出身の若者だったとすると、長野自動車道を南下して松本の中心市街地に行くのなら、もう30分プラスして北陸新幹線で東京駅に出てしまうのではないかと思う。
だが、松本は違う。人口規模でも経済規模でも後塵を拝している。新幹線も通っていないから、東京に出るまでは特急あずさに2時間30分以上も揺られなければいけない。冬季オリンピックも開催していない。半ばプロレス的な側面もあったかもしれないが、鬱積したコンプレックスはサッカーでマウントを取ることによって解消可能となる。
さらに歴史的経緯のレイヤーが重なり、いよいよ分断は決定的なものとなる。松本市を含む中南信地方は「筑摩県」だったが、1876年の第二次都府県統合によって廃止された。以降は分県論が折に触れて噴出。最も有名なのは1948〜49年の出来事だろう。2013年1月発行の「広報ながのけん」内のインタビューで、初代広報室長の太田今朝秋氏はこう述べている。
「県庁舎の一部が焼失したことを発端に、北信側(長野県の北部・東部)と南信側(長野県の中部・南部)の対立が激しくなり、県議会が分県についての特別委員会を設置し、審議の結果、分県案は委員会では賛成多数となりました。しかし、この案が通過すれば、長野県は2つに分かれるという本会議の日に、分県に反対する北信側は約千人の県民を動員。そして、委員長が特別委員会の結果を報告するため登壇するや否や傍聴席と議会の周囲から一斉に『信濃の国』の大合唱が始まりました。これを聞いた委員長は、『信濃は一つだ』という思いが込み上げ、壇上で絶句してしまったそうです。結果はご存知の通り、分県は不成立となりました」
併合されて消滅した行政区分は全国を見渡せば他にいくらでもある。2022年を生きる人々が直接体験していないにせよ、今もなお「語られる」時点で尾を引いていると言える。例えば旧筑摩県の一部は岐阜県中津川市などに移行されているが、それをいまだに根に持っている人がどれだけ存在するだろうか。寡聞にして知らない。
松本から長野へと伝播していった熱量
……



Profile
大枝 令
1978年、東京都出身。早大卒。2005年から長野県の新聞社で勤務し、09年の全国地域リーグ決勝大会で松本山雅FCと出会う。15年に独立し、以降は長野県内のスポーツ全般をフィールドとしてきた。クラブ公式有料サイト「ヤマガプレミアム」編集長。