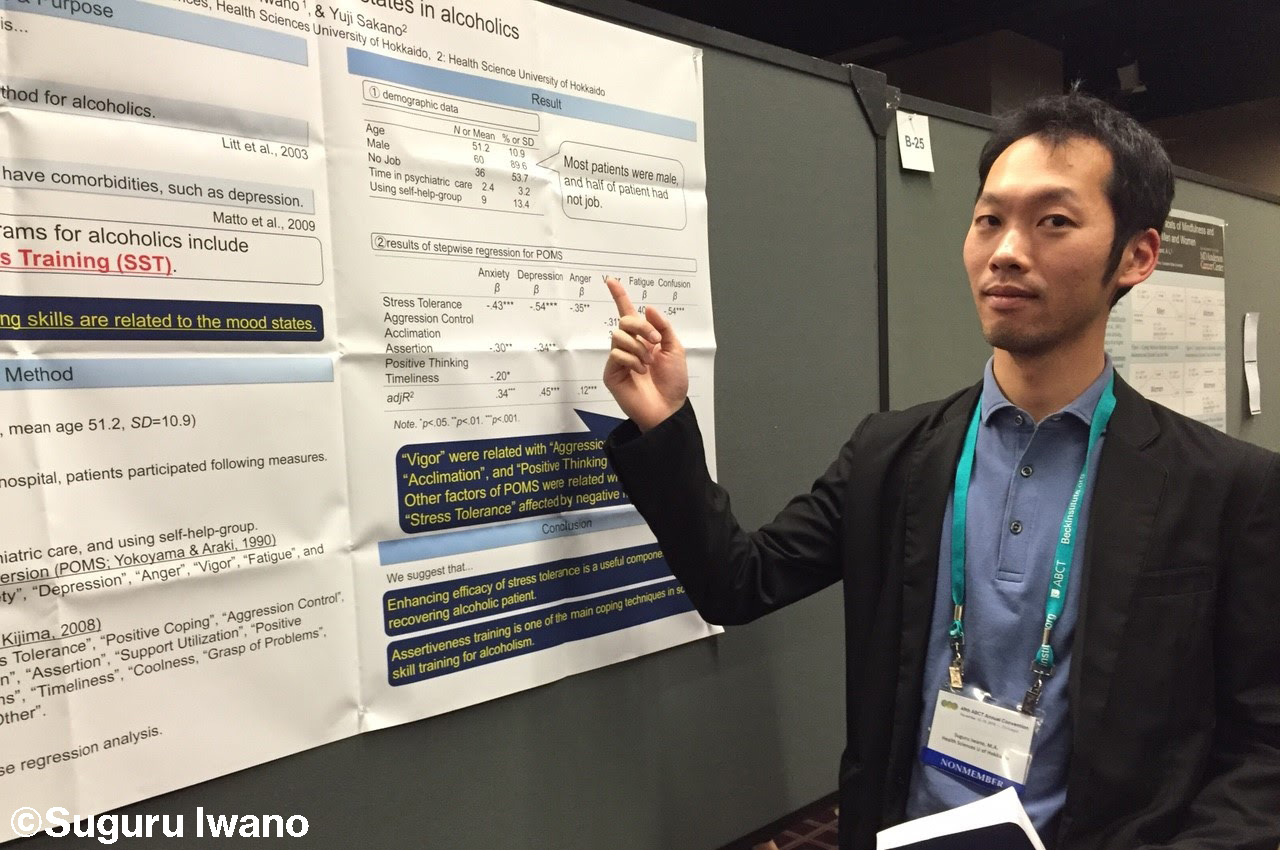“バッドボーイ”は消えてゆくのか。現代サッカーの「優等生」論について:イングランド編
ピッチ上での愚行に対しては仕方ないとして、SNSを含むピッチ外での言動でも批判されるネイマールを見ていてふと思う。最近は“愛すべき悪童”ポジションのスター選手がめっきり減ったなと。かつては私生活で多少ハメを外したって、プレーで結果を出せばそれでOKだったフットボーラーだが、現代において選手は「商品」となり、そして品行方正を求められるようになった。ビジネス化の影響、社会全体の変化……良いアスリートとは良い人間である、と考えられるようになった背景には何があるのか。叩かれて当然だと思う反面、その風当たりの強さに昔は面白かったなと思ったりもする今日この頃。主要国それぞれの“バッドボーイ”をめぐる変化について、そんな時代を懐かしみながら各国の書き手に綴ってもらった特集のイングランド編。
※『フットボリスタ第84号』より掲載。
バッドボーイの種類は、その国の伝統的な「カッコよさ」の定義と結びつく。英国なら、まずは「ハードな男」だろう。ラテン系の“汚い”選手とは違い、真っ向から勝負を挑む彼らを「悪」と呼ぶのは気が引けるが、今では考えられないような逸話が残っているのも事実だ。
1960、70年代にリーズで黄金期を築いたノーマン・ハンターは、1974年に選手協会の年間最優秀選手に選ばれる名プレーヤーだったが、“Bites Yer Legs”(足に噛みつく)の愛称が示す通り、激しいタックルでも知られ、「旅行中の遊びのサッカーで素人を3回転するほど吹き飛ばした」と証言するチームメイトがいるほどだ。稀代のドリブラーであるジョージ・ベストもリーズ戦だけはすね当てを着用したが、別にリーズが特別だったわけではない。

同年代にチェルシーで活躍したDFロン・ハリスは“チョッパー”(なた)の異名を持つ危険なタックラーで、試合前にスパイクのポイントに消毒液をかけていたそうだ。彼ら以外にも、アーセナルのピーター・ストーリーや“アンフィールドの鉄”ことリバプールのトミー・スミスなど、各クラブに「ハードな男」がいた。
今でも英国には「男らしさ」「勇敢さ」を敬慕する“マスキュリニティ文化”が残っており、どんな美しいゴールよりも激しいタックルに会場が沸くことがある。しかし、大英帝国のプライドがそうさせるのか“マリーシア”のような欺く行為はご法度のため、フットボールの非コンタクト化が進むにつれてハードマンは居場所を失っていった。
女性問題には今なお寛容
……



Profile
田島 大
埼玉県出身。学生時代を英国で過ごし、ロンドン大学(University College London)理学部を卒業。帰国後はスポーツとメディアの架け橋を担うフットメディア社で日頃から欧州サッカーを扱う仕事に従事し、イングランドに関する記事の翻訳・原稿執筆をしている。ちなみに遅咲きの愛犬家。