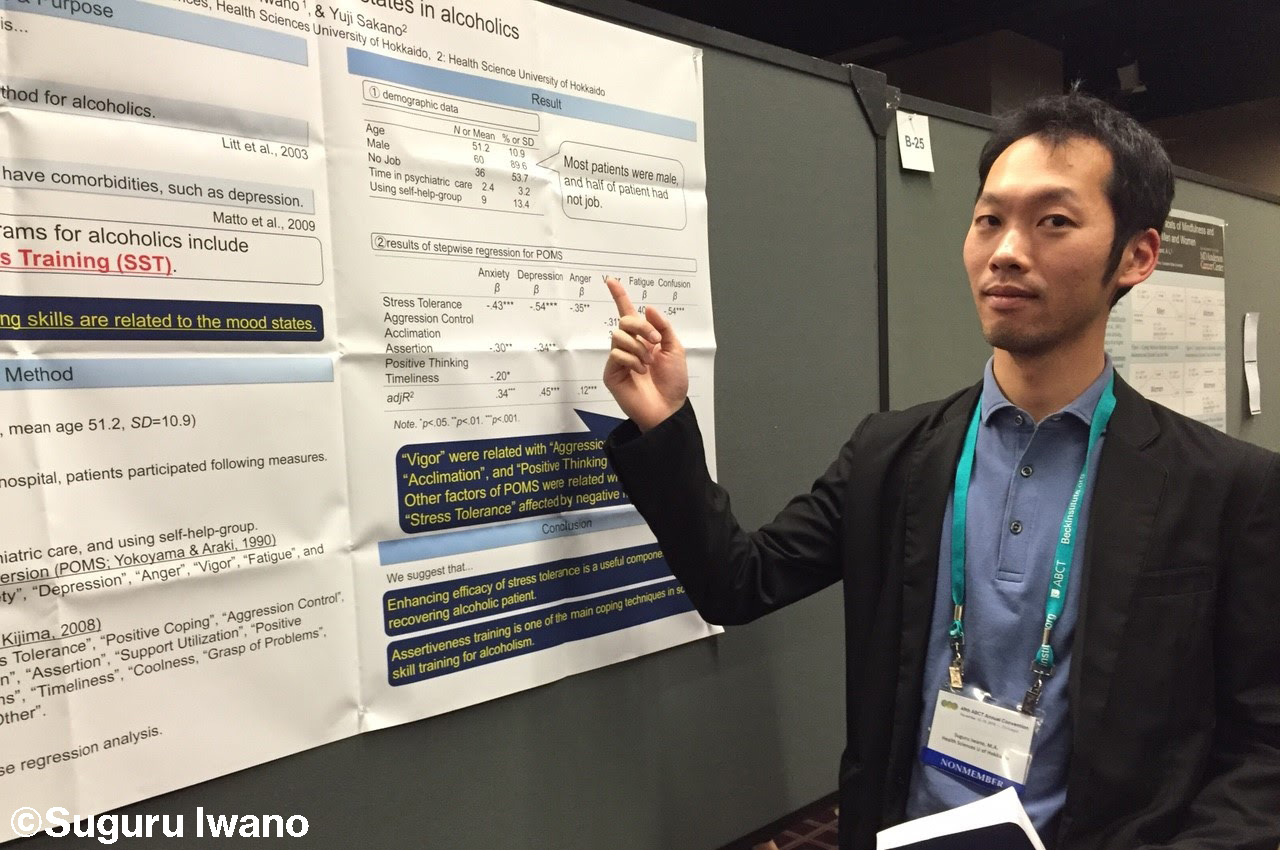白石尚久(シント=トロイデンU-21アシスタントコーチ)インタビュー
アルゼンチン、フランスでプレーし、オランダやスペインでコーチングを学ぶという異色のキャリアを歩んできた白石尚久。現在はシント=トロイデンU-21のアシスタントコーチを務める日本人指導者は、いかにして現在地にたどり着いたのか。そして目まぐるしく変化する現代サッカーに、指導者としてどう適応しているのか。彼のユニークな経歴と、データ分析を用いたトレーニング構築への向き合い方を聞いた。
サッカーにのめり込んだ男の、ユニークなキャリア
――白石さんは高校3年生でサッカーを始め、大学時代はアルゼンチンに渡りプレーされたんですよね。どのような経緯があったのでしょうか?
「小学生の頃からサッカーをしたいと思っていましたが、もともと違うスポーツをやっていたんです。中学校の部活動は、小さい頃からサッカーをやっている子たちには勝てないと思い全員初心者からスタートのテニス部を選んだのですが、高校に進んでからもやっぱりサッカーを諦めきれませんでした。それで、高校3年生になってからサッカーを始めたんです。その後はサッカー部に入るため、明治大学に進学しましたが入部テストで全然通用しなくて。サッカーができないならここに来た意味がないなと思い、強豪国であるアルゼンチンへ行ってサッカーを勉強しようと決めました。ちょうど国内でマラドーナがプレーしていた頃でしたね」
――アルゼンチンへはどのくらいの期間行かれたんですか?
「4年間です。とにかく最短でサッカーを勉強できて自分の実力を上げられる環境に身を置きたかったので、きちんとしたプロクラブの組織の中で学ぶ必要があると考えたんです。それで、まずヒムナシアというクラブのU-20に練習生として参加しました。フィジカルだけでなくボールを蹴る技術やコントロールする技術も持っていなかったので、毎日基礎から練習していました。また、試合に出ていない時も僕はベンチの監督の横に座って、ずっと目の前の試合についてのノートを取り続けました。ハーフタイムになるとロッカールームに戻りながら監督に『タカ、どんなことをメモしたんだ? 』と聞かれるので、自分たちのチームの問題点とその原因や相手チームのやり方など、ノートに書いたことを伝えていました。今思うと、あの時すでにサッカーをやりながら分析の勉強もしていたんですよね。あとはハングリーさだったり自分の見せ方だったり、外国人がどうやって海外で結果を残していくかというところも鍛えられました」

――サッカーの部分だけでなく、相当なコミュニケーション能力もいりますよね。いきなり日本から来て、チームに溶け込まなきゃいけないという。
「そうですね。当時はスペイン語も話せなかったし、お金や服を盗られたりロッカールームに入れた自分の荷物が廊下に放り出されていたりということが日常茶飯事でした。ピッチ上でも下手くそだからボールが回ってこないんですよ。11人対12人でゲームをやったなんてこともありました。ピッチ上で僕が12人目の選手、“いないもの”という扱いですね。向こうでは攻撃だけでなく、守備もやらないと周りには認めてもらえない。奪われたら奪い返して味方にパスを出して、それで初めて自分のところにもパスが回ってきますから」
――その頃からすでに監督や指導者になりたいというビジョンはあったのでしょうか?
「当時は全然ありませんでした。純粋にサッカーを学びに行ったという感じです。将来のためというより、ただ自分がやりたいことをやったというだけでした。多分ずっとサッカーをやれなかったことに対するフラストレーションが、相当あったのだと思います。アルゼンチンで4年間過ごして、ここではもう可能性がないから今度はヨーロッパでサッカーを勉強してみたいと思いました。まだ僕はサッカーをやりたいし、できると思ったからです。それでチームを探していたら、たまたまアルゼンチンで知り合ったフランスの人から『テストを受けに来ない? 』と声をかけてもらえて。それでフランスへ行き、セミプロリーグで3年間プレーしました。当時は毎日サッカーしかしていなかったですね。人の3、4倍くらい練習しました。フランスのサッカーって、右に数回パス出したらすぐ左へサイドチェンジして縦、という感じでとても速いんですよ。アルゼンチンで僕がプレーしていたチームはショートパスで後ろからきっちり繋いでいくスタイルだったので、余計にその違いに驚きました」
――アルゼンチンで4年、フランスで3年の計7年サッカーを海外で学ばれたということですね。そして帰国後は日本の広告代理店に就職されたんですよね。
「はい。28歳の終わりぐらいに就職して、遅い社会人デビューしました(笑)。選手として、壁を越えることに疲れてしまって。気持ちの面でも限界を感じて、現役引退を決断しました。それで当時スポーツビジネスにすごく興味があって、日本にいながら世界のサッカーの仕事ができる会社を探して入社してという流れです。ただ指導者にも興味があったので、まずその会社で2年働いてみて残るのか指導者を目指すのかを判断することにしました。結果的には、自分はサラリーマンじゃないな、エンターテインメントを作る側ではないなと感じました。自分は舞台に立つ側の仕事がやりたいので、じゃあサッカーの現場ではどういうポジションがあるのかと考えた時に、それは監督だな、と。海外生活を経て身に着けた言語やバイタリティと、アルゼンチンで試合分析のノートを大量に取っていたという経験があったので、監督を目指してみようと決心しました。それで働きながら毎年フェイエノールトやアーセナルのベンゲルのところに通い、勉強しました」
――そして、バルセロナのアカデミーに行かれたということですね。
「そうです。そのままアーセナルでやるにはレベルが足りないと言われたので、他のクラブをいくつかあたった中で引っかかったのがバルセロナでした。結果的に、いきなり世界的なビッグクラブで指導者としてのキャリアをスタートさせることになったわけです。バルサのエンブレムがついた服を着た時は、不思議な心地がしましたね。バルサのスクールコーチをしばらくやってから、指導者ライセンス取得のためのインターンでCEサン・ガブリエルの男子のユースチームを指導しました。そうしたら、そこのクラブの女子チームの選手たちが僕のトレーニングを見て推薦したそうで、オーナーが『来シーズンあの日本人に女子1部の監督をやらせる』と言ったんです」……



Profile
浅野 賀一
1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。