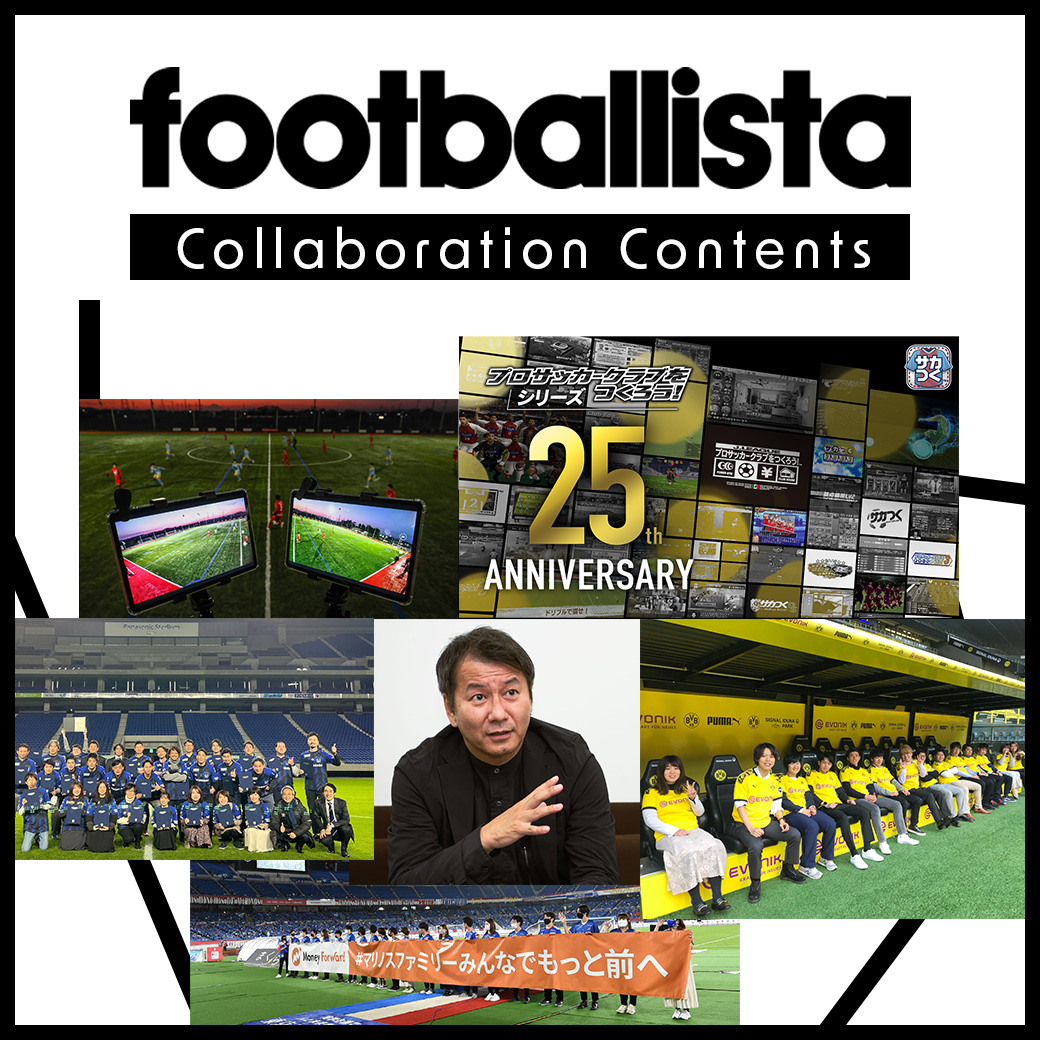せこの「アーセナル・レビュー」第15回
ミケル・アルテタ監督の下で一歩ずつ着実に再建を進めているアーセナル。その復活の軌跡をいち”グーナー”(アーセナルサポーターの愛称)でありながら、様々な試合を鋭い視点でわかりやすく振り返っているマッチレビュアーのせこ氏がたどる。第15回では、3-0先勝のレアル・マドリー戦で見せた新たな顔と景色を分析する。
サッカーファンにとっての幸せはいろいろあるけども、個人的にそれを一番感じるのはまだ見ぬ光景を応援しているクラブに見せてもらった時だと思う。自分がアーセナルを追い始めたのは2006年W杯の後。2005-06シーズン以来となるレアル・マドリーとの激突は紛れもなく「まだ見ぬ光景」である。まずはこのCL準々決勝に進めたことがアーセナルファンとしてとても幸せだ。
起用できない選手を多く抱えている両チームにとって、第1戦のスターターで選択を余儀なくされるポジションは少ない。アーセナルは本職不在のCFにメリーノ、ガブリエウがシーズン絶望となった左CBにキビオルを起用。どちらも直近の試合を見ていれば素直な判断と取ることができるだろう。
マドリーの悩みどころはSB。フェルラン・メンディが不在の左SBに、近年はCBのイメージが強いダビド・アラバが登用されたのはサプライズと言えるだろうか。ルーカス・バスケスではなくフェデリコ・バルベルデを右SBとして選択した時点で、カルロ・アンチェロッティ監督に残されたダブルボランチの選択肢はルカ・モドリッチとエドゥアルド・カマビンガしかなかった。
This atmosphere
pic.twitter.com/5BBDlFp2Mr
— Arsenal (@Arsenal) April 8, 2025
序盤からボールを持つ機会が多かったのは、本拠エミレーツスタジアムで戦うアーセナル。対して[4-4-2]で構えるマドリーは、ビニシウス・ジュニオールとキリアン・ムバッペの2トップの守備のスタート位置をトーマス周辺に設定。最終ラインまでプレスに来ない彼らを相手に、ホームチームはCBからゆったりとボールを持つ。
サカの1対1とカウンターへの対策を兼ねたティンバーの位置取り
[4-2-3-1]のベースポジションから左SBのルイス・スケリーがインサイドに入るという仕組み自体はいつもと変わらないアーセナル。あえて変化を挙げるとすれば、ボール保持局面における位置交換が最小限に抑えられていたことだろう。
ルイス・スケリーを例外として、多くの選手はどちらかといえばポジションを守る傾向が強かった。特に右サイドはこの傾向を遵守。ティンバーは無理にオーバーラップをせず、前でボールを持つサカを追い越す頻度はかなり少なかった。
ポジションを入れ替える頻度が少ない理由はいくつかあると考える。1つは単純にその必要に迫られていないから。そもそも、アーセナルがベースポジションをかなり入れ替えながらボールを動かすようになったのは、2023-24シーズンの開幕後。前季にボール保持型チームの割にはハイプレスでポゼッションを咎められるようになったのが始まりである。
つまり、移動を増やした理由は前からプレスに来る相手に対して、不定形でプレスを外す必要があったからである。しかし、この試合のマドリーは前から強引にプレッシングを仕掛けてこない。そのため過度なポジションチェンジで嚙み合わせをズラすという作業が絶対必要というわけではなかった。
その理由にはアーセナルの守る右サイドの要因もあるだろう。真っ先に挙げられるのはカウンターへの対策だ。ビニシウス、ムバッペの2人はどちらも同サイドに流れる傾向がある。不測のボールロスト時に対人守備能力が高いティンバーが後方にいるかどうかは、彼らを食い止められるかどうかの成否を分ける非常に重要なファクターだ。攻め上がりを抑制することでのリスクヘッジを行ったのだろう。
……



Profile
せこ
野球部だった高校時代の2006年、ドイツW杯をきっかけにサッカーにハマる。たまたま目についたアンリがきっかけでそのままアーセナルファンに。その後、川崎フロンターレサポーターの友人の誘いがきっかけで、2012年前後からJリーグも見るように。2018年より趣味でアーセナル、川崎フロンターレを中心にJリーグと欧州サッカーのマッチレビューを書く。サッカーと同じくらい乃木坂46を愛している。