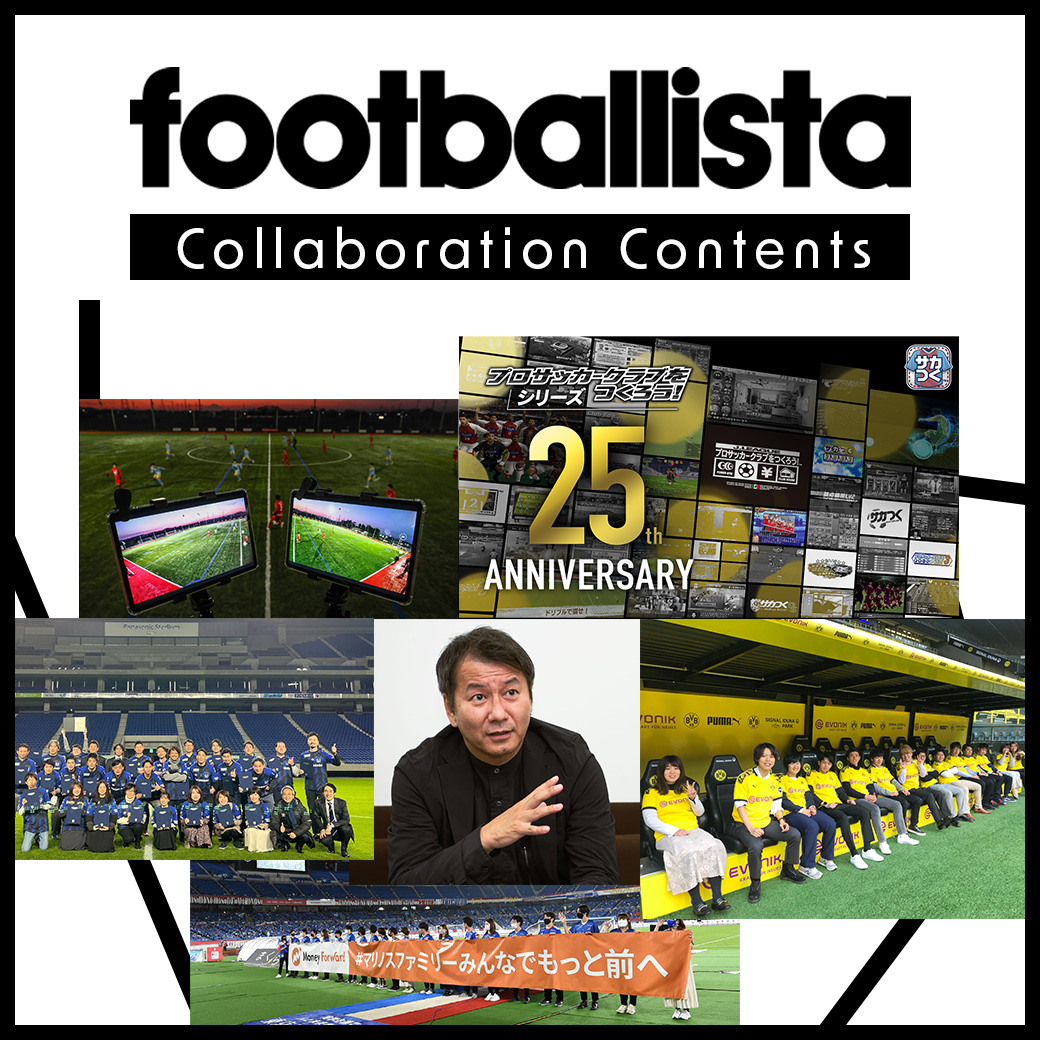レナート・バルディのJクラブ徹底解析#2
浦和レッズ
『モダンサッカーの教科書』シリーズの共著者としてfootballistaの読者にはおなじみのレナート・バルディ。ボローニャ、ミランなどセリエAクラブの分析担当を歴任し、FIGC(イタリアサッカー連盟)ではアナリスト講座の講師を任されている。現在はイタリア代表のマッチアナリストとしてスパレッティ監督を支える「分析のプロ」の目で、Jリーグ注目クラブの戦術フレームワークを徹底的に解析してもらおう。
第1&2回は、6月のクラブW杯でインテルと同グループになった浦和レッズ。後編では、「ネガティブトランジション」と「守備」を分析する。1対1のデュエル勝率の低さに表れている守備全般の淡白さの背景にあるものとは何なのか?
ゲーゲンプレッシングが機能しない背景
――後編ではネガティブトランジション(攻→守の切り替え)を含めたボール非保持局面を分析していきましょう。Jリーグでは、アグレッシブなゲーゲンプレッシングによる即時奪回を前面に打ち出したチームはあまり見ない印象があります。浦和はどうでしょう。
「基本的な姿勢としては、後退せず前に出てのゲーゲンプレッシングで即時奪回を狙おうとしているのですが、タイミングの的確さやプレッシャーの強度という点で不十分なことも多く、システマティックに機能させるには至っていません。結果的には、ボールをカバーしながら後退して、ブロックを整える形に落ち着くことが多い。ただ、危険なカウンターアタックを許す場面がほとんどなかったことも事実です。おそらくこれは、Jリーグのサッカーが全般的に、リスクを冒して速攻を仕掛けるよりもいったんポゼッションを確立する方を選ぶ傾向が強いことも関係しているでしょう。さっき(前編の中で)、Jリーグはリズムがスローで単調だという話がありましたが、それもこの傾向と結びついています。
話はそれますが、こうした傾向がもたらす『習慣』を破ろうとするならば、毎日のトレーニングの中で継続的に取り組むことが不可欠ですし、何よりもまず選手たち自身が、それが効果的であり自分たちにメリットをもたらすと納得する必要があります。例えば、奪ったボールを素早く縦に展開したところで、前線がその状況を活かそうという意識を持って準備していなければ、すぐにボールを失って守勢に回る結果に終わります。これは攻撃側のポジティブトランジションの話ですが、ネガティブトランジション時の振る舞いに関しても話は同じです。アグレッシブかつ高強度のゲーゲンプレッシングをシステマティックに行うためには、ボールを奪い切る決意と確信が不可欠です。浦和がそれを持っているかと言えば答えはNOですが、段階的な後退とブロック形成によって相手にカウンターアタックを許さず、安定した守備の局面へと移行する危険回避はしっかりできています」
――逆に言えば、敵陣でのボール奪取からショートカウンターでフィニッシュまで持っていく場面も稀ということになりますね。
「必然的にそうなりますね。浦和の安居、グスタフソンもそうですが、Jリーグのボランチは絶え間なく動き続けてはいるものの、爆発的な縦の加速を持っているタイプは少ないという印象があります。浦和の対戦相手の中にもほとんど見当たりませんでした。5試合見た中でも激しいトランジションは敵味方ともほとんどなく、ボールを失ったら即時奪回に強くはこだわらずミドルブロック、ローブロックに移行する、ボールを奪った時もいったんポゼッションを確立して攻撃に転じるという振る舞いがどのチームにも共通していた。そうした環境の中では、即時奪回が常に機能していなくとも、決定的なカウンターを喫する可能性は低いですし、その点で浦和のネガティブトランジションは問題なく機能していると言うこともできます。強度を上げて即時奪回の頻度を高めていくのは次のステップでしょう」
Recovery
#urawareds #浦和レッズ pic.twitter.com/Jb7HQCPkAj
— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) March 30, 2025
縦横にコンパクトな守備ブロック
――では非保持局面について見ていきましょう。……



Profile
片野 道郎
1962年仙台市生まれ。95年から北イタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。主な著書に『チャンピオンズリーグ・クロニクル』、『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』『モウリーニョの流儀』。共著に『モダンサッカーの教科書』などがある。