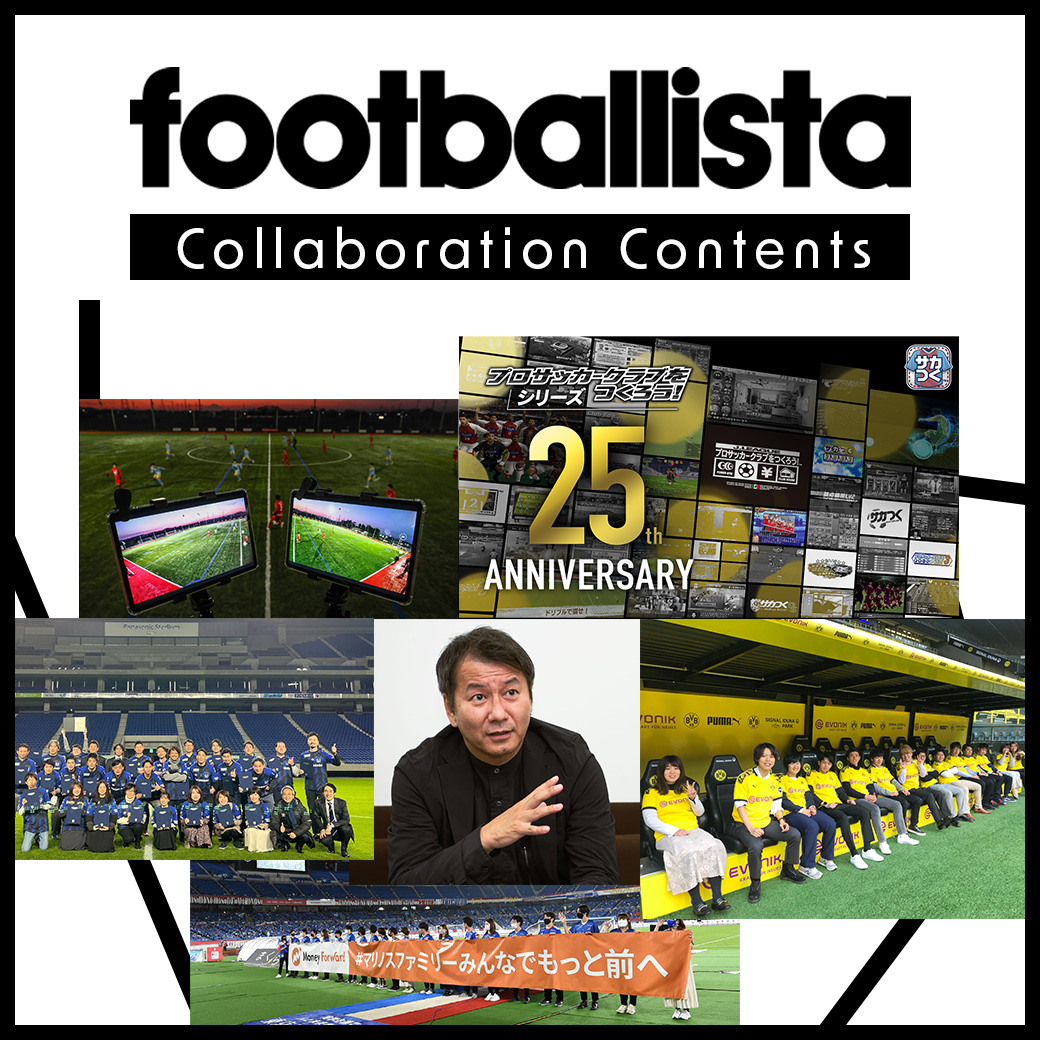「分析のプロ」が見た、浦和レッズの「クロス主体だけど中に人がいない」問題の解決策とは?

レナート・バルディのJクラブ徹底解析#1
浦和レッズ
『モダンサッカーの教科書』シリーズの共著者としてfootballistaの読者にはおなじみのレナート・バルディ。ボローニャ、ミランなどセリエAクラブの分析担当を歴任し、FIGC(イタリアサッカー連盟)ではアナリスト講座の講師を任されている。現在はイタリア代表のマッチアナリストとしてスパレッティ監督を支える「分析のプロ」の目で、Jリーグ注目クラブの戦術フレームワークを徹底的に解析してもらおう。
第1&2回は、6月のクラブW杯でインテルと同グループになった浦和レッズ。第二次マチェイ・スコルジャ政権のチームは苦しいスタートになっているが、フラットな目で現状分析し、課題解決の方法を探りたい。前編では、1試合平均1ゴールを割り込む深刻な得点力不足の原因と解決策について考察する。
レギュラー11人の個人分析
――Jリーグ注目チームの戦術を、ヨーロッパ基準のニュートラルな視点から分析していこうという新シリーズ、第1回は、6月にアメリカで行なわれるクラブW杯に出場する浦和レッズを取り上げましょう。ちょうどインテルと同じグループに入っているので、イタリア視点でも気になるチームです。昨シーズン途中に就任したポーランド人のマチェイ・スコルジャ監督の下で臨んだ今シーズンは、開幕6試合を終えた時点で1勝3分2敗(勝ち点6)、17位と出足で躓いている状況です。レナートには開幕からの4試合(詳細な分析は第4節・柏戦までの4試合で行い、第5節・岡山戦も見てはいる)を分析してもらいました。
「第一印象として言えるのは、私が抱いている日本のサッカー、日本のチームのイメージに近いチームだということです。基本技術が高く、戦術的秩序も取れていて、明確なゲームモデルに則ってプレーしていることがわかる。自陣ペナルティエリアの手前から敵陣ペナルティエリア手前までの60mは十分にクオリティが高い。ただ最初と最後の20mでは、個のクオリティという点でも戦術的な側面においても、いくつかの課題を抱えているように見えます。私が見た試合に限って言えば、ピッチ上の結果にもそれが反映していました」
――戦力的には、Jリーグでも最も充実したチームの1つです。『Transfermarkt』によれば、登録選手の市場価値総額ではリーグトップですからね。ロースター全体で2100万ユーロというのは、オランダリーグやベルギーリーグの中位くらいという水準です。
「何人か質の高い選手がいます。例えばグスタフソンは、私がトリノで2年間指導したことがあるので良く知っています。安定したテクニックと攻撃センスを備えているのでインサイドハーフとして起用していましたが、浦和で務めているように2セントラルMFの一角でも十分プレーできる能力を持っています。チームの戦術分析に入る前に、私が見た5試合をもとに、レギュラーと想定される選手について、簡単にコメントしておきましょう。
基本システムは[4-2-3-1]です。GKの西川はリーダーシップがあり、積極的なコーチングで守備を統率しています。ビルドアップにも可能な範囲で前向きに関与します。ただ守備範囲という点では、ハイボールの処理や飛び出しの判断に課題が見られます。
右SBの関根もパーソナリティがあり、攻守両局面ともに戦術的な判断力に優れています。爆発的なスピードや1対1の突破力は持っていませんが、ビルドアップへの貢献度は高いし、守備においても戦術的な選択ミスが少ない。CBはブラジル人のボザとノルウェー人のホイブラーテン。ともにビルドアップ能力はそれなりに高いですが、守備に関してはスピードが足りないこともあって、背後の広いスペースを守る際には困難に陥る場面も見られました。左SB荻原はライン際を縦に上下動するオーソドックスなタイプで、忠実に攻守のタスクをこなしていました」
――中盤センターは安居とグスタフソンのペアになりました。開幕からの2試合はグスタフソンのところに渡辺が入っていましたが、第2節京都戦の途中でケガをしたため、その後はグスタフソンが入っています。
「安居はダイナミックなMFで、ボールのラインよりも後方に留まって的確なポジショニングでスペースを管理します。グスタフソンはすでに見たように、3MFのインサイドハーフの方が向いているタイプだと思いますが、2セントラルの一角でも安居との補完性は悪くはありません。
ただこのペアは中盤のフィルター機能という点ではやや物足りなさを残しています。セカンドボールの競り合いや1対1のデュエルで劣勢に陥り、相手が2ライン間で前を向く状況を招く場面が何度かありました。しかしこれには、[4-2-3-1]というシステムの中で左右のウイングの守備参加が不十分なため、2CMFがカバーしきれないスペースが中盤に生まれた結果、という側面もあります。特に左ウイングのマテウス・サヴィオは、攻撃のクオリティという点ではチーム随一ですが、守備の局面では貢献が十分ではなく、その分リスクももたらしています」
――前線のアタッカー陣は、日本人とブラジル人が2人ずつの構成です。
「2列目の左に入るサヴィオは、ダイナミズムと1対1の突破力に優れる、チームで最も危険なプレーヤーです。ただ攻撃性能が高い反面、今見たように守備への貢献度には物足りなさを残しています。トップ下には本来セントラルMFの松本。スペースへの動き出しが良く、ゴール前への侵入も効果的ですが、アシストとフィニッシュに関してはクオリティがやや物足りないかもしれません。右サイドには金子と前田(のちに広島に移籍決定)が起用されていますが、現在のところ金子が優先されているようです。彼はサヴィオよりも守備意識が高く、戦術的秩序もありますが、ゲーゲンプレッシングや1対1のデュエルではやや積極性に欠ける部分があります。CFはチアゴ・サンタナ。昨シーズンのチーム得点王で、強靭なフィジカルを活かして前線の基準点となるだけでなく、ゴールセンスも備えています。ただややプレーが粗いというか、技術的な精度が足りない部分もあります」
ブラッシュアップされた「フレームワーク」
――では、レナートがアナリストとしての仕事で使っているフレームワークに従って、チームの分析を進めて行くことにしましょう。初回なので、フレームワークをいったん整理しておきましょうか。
「はい。3年前に『モダンサッカーの教科書IV』で取り上げた時と比べて、フェーズの区切り方や用語にいくつかの修正が加わっています。これは、近年の戦術的傾向の変化に対応すると同時に、イタリア代表でスパレッティ監督と仕事をする中で得た知見も反映した結果です。現在私が講師をしているFIGC(イタリアサッカー連盟)のマッチアナリスト講座でも、このフレームワークを使っています。
<攻撃>
・ゴールキック
・プレッシャー下でのビルドアップ(ファーストサード)
・非プレッシャー下でのビルドアップ(ミドルサード)
・ファイナルサード攻略=包囲(ファイナルサード)
<ネガティブトランジション>
<守備>
・ゴールキックへのプレッシング
・ハイプレス(ファイナルサード)
・ミドルブロック(ミドルサード)
・ローブロック(ファーストサード)
<ポジティブトランジション>
まずボール保持の局面については、ゴールキックとオープンプレーに大別した上で、後者はプレッシャー下でのビルドアップ、非プレッシャー下でのビルドアップ、ファイナルサード攻略(包囲=アッチェルキアメント)に分けています。ゴールキックはセットプレー的な側面が強いので、オープンプレーでのビルドアップとは区別する必要があります。
オープンプレーについては、同じビルドアップでも相手がハイプレスをかけてきた場合(ファーストサードが舞台)と、中盤でブロックを形成して待ち受ける場合(ミドルサードが舞台)では状況が根本的に異なるので、区別して捉える必要があります。いずれも、敵中盤ラインを越えて2ライン間にボールを届けるまでのプロセスを扱います。
ファイナルサード攻略は、以前はポジショナルアタックという言葉を使っていましたが、近年はポジショナルプレー、リレーショナルプレーといった言葉が広まって、それと混同されやすくなったので、スパレッティ監督が好んで使っている『包囲(アッチェルキアメント)』という言葉を導入しました。これは、相手をゴール前に押し込んだ状態で、どのように決定機を作り出しゴールを奪おうとするかに焦点を当てるものです。私は、ネガティブトランジションもこのフェーズと関連づけて考えています。ボールロスト時にどのように振る舞うかは、その後の攻撃の形と密接に関わっているからです。
この『守備が攻撃を規定する』という観点に立つと、ボール非保持局面の捉え方も変わってきます。こちらも、ゴールキックに対するプレッシングは、通常のプレッシングとは区別して扱います。オープンプレーでの守備は、相手が保持するボールの位置に応じて、ハイプレス、ミドルブロック、ローブロックに大別しています。以前は非保持の局面を大きくプレッシングと組織的守備に分けていましたが、オープンプレーの守備は高さによって振る舞いが変わると捉えた方が理解しやすいので、そのように区別しています」

柔軟性ではなく、原則を重視したビルドアップ
――では、まず攻撃から見ていきましょうか。……



Profile
片野 道郎
1962年仙台市生まれ。95年から北イタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。主な著書に『チャンピオンズリーグ・クロニクル』、『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』『モウリーニョの流儀』。共著に『モダンサッカーの教科書』などがある。