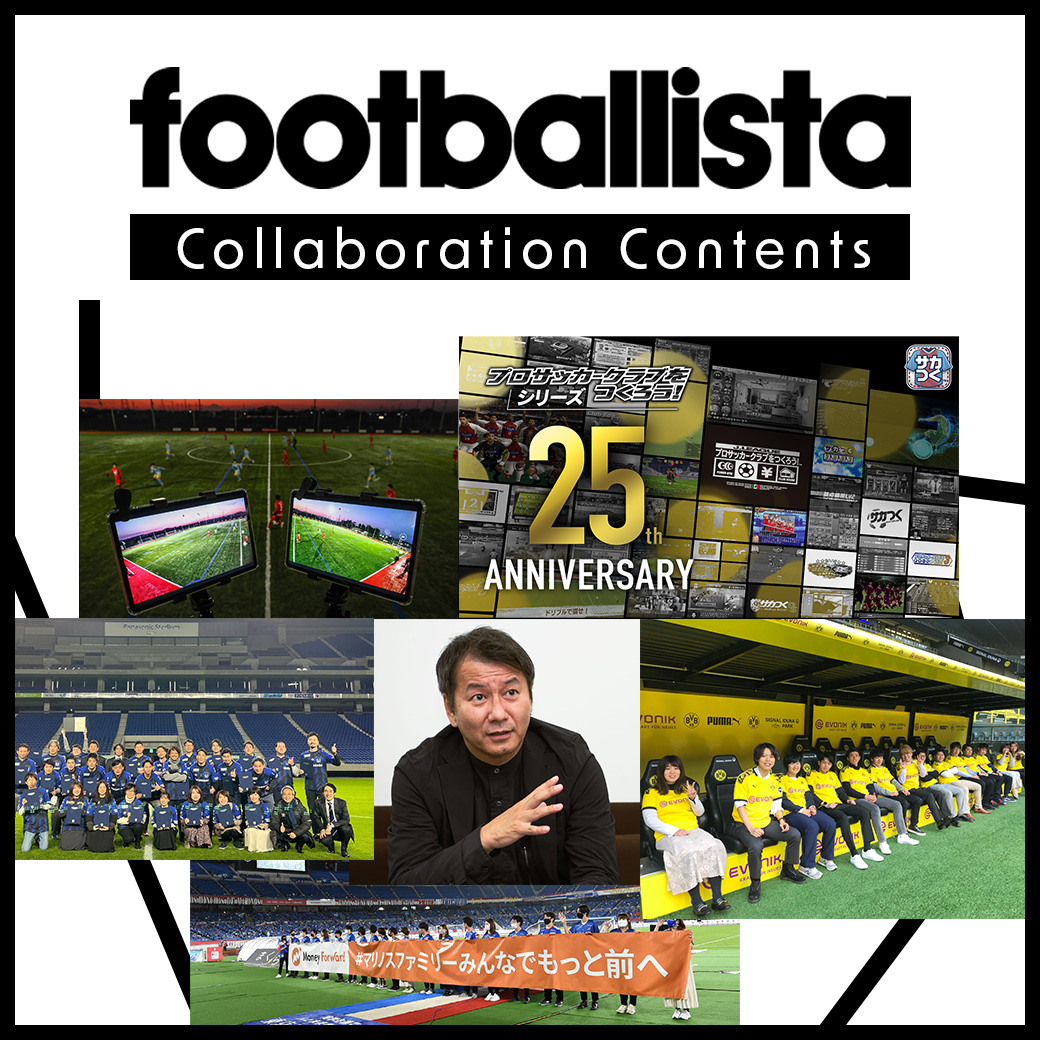TACTICAL FRONTIER~進化型サッカー評論~#14
『ポジショナルプレーのすべて』の著者で、SNSでの独自ネットワークや英語文献を読み解くスキルでアカデミック化した欧州フットボールの進化を伝えてきた結城康平氏の雑誌連載が、WEBの月刊連載としてリニューアル。国籍・プロアマ問わず最先端の理論が共有されるボーダーレス化の先に待つ“戦術革命”にフォーカスし、複雑化した現代フットボールの新しい楽しみ方を提案する。
第14回は、プレミアリーグで価値が拡大している「セカンドボール」を探求してみたい。ボーンマスやニューカッスル、ブレントフォードはなぜ、強いのか? 空中戦と地上戦、戦術への落とし込みなど多方面から考察してみよう。
モダンフットボールで「セカンドボール」が注目される必然
イングランド・プレミアリーグは、ある意味で魔境だった。欧州の強豪クラブで監督を経験しているカルロ・アンチェロッティは、このリーグの特徴を次のように説明した。
「プレス戦術を突破する方法は、シンプルだ。ただし、その実行は簡単ではない。パスで突破する技術があれば、それが方法になる。それが難しければ、ロングボールを蹴ればいい。そうなれば、『セカンドボール争い』になる。イングランドのクラブはこの方法を得意としており、能力とメンタルの両面でセカンドボールを奪うことに長けている」
そして今年、グアルディオラは次のようにコメントしている。
「今、モダンなフットボールとは、ボーンマスやニューカッスル、ブライトンやリバプールがプレーしている手法だ」
グアルディオラを筆頭にした欧州屈指の指導者がプレミアリーグに伝えたビルドアップの方法論によって、多くのクラブは全局面にハイレベルに適応するようになった。ボール非保持の局面だけに集中するクラブは減り、大柄な選手を揃えたクラブであっても必要があればGKから丁寧にボールを前進させる。DFラインを下げて徹底して守るのではなく、強豪が相手でも時間帯に応じてハイプレスを仕掛けていくチームも珍しくない。
そういったハイプレスやビルドアップが多くのチームに戦術として実装された結果として、多くのクラブが攻撃時にはハイラインを保つことが一般的となり、コンパクトなエリアで敵味方がプレーすることが増えている。FAカップ決勝、リバプール対ニューカッスルはその典型例だった。互いに狭いエリアで中盤のプレーヤーが身体をぶつけ合い、そこからゴールに迫るショートカウンターを容赦なく撃ち合うハイペースのゲームは、今のプレミアリーグのクラブを象徴するものだった。
前述したように、肉弾戦を好むプレミアリーグでは伝統的に強靭に鍛え上げた肉体を誇るファイターがロングボールに競り合うことが多く、その結果としてイーブンボールが増えていた。シャビ・アロンソやミケル・アルテタのようにスペインの地で磨かれたテクニシャンは、その繊細なプレーだけでは生き残れず、思考力や判断力を鍛えることでセカンドボールを予測し、それを拾うことでチームを助けるというスタイルを確立した。
しかし、現代フットボールでは中盤が究極までに過密化していることから、トラップが少し乱れればそれもセカンドボールになる。より狭いスペースでボールをコントロールしなければならず、相手とのボディコンタクトも増えていく。その結果として、ボールを保持しながら守備でも働けるタフなMFが多くのチームで主力として活躍するようになっている。アンドレア・ピルロが絶滅危惧種となり、ニューカッスルの中盤に並んだサンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイス、ジョエリントンのように、デュエルを厭わない選手が重宝されるようになった。
最もセカンドボール回収率が高いのは、ペップ・シティ!
統計上、プレミアリーグで「セカンドボールを最も高い確率で拾うチーム」はどこなのだろうか?……



Profile
結城 康平
1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に記事を寄稿しつつ、サッカー観戦を面白くするためのアイディアを練りながら日々を過ごしている。好きなバンドは、エジンバラ出身のBlue Rose Code。