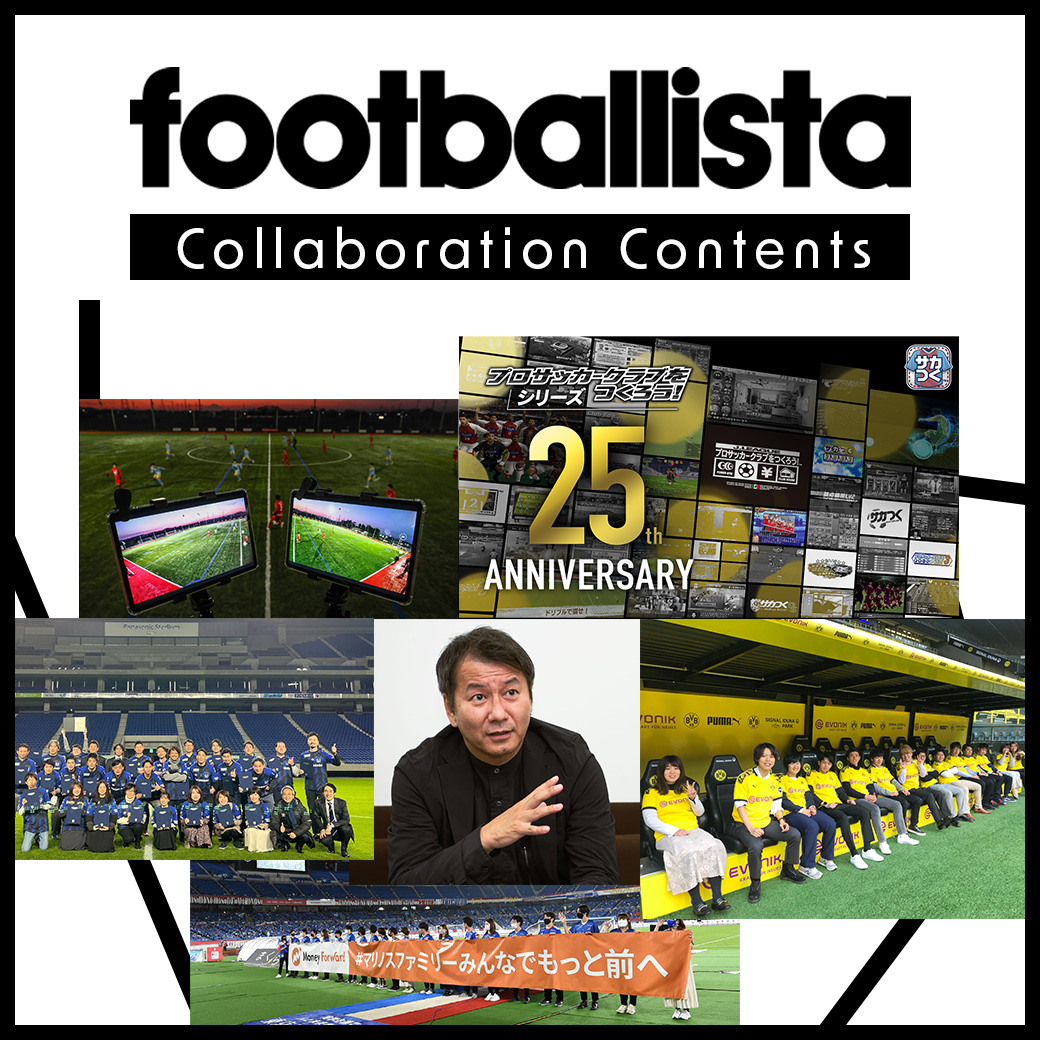CALCIOおもてうら#39
イタリア在住30年、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えるジャーナリスト・片野道郎が、ホットなニュースを題材に複雑怪奇なカルチョの背景を読み解く。
今回は、きわめて高度化したデータスカウティング時代で差別化要因になるものについて考えてみたい。どのチームもプロバイダーから最先端の分析結果をもらえるようになり、データやAIの活用はもはや当たり前の前提になっている。その先に待つものとは?
近年、プロサッカークラブの強化部門において、データスカウティングの重要性が高まっていることは、いろいろなところで指摘されている通り。例えばスポーツベッティング分野のデータアナリストをオーナーに持つブライトンやブレントフォードの成功も、そうした文脈で取り上げられることが多い。しかし、ここ数年で急速に進んだデータサービスの高度化によって、少なくとも5大リーグレベルのクラブの間では、「スカウティングにおけるデータの活用」というレベルでは格差がなくなってきているようだ。
高度化したデータスカウティングの「コモディティ化」
その最大の理由は、どのクラブもデータサービス会社からかなり高度なスカウティングデータが入手できるようになったことにある。例えば、この分野の最大手『STATS Perform』で南欧地区のビジネスマネジャーを務めるトンマーゾ・レフィーニは、昨年行ったインタビューでこんな説明をしてくれた。
「強化部門へのサービスにおいては、チームの陣容全体を評価した時に、特定のポジションや戦術的機能を満たすこういうタイプの選手が足りない、それに当てはまる選手をクラブの戦術やスタイル、強化戦略や予算などを考慮に入れた上で選ぶとすれば、候補選手のリストはこうでランキングはこうなる、というところまで提案しています」
数年前までは、自前のデータ部門を持ち独自のモデルやパラメータを使ってデータ分析を行うことで、従来のスカウティング手法ではカバーできなかった中堅・弱小国やその下部リーグまで含めた膨大な数の選手をカバーしフィルタリング/スクリーニングすることによって、「原石の発掘」や「よりコスパの高い選手の特定」、「戦術的な欠落の的確な補完」というアドバンテージを得ることが可能だった。しかし今や、このレベルのデータスカウティングは、データサービス会社のデフォルトに近いレベルまで敷居が下がっている。
言ってみれば「スカウティングにおけるデータの活用」はもちろんのこと、データ分析モデルの精緻化やクラブのニーズに応じたカスタマイズという細部すらも、今や「コモディティ化」が進んでおり、それ自体で競争優位性を得ることは難しいということ。逆に言えば、このレベルでデータを十分に活用できていないクラブは、それだけで競争上劣位に置かれているということでもある。
@StatsPerform @OptaSTATS #Opta production center @ Aveiro
pic.twitter.com/83lYKJMZuC
— Tommaso Refini (@tommasorefini) January 17, 2023
細分化したニーズに対応。『Soccerment』による13のクラスタ分類
スカウティングに関するデータサービスの質がどれだけ高まったかを示す興味深い一例が、本誌1月のポジショナルプレー特集に掲載された「非ポジショナルプレー」の可能性についての長いインタビューの主役であるアントニオ・ガリアルディ(この2月よりパルマ助監督)が、イタリア代表の主席マッチアナリストを務めていた当時にイタリアの新興データサービス会社『Soccerment』 と共同開発した、プレーヤーの「機能」別分類クラスタ。……



Profile
片野 道郎
1962年仙台市生まれ。95年から北イタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。主な著書に『チャンピオンズリーグ・クロニクル』、『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』『モウリーニョの流儀』。共著に『モダンサッカーの教科書』などがある。