VARが開けたパンドラの箱 フットボールが死んだ日

【VAR特集#6】2XXX年 未来への旅
2019年9月24日、2020年のJ1リーグ全306試合でのVAR導入が承認された。世界的な流れを見ても、もう後戻りはできそうもない。VAR、ひいてはテクノロジーを導入したフットボールの行く末には何が待つのか。過去から現在、そして未来をのぞく時間旅行への誘い――。
1863 フリーメイソンズ・タバーン
10月26日、グレート・クイーン街の居酒屋フリーメイソンズ・タバーンに次々と馬車が到着していた。南部の学校とクラブの代表者たちの会合である。ほぼ全員がパブリック・スクール出身の「ジェントルマン」だった。
ハンチングを被った髭面の男たちは、階上の部屋でビールを飲みながら議題について話し合った。The FAを結成し、年会費を1ギニーにすることはすぐに決まった。しかしそこからが難航した。ハロー校出身者で構成されたフォレスト・クラブの代表、ジェームズ・フレデリック・オルコックが「ハッキング禁止をルールに盛り込むべきだ」と主張したからだ。ブラック・ヒースクラブのフランシス・キャンベルはこれに猛然と異議を唱えている。キャンベルの主張は「男らしさがなくなる」であった。投票の結果、13対4でオルコックの提案が可決され、ブラック・ヒースクラブはこれを不服として脱会、8年後にラグビー協会を設立するに至る――。
フットボールをラグビーと分裂させた「ハッキング」とは、相手のくるぶしから膝の間を蹴って撃退する行為のこと。ボールを手で扱うハンドリングより、ハッキングの方がはるかに重大事だったわけだ。
社会の指導階級であるジェントルマンたちによるフットボールとは、恐ろしく荒っぽい野蛮なスポーツだった。理性を失うぎりぎりまで闘争に没頭するが、そのぎりぎりの際でフェアプレーを実行する。それが社会のリーダーたる彼らの誇りだった。とはいえ、その高慢な面の皮を1枚剝けば残忍性も帯びていたジェントルマンたちのゲームを、彼らだけで行うわけにはいかなかった。第三者を立て、レフェリーとした。頼んだ以上文句は言わない。これもまた、ジェントルマンのプライドである。

1966 ウェンブリースタジアム
レフェリーの権威は絶対。これがフットボールのルールだ。
レフェリーが偉いわけではない。よく間違いもする。選手たちがレフェリーに権威を持たせているだけだ。いわば架空の権威であり、タテマエである。ホンネを言えば「クソ審判」と誰もが思っている。思っていても、それを口に出したらフィールドにはいられない。レフェリーの権威は守られなければならない。レフェリーが守られなければフットボールは存続できないので、レフェリーの権威はフットボールを守るための“犯してはならない聖域”としたわけだ。
ジェントルマンが作ったフットボールの世界は最初から倒錯的だった。レフェリーがどんな間違いを犯そうとも、それを認めなければならないルールもその1つだろう。
1966年7月30日、歴史的なジャッジが下されている。場所はロンドン、ウェンブリースタジアム。舞台はFIFAワールドカップ決勝。イングランドと西ドイツの試合は2-2で延長に突入していた。
101分、イングランドのジェフ・ハーストの放ったシュートはバーに当たり、真下に落下した。ボールはフィールド側に戻って来たが、ゴットフリート・ディーンスト主審はゴールと判定した。副審のトフィク・バフラモフに確認しての判定だった。「白煙が飛ぶのが見えた」と主張する西ドイツの選手たちは抗議したが、レフェリーの判定が覆るはずはない。120分にもう1点を加えたイングランドが4-2で西ドイツを下して初優勝を成し遂げた。
ノーゴールを証明する写真には懸賞金もついたが、明確な証拠は出てこなかった。スイス人の主審とアゼルバイジャン出身の副審がともにユダヤ系だったことから、判定の疑惑はいっそう深まったが真実は闇の中だ。
それ以前もその後も、フットボールに疑惑の判定はつきものだった。しかし、依然としてレフェリーの権威は守られていた。言い換えると、レフェリーのミスは許容されていた。それは表面上のことであり、ホンネが別だったのは言うまでもない。ドイツ人は永久にハーストの得点を認めない。だが、それでもタテマエは尊重されていた。世界一か否かを左右する判定でさえ許容されたのだから、人々はどんなに不満でも最後は受け入れる他なかった。このころまでは、少なくともフットボールは理不尽であるとみなが理解していた。

2012 ホークアイ
2010年南アフリカワールドカップ、ドイツ対イングランド。フランク・ランパードのシュートはバーに当たって落下、フィールド内に跳ね返ってきた。そしてノーゴールと判定された。試合はドイツが4-1で勝って準々決勝へ進んだのだが、38分のランパードのシュートが得点と認められていれば2-2になっていた。ドイツ人は1966年の判定を思い出し、多少は溜飲を下げたかもしれない。
イングランドのファビオ・カペッロ監督は「ここにテクノロジーがないのは信じがたい」と憤慨した。
「5人の審判がいて、誰もゴールか否かを判別できなかった」(ファビオ・カペッロ)

テニスで採用されたビデオカメラによるホークアイやボールにチップを埋め込む磁場式の導入が検討されていたが、FIFAは判定を人間の眼で行うことに固執。ゴール脇に審判を増員してワールドカップに臨んでいた。
5人の審判は誰もランパードのシュートがゴールラインを越えていたかどうか確信を持てなかったが、世界中の人々はゴールだと確信している。テレビ画面は、繰り返しボールがゴールラインを完全に越えているシーンを映し出していたからだ。
ゼップ・ブラッターFIFA会長は「ファンは議論したいもの。これも我われのスポーツの人間性の一部だよ」と話したが、人々がこれに共感したとは思えない。同じような判定ミスは他にも起こっていた。判定は信用できない。その証拠も次々と挙がっている。1966年のように、うやむやにできなくなっていた。
2012年FIFAクラブワールドカップ、サンフレッチェ広島対オークランド・シティ。ついにFIFAはゴール・ライン・テクノロジーを導入する。

ホンネがタテマエを越えたターニングポイントだった。判定が信用に足らないことは、フットボールが開始された時から実は誰もが知っていた。しかし、タテマエは尊重されてきた。タテマエを綺麗な言葉で言うなら理想である。人間は間違える、間違えは許容される、それがフットボールの理念であり美しいタテマエだった。
だが、21世紀になって判定は間違ってはいけないことになった。もちろん、ロンドンの居酒屋でジェントルマンたちがルールについて議論した時、機械が判定の助けになると想像していた者はいなかっただろう。機械判定はただ想定外だったに過ぎない。しかし、その時彼らが理想を掲げたのは確かだ。タテマエに過ぎないとわかっていても、ホンネを剥き出しにするほど品格に欠けてはいなかった。
なぜ、ホンネはタテマエを越えていったのか。理不尽に堪え忍んできた人々が一斉蜂起したからではない。レフェリーの自宅を襲撃したところで、タテマエは強靱でルールも変わらなかった。なぜ、急に判定は正しくなければならなくなったのか。答えは察しの通り、フットボールが巨大なビジネスに変貌していたからだ。この理不尽極まりないスポーツに対して、ばかばかしいほどの大金が投じられるようになっていた。フェアネスをモツトーとするビジネスマンは判定ミスなど許容できるものではなく、彼らのルールでは一刻も早く機械を導入すべきなのだ。間違った判定1つで投入した資金が水の泡になるのは耐えられない。フットボールにそんな大金を突っ込んでいる方がどうかしているのだが、彼らは理不尽さに耐えてきた人々の忍耐と諦観を持たなかった。
ホンネが初めて勝利した。資本主義を味方にしたホンネがタテマエを打ち倒したのだ。
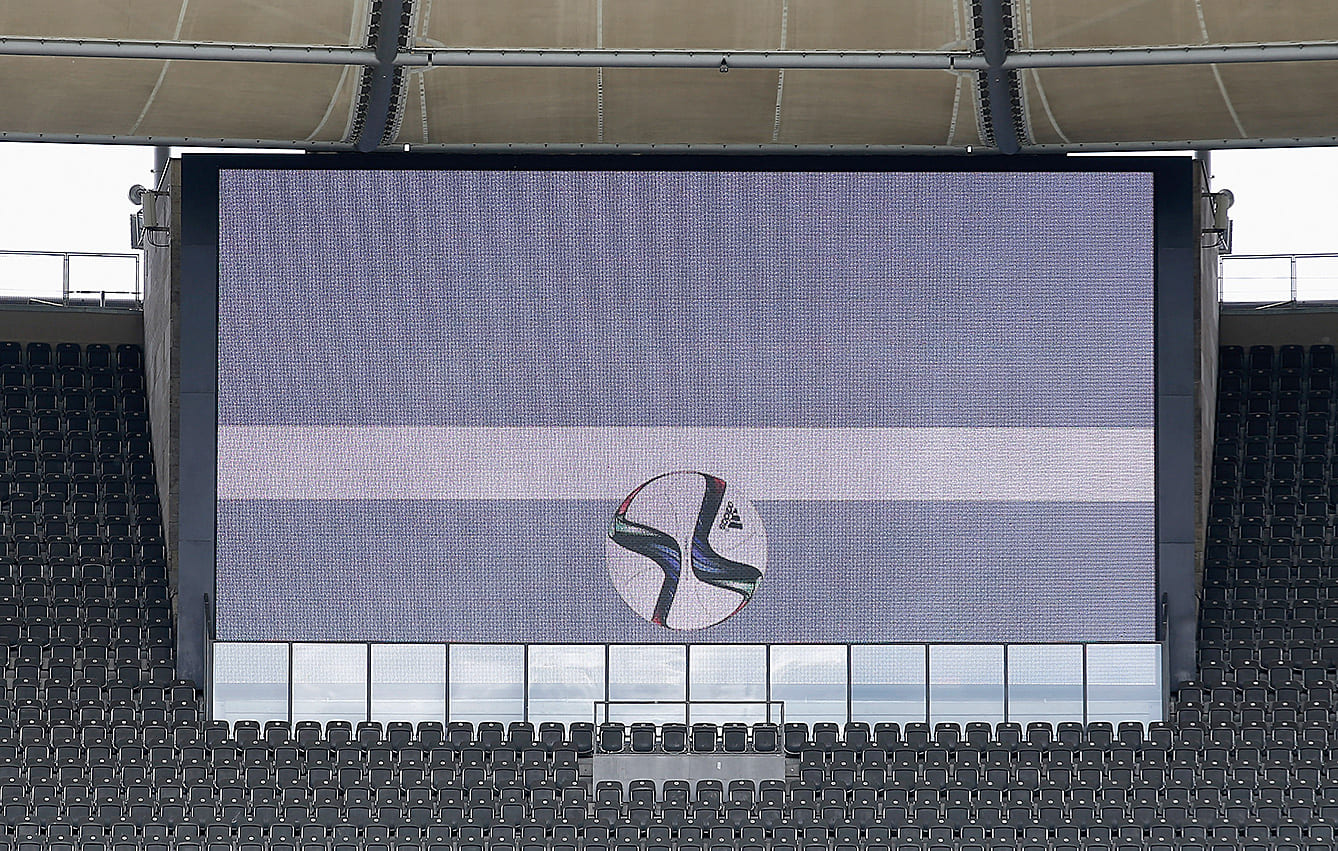
2018 VAR
2018年ロシアワールドカップの主役は優勝したフランスではなく、VARだった。
ホンネがいったん勝利した以上、タテマエは後退の一途をたどった。ゴールラインをボールが越えているかどうかだけでなく、重要なシーンはすべてビデオカメラの監視下に置かれ、誰も気づかなかったファウルが暴き出され、2cmの差でオフサイドになることも笑い話ではなくなった。
首の皮1枚残されたタテマエは、機械は材料を提供するが最終判断は主審が行うということ。もう答えは出ているのだが、フットボールは人間がやるという一線だけは辛うじて譲らなかった。機械はまだ判定をしていない。映像でも明確でないことは、主審が見ても明確なはずはないのだが、機械の声を聞くわけではない。
当面の課題は判定に時間がかかり過ぎることだった。ボールがゴールインしてから10秒程度、長ければ3分間も、それが本当にゴールなのか全員が待たされる。ゴール直後の歓喜というフットボール最大のカタルシスが台なしになっている。これは何とかしなければいけなかった。

20XX そしてレフェリーはいなくなった
VARが導入されてからの流れは早かった。すでにパンドラの箱は空いている。
AIの発達とともに、判定はAIが一手に引き受けることになった。ビッグデータの解析において人間など問題にならない。ゴール後の確認作業は1秒に短縮された。
すぐに副審が姿を消した。そもそも際どいオフサイド判定において、副審は自分の眼を信用していない。見えた通りに判定したら誤審になることを、彼らはすでに経験的に知っていた。どのケースがオフサイドに見えてオンサイドであるか、その感覚を持つことは優れた副審にとって必須の技術とさえ言える。彼らは肉眼で見えたことに背いた判定をしていたわけだ。つまり、オフサイド判定はそもそも人間には無理だったということになるのかもしれない。
やがて主審もいなくなった。判定はAIがしていて、主審はそれを選手たちに伝達する役割を果たしているに過ぎないのだから、いなくて困るのは乱闘にでもなった時ぐらいなのだ。乱闘で役に立つのは主審より警備員であることもすぐに判明した。フィールド上空には小型のドローンが飛び交い、AIの指令を受けてファウルのあった地点をライトで照らす。PKの時はペナルティエリア内に観客からも見える大きな「PK」の文字が映し出される。退場者には赤い照明がドローンから注がれ、その選手がロッカールームに消えるまで、赤く照らし続けた。

20XX サイボーグの時代
判定は人間の領域ではなくなった。レフェリーが人間でなくていいなら、選手も人間でなくてもいいのではないか? これが最終的な問いである。
ある年、バルセロナのスーパースターが重傷を負った。一昔前なら再起不能の大ケガだった。だが、人類の英知がカタルーニャの英雄を蘇らせることに成功する。人工の骨、人工の筋肉、人工の神経などによって再生された彼の左足は、むしろ全盛期のパフォーマンスを上回っていた。偉大なスターの復活を誰もが祝福したが、論争はそこから始まる。
レアル・マドリーは彼らのスターを何ら負傷の痕跡がないにもかかわらず、増強手術を行ったのだ。秘密裏に行った手術がスクープされ、世界中から非難の声が沸き起こったが、レアルの首脳部は開き直って反撃に出た。
「ケガであろうとなかろうと(負傷はあったと言い張っていたが)、結果が増強であることに変わりはない。我われが非難されるなら、バルセロナの彼も引退させるべきだ」
医術によって増強された選手を認めるべきか否か。この論争の答えは自明だとFIFAは当初タカを括っていた。だが、彼らの思惑に反し、世論はほぼ真っ二つだったのだ。
かつてハンディキャップ・パーソンと呼ばれていた人々は、スポーツの世界で表舞台に躍り出ている。100mスプリントの世界記録保持者はパラリンピックのアスリートだった。その他の競技でも世界記録はハンディキャップがあるはずの選手によって次々に更新されていった。医学の進歩はハンディキャップをアドバンテージに変えていた。オリンピックとパラリンピックの統合が検討され、それは時間の問題だった。
個人スポーツのヒーローは、すでに増強されたアスリートになっていた。どの競技もビジネスとなっていたので、たとえテクノロジーの助けを借りたにせよ重要なのは世界一という事実だ。世界で一番速い、強い、巧い、誰も到達しなかった未知の領域に立った者にこそ大金を投資する価値がある。
FIFAは増強手術を負傷の場合に限るとした。しかも、元の状態に戻すまでで、それ以上の増強を禁じた。しかし、せっかく使える最新の医学を活用せず、つまり患者を古い医療水準で中途半端にしか治療できないなど、世間の理解を得られるわけがない。FIFAは追い込まれ、ついに会長の信じがたい失言によってこの論争にケリがついている。
「フットボールは人間がやるものだ!」
会長の魂の叫びだった。だが、致命的でもあった。人工の足をつけた選手は人間ではないと断じたに等しかったからだ。そういうつもりはなくても、そう解釈されて弁明できる発言ではなかった。FIFAは全面的に敗北し、フットボールは増強されたサイボーグがプレーするスポーツへと舵を切る。
2XXX年、もはや人間も、サイボーグ化した人間も、ロボットですらフットボールをプレーしていない。プレーするのは本物とまったく見分けがつかない、プログラミングされたホロスコープの選手たちだ。投影はどこでも可能なので、スタジアムではなく映画館でも広場でもいっせいに同じ試合を観戦できるようになった。ただ、フットボールはギャンブルの対象として存在しているだけだ。依然として巨大なビジネスではあるが、人間のする営みではなくなった――。
人がやる以上は間違うし、それを認めなければならない。そのタテマエが崩れたのはゴール・ライン・テクノロジーの導入だったが、流れを決めたのはVARだったかもしれない。もしかしたら、「男らしくない」という反対を押し切ってハッキングを禁止したロンドンの居酒屋から、もうそうなっていたのかもしれないが。
Photos: Allsport Hulton/Archive, Hulton/Archive/Getty Images, Getty Images, Bongarts/Getty Images



Profile
西部 謙司
1962年9月27日、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒業後、会社員を経て、学研『ストライカー』の編集部勤務。95~98年にフランスのパリに住み、欧州サッカーを取材。02年にフリーランスとなる。『戦術リストランテV サッカーの解釈を変える最先端の戦術用語』(小社刊)が発売中。









