ベルギーとの差は高さではない。「抗プランB」がなかった日本

林舞輝の日本代表テクニカルレポート第4回:日本対ベルギー
欧州サッカーの指導者養成機関の最高峰の一つであるポルト大学大学院に在籍しつつ、ポルトガル1部のボアビスタU-22でコーチを務める新進気鋭の23歳、林舞輝が日本代表のゲームを戦術的な視点から斬る。第4回のテーマは、歴史的名勝負となったベルギー戦で「2点のリードを守り切れなかった日本サッカー界全体の課題」を考察する。
一体、何が足りなかったのか?
ベルギーに2-3の惜敗を喫したあの日から、きっとサッカーを愛する読者の皆さんも今の私と同じように、気が付けばふとぼんやりとそんなことを考えていたのではないか。
私たちには、何が足りなかったのか?
どうすれば勝てたのか?
これから何をすれば、何年後に、勝てるのか?
私が見た限りでは何度ビデオを見直しても、ピッチ上に足りないものは何もなかった。何一つとして、本当に何も、なかった。選手たちは一人残らず全員がベストを、いや、ベスト以上を出し切った。だからこそ、国全体がこれだけ盛り上がり、感動し、そして悔しさをにじませているのだろう。
何も足りないものはなかった――だが、それはつまり矛盾するようだが、何もかもが足りなかったということだ。日本のベスト8への道のりは、果てしなく、果てしなく、果てしなく、長い。
変則ビルドアップ、そしてルカクへの「プランB」
序盤から、日本は優勝候補の一角とも呼び名高いベルギー相手に、真っ向勝負を挑む。ベルギーの[3-4-3]に対し、日本は通常通り攻撃時は[4-2-3-1]、守備は[4-4-2]の形でコンパクトな陣形を維持し、ミドルプレスからハイプレスを仕掛ける。一見バランスの悪そうなベルギーだが、それぞれの長所・短所を補い合う安定性を求めた組み合わせになっている。ベルギーのビルドアップは特徴的で、両脇のCBが開いて全体的に左に寄る「右SBなしの4バック」に近いような陣形を作り、そこから右CBと高い位置の右ウイングバックの間にアクセル・ウィツェルもしくはケビン・デ・ブルイネが下りてくる。3人のCB全員が高いビルドアップ能力を持っている上に、両ウイングバックが相手SBにとってプレスに行きづらい嫌な高さにポジションを取る厄介な形だ。
日本はこのベルギーのビルドアップに対し、序盤からアグレッシブにプレスをかける。大迫勇也&香川真司の2枚はベルギーの3CBにプレスをかけに行くより、まずは後ろのデ・ブルイネとウィツェルへのリンクを遮断し、ベルギーの組織を前と後ろで分断させることを優先。そして、ベルギーのサイドのCBトビー・アルデルワイレルトとヤン・フェルトンゲンへの中距離の横パスを日本のハイプレスのスイッチにし、両サイドの乾貴士と原口元気が左右のCBにハイプレスを敢行、後ろの長友佑都と酒井宏樹が1つ前に出てベルギーのウイングバックへの縦パスのインターセプトを狙っていた。乾がアタックした時に長友が前にスライドせずベルギーの右ウイングバックのトーマス・ムニエがフリーになってしまった場面があったものの、ミドルプレスからのハイプレスの狙いと原則が見え、アグレッシブにボールを奪いに行く姿勢を見せた。
日本が積極的に前から来るとは予想していなかっただろうベルギーだが、さすが百戦錬磨の一流選手がそろったチーム、組織的攻撃をロメル・ルカクへのロングボールへ切り替える。これは日本のハイプレスに対するこの時点での最善策であったように思える。

日本がハイプレスを敢行する場合、前述のようにウイング(乾、原口)がベルギーのサイドCB(アルデルワイレルト、フェルトンゲン)にアタック、SB(長友、酒井)が前にスライドしてベルギーのウイングバック(ヤニック・フェレイラ・カラスコ、ムニエ)にアタックするので、SBの後ろのスペース(=CB横のスペース)が空く。日本のハイプレスを察したベルギーは、その前に出た日本のSBの後ろのスペースへルカクやエデン・アザールが流れ、そこにロングボールを送り込むことによってハイプレスを回避。その後も、ルカクがライン間まで引いたりドリース・メルテンスやムニエが中に入りボールを引き出すなど、戦術的な動きによるポジショナル・ゲームにより日本のプレスはマークがズレズレになりなかなか機能しなくなってしまい、立て続けにシュートチャンスを作られる。日本のハイプレスがハマりそうになるとルカクにロングボールを放り込まれ大迫と両ウイングが前プレスの後に必死に自陣に戻るというのを繰り返し、結果的にこれが日本が後半の早い時間でバテてミドルプレスの強度が一気に落ちる原因にもなってしまった。
ベルギーのウイングバックは死にかけていた
一方で、攻撃面ではそれまで日本を牽引してきた柴崎岳は、全試合にスタメン出場した影響からかコンディションが万全ではないように見え、またSBとCBの間(ハーフスペース)の得意なスペースをベルギーの2シャドー(アザール、メルテンス)に埋められ、息苦しさが見えた。サイドCBがハーフスペースを封鎖しているために、乾はなかなかライン間のハーフスペースに入って受けるという得意な形ができず、無理に裏を狙ってしまったり、大迫はさすがにバンサン・コンパニ相手に毎回ボールを収めるのはハードルが高かったのか、下がり過ぎて全体的に組織が深さを取れない時間帯があるなど、思うようにいかない。唯一90分にわたってベルギーに問題をもたらし続けたのは、間のスペースでボールを受けては優れたテクニックとアイディアでチャンスを作り出した香川だけであった。
一方で、「日本のハイプレスがハマりそうになったらSB裏にロングボール」という戦術は、もともと高い運動量が要求されるベルギーのウイングバックにとってもかなりのハードワークであり、彼らの戻りがどんどん遅くなっていっていた。前半終了時にはベルギーのサイドは構造的にもスタミナ的にもほぼ破壊されており、サイドチェンジが有効だというのはこの時点でかなり明確になっていた。
すると、その穴となっていたウイングバックの裏のスペースを突き、日本が後半開始直後に先制。奪ってから周りの選手がスペースを作りながら最後はウイング(原口)の裏に速いボールを供給して得点、というまさにハリルホジッチ前監督が目指していた形そのもののようであった。その後、追いつきたい気持ちが強過ぎるベルギーは、前と後ろが徐々に離れてしまい、真ん中がどんどん空いていく。結果、ポゼッションしながらガラ空きの中盤を楽に通過し互いのエンドを行き来するような試合展開の中で、乾のスーパーミドルが決まり、2点目。ティボ・クルトワがエリア外からのシュートに触れもしないというのはあまり見たことがない。それぐらいスーパーなゴールだった。

戦術の差。「対日本」用に準備された交代策
この予想外の立て続けの失点でベルギーがガタガタになるのが日本にとっては理想的な形だったが、ベルギーは逆に結束し、落ち着きを取り戻す。冷静さと結束を取り戻すきっかけになったのが、マルアン・フェライーニとナセル・シャドリの同時交代。これで狙いがハッキリした。フェライーニがメルテンスと代わって右シャドーに入り、シャドリはカラスコと代わり左ウイングバックへ。ちょうど日本のミドルプレスの強度が前半の過労もあって落ちてきていたタイミングであり、この交代により押し込まれ同点に追いつかれる。
ベルギーは4バックに変えたとの意見を散見したが、フォーメーション自体はまったく変わっていないと思われる。右SBなしの4人でのビルドアップは前述した通りそれより前からやっていたし、ボールサイドのウイングバックが高い位置からアタックした時にCBがスライドして逆サイドのウイングバックが絞って4人のラインになるのも、ベルギーの典型的な守備原則であった。ベルギーの得点のあと2回の日本のキックオフでのベルギーの配置を見れば一目瞭然で、完全に[3-4-3]の形だ。なので、シャドリになって左ウイングバックがより攻撃的になり高い位置を取ったなど、組織のバランスは多少変わったが、フォーメーション自体は変わっていないと見ていいだろう。
この交代は決してむやみな高さ勝負に来たのではなく、日本にリードされた時用に事前から練られていた作戦であったように思える。理由は、まずフェライーニの位置。マルティネス監督はフェライーニを身長の低い長友に当てにきた。吉田麻也や昌子源がグループステージで強靭な世界レベルのFWたちに空中戦で競り勝っていたのを見て、中央よりも日本のDF陣の中でダントツで背の低い長友にマッチアップさせることにしたのだろう。フェライーニはメルテンスほど動きで攪乱させることはできないが、懐が深くボールを収められる。アフロの巨人がこのゾーンで長友・昌子・柴崎の間をうろつき、中盤での数的優位を作りながらボールを受けて収めてチャンスメイク、そして自分もエリア内に入って空爆に参戦。そして、右シャドーのフェライーニにクロスを上げられるよう、左ウイングバックに攻撃的で質の高いクロスボールを供給できるシャドリを入れたのは非常に理にかなっている。
この2枚替えはマルティネス監督が即座に思いついたというより、日本にリードされパワープレーをする時用に事前にアイディアを持っていたと考えるのが自然だろう。正直、攻撃的なポジションで真ん中のラインならどこでもできるフェライーニを、まさか右ウイング(シャドー)で使ってくるとは思っていなかった。結果的には、両者ともがゴールを決め、プロセスとしても結果としても最高の交代策となった。高さで勝ったのではなく、高さを生かした戦術で勝った、の方が正しいだろう。
2失点目、昌子と他DF陣の判断がズレていた
最初の失点は非常に不運であった(あのCKになるまでのプロセスには運で片付けられない問題はあったが)。
だが、2失点目は不運でも純粋な高さでやられたのでもなく、完全にロジックだ。ポーランド戦のマッチレポートでも日本の大きな弱点の一つとして指摘していたが、危惧していたファイナルサードでの守備の脆さ、守備原則のなさが原因であり、「フェライーニが高かった」「DFの高さ不足」で済ませてはいけない。アザールが後ろ向きにボールを動かした瞬間、中央の昌子がラインを上げようとした。両手を広げラインを上げるよう指示し自分も高い位置を取る。だが、周りの選手は昌子に合わせてラインを上げることをしない。結果、昌子だけが不自然に最終ラインより高い位置を取り、そこをフェライーニに支配され失点。決して、純粋な高さ勝負で負けたのではなく、守備原則のなさと統率力のなさによる自滅だ。

あのような状況下で、エリア内では誰がラインコントローラーで誰が統率するのか原則は決めておかなければならないし、エリア内の守備はゾーンなのかマンツーマンなのかも練習の時点でハッキリさせなければならなかった。ファイナルサードでの守備原則がなく、「なんとなく」でずっと守っていたツケがここで回ってきた。初戦からずっとエリア内で危険な状況を作られていたのだから、そこから学習してファイナルサードでの守備原則を作っておかなければならなかった。昌子がラインコントローラーと決めておき、アザールがボールを持った時に全員が昌子と同じ高さにポジションを合わせていれば、フェライーニは余裕でオフサイドだった。もし他の選手がラインコントローラーと設定しエリア内は人を捕まえてマンツーマンなどの原則を決めておけば、昌子がフェライーニと互角に競り合う状態になったため、あそこまで余裕を持ってヘディングされることはなかっただろう。
あのカウンターを防ぐ方法はあったのか?
ベルギーの交代策がハマった一方で、日本の交代策はあまり効果的なものではなかった。柴崎に代わって入った山口は、ハーフスペースをうろうろ彷徨ってボールの収まり所となるフェライーニを封鎖する根本的な解決にはならず、本田は逆サイドに流れてチャンスを作ろうとするものの、むしろ守備面で左ウイングバックのシャドリにスペースを空けてしまっていた。交代で消耗してしまったミドルプレスの強度の再生をしたいところだったが、交代後もプレスは機能せず、不慣れな撤退戦で何とか持ちこたえる。
そして、最後のCKのシーン。敵ながらあっぱれの、思わず息を飲むような素晴らしいカウンターを食らい、日本は美しく散った。圧倒的な能力を持つベルギーの個が、今大会初めてチームの勝利のために全員がエゴを捨て、美しい団結と連携を魅せた9秒間だった。確かにあのシーンで「あそこでこうしていれば」というのはいくつもある。本田のCKの狙い、カウンター対策のポジショニングを取れていなかった、キャッチした直後のクルトワの前に立ってすぐに速攻を出させない選手がいなかった、遅らせるorファウル覚悟で奪いに行くかで山を張れなかった山口、戻り切れなかった守備陣、おそらく日本の弱点として事前にこの形を狙い準備していただろうという戦略の差……。

もっと言えば、その前にも自分たちのCKからカウンターを食らいデ・ブルイネに決定機を作られ、そこで取られたCKから同点ゴールを許しているのだから、もっと慎重になるべきだった。同じミスを2度して2度失点するというのは、このレベルでは許されない。さらに言うと、そもそもCKというのは世間で言われているほど大きなチャンスではないので、リスクをかける価値もあまりないのではないか(2010年W杯、EURO2012、10-11シーズンのCLなど計124試合の1139回のCKを分析した研究『Casal, Dios, Arda & Boubeta, 2015』では、CKが得点になる確率はわずか2.2%、つまり50本に1本の割合だった)。
だが、それらは所詮、すべて結果論だ。あそこでリスクをかけず延長戦になったとしても厳しい試合だったのは間違いないし、あのCKでゴールを決めていた可能性だってあった。従って、上記の指摘のどれも、あの死闘を全力で戦い切った選手たちには口が裂けても言えない言葉だ。
日本サッカーの課題が詰まった90分間
今、ここで本当に問うべきは、「あの場面で誰が悪かったか」ではなく、「2-2の後半ラストプレーでまったく同じ状況が日本に訪れた時、日本はあれと同じ速さ・質のカウンターでベルギー相手にゴールを決めることができるか」だ。また、「もしベルギーが先に2点リードした場合、ベルギーならどうしていたか」だ。答えは明確だろう。
日本は2点リードしてから、引いて守ることもできなかったし、効果的なカウンターを繰り出すこともできなかった。あの状況での定石では、2点離されたことからリスクをかけて攻撃してくる相手に対し、自陣でブロックを引いて跳ね返し、カウンターで一気に仕留めて息の根を止めることだ。
だが、日本は常に日本のサッカーしかできなかった。いわゆる「自分たちのサッカー」や「プランA」しかない状態で勝ちに行くというのは、まだ良いかもしれないが、少なくとも相手がずっと「プランA」だけでくるとは限らないのがサッカーだ。ということは、相手がプランを変えてきた時、相手の「プランB」に対応できる「抗プランB」を持ち合わせていなければならない。例えば、スペインもプランAしかないチームだが、その範囲内で相手がプランBにした時の対策である抗プランBは常に持ち合わせている。それが、今の日本にはなかった。選手選考の問題ではない。日本中から誰を集めてもあのベルギーと同じ速さ・質のカウンターはできないだろうし、ルカク&フェライーニの空爆に30分耐えられるDFもいないし、右シャドーにフェライーニを入れる奇策に対応できそうな監督もいない。つまり、これは現段階でどうしようもない問題だったわけだ。
これが冒頭の、「何も足りないものはなかったが、それはつまり何もかもが足りなかったということでもある」という言葉の真意だ。何も足りなくなかった。日本は正々堂々戦って素晴らしいサッカーをした。日本の誰もがベストを尽くした。だが、この試合に勝利するため、ベスト8の壁を乗り越えるには、残念ながら、何もかもが足りなかった。

しかし言い換えれば、この試合は今後20年の日本サッカーが向き合っていく課題が詰まった90分間だったと言って良いだろう。
試合終了のホイッスルを聴いた時の私の一番の感想は、「負けでいいから延長戦をやってほしい」だった。純粋に、負けでも何でもいいから、もっとあの試合を見ていたかった。それだけ美しく勇敢で、面白い試合だった。だからこそ、非常に悔やまれる敗戦だった。この悔しい敗戦を、日本は今後20年の糧にしていかなければならない。
今回の敗戦はシチュエーションとしてはドーハの悲劇に近いとも言えるかもしれない。まさかたどり着くとも思っていなかった悲願のW杯ベスト8まであと一歩というところまで迫りながら、後半アディショナルタイムに歴史を変えるチャンスが指の間から滑り落ちた。だが、私たちはあのドーハの悲劇を未来の日本サッカーへの糧にし、やっとここまでたどり着くことができた。日本サッカー史に残る悲劇であったのは間違いないが、「あれがあったから今の日本サッカーがある」と胸を張って言えるぐらい、現在までその悲劇を力に変えてきた。
初出場からの20年で、日本はグループステージ敗退が3回、ベスト16が3回。よって、この20年での日本の世界での立ち位置は、グループステージ敗退とベスト16進出のちょうど間だったと言っていいだろう。そして、また、これからの20年が始まる。20年の努力と20年の美学、20年の戦い。そして、その積み重ねの、100年の戦い。まだまだ日本サッカーの進むべき道は、果てしなく、果てしなく、果てしなく、長い。

Photos: Getty Images


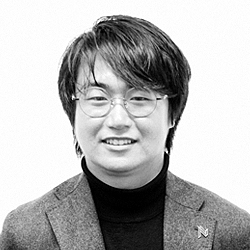
Profile
林 舞輝
1994年12月11日生まれ。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチームのアシスタントコーチを務める。モウリーニョが責任者・講師を務める指導者養成コースで学び、わずか23歳でJFLに所属する奈良クラブのGMに就任。2020年より同クラブの監督を務める。














