
なぜ日本は数的優位で苦しんだ?コロンビア戦の謎を林舞輝が解く
林舞輝の日本代表テクニカルレポート第1回:日本対コロンビア
欧州サッカーの指導者養成機関の最高峰の一つであるポルト大学大学院に在籍しつつ、ポルトガル1部のボアビスタU-22でコーチを務める新進気鋭の23歳、林舞輝が日本代表のゲームを戦術的な視点から斬る。第1回のテーマは「コロンビア戦で、なぜ日本は数的優位にもかかわらず苦しんだのか?」。
試合開始直後の退場&PKから試合前のプランが崩壊した両チーム。その中で、組織として戦おうとしたコロンビアと、個がその場その場の判断で「孤軍奮闘」した日本。「個の日本」が「組織のコロンビア」を走力と技術で上回ったという試合だった。
開始わずか3分でカルロス・サンチェスが退場しPKを獲得という、日本にとって望外の幸運が訪れる。ペケルマン監督にとってはもちろん想定外だったろうが、西野監督もまさか3分で相手が1人少なくなり1-0という状況は想像できなかっただろう。私もフットボリスタ本誌でコロンビア戦の分析と対戦シミュレーションをしたが、さすがにいきなり相手が1人少なくなるシミュレーションはできなかった。ここからは、両チームにとって想定外のファンタジーの始まりであった。
正解は「3対1のボール回し→ボランチの引き出し」
残り85分を1人少ない状態で戦いながら点を取りに行かなければならないという最悪の状況になったコロンビアは、トップ下のキンテーロをボランチの位置に下げ[4-4-1]の形でブロックを引き撤退する。前からのハイプレスは封印し、陣形を整えて構える方を優先。1人少ない状態で無理に前からボールを奪いに行き体力を消耗するより、まずは守備陣形を整え2失点目は何としてでも避けようという判断であり、前半は0-1のままで良いと思っていたはずだ。その上で後半のどこかで勝負に出ていくつもりだったのだろう。思いもしない最悪の事件からチームで柔軟に対応し即座に組織を作り直したコロンビアは、さすがと言えよう。

一方で、日本は1人多くなりリードしているにもかかわらず、おそらく事前のプラン通りに縦へ、前へと出ていく。ボールを繋ごうと前に出てくるコロンビア相手なら効果的だったかもしれないが、状況はすでに変わっていた。日本の攻撃はコロンビアのブロック守備にかかり、カウンターを食らう。ここに、組織としてコロンビアとの差が出てしまった。試合前のプランが崩壊した両者だが、日本は組織としてどう動くかが定まらなかった。
1点リードで1人多いという状況にもかかわらず、リスクのある難易度の高い縦パスを通そうとし、それを読まれて回収され、リスクの代償を払わされる。その“不必要なリスク”を個のハードワークと頑張りで何とかカバー。ポゼッションの局面でも3人目の動きは皆無に等しく、それ以前に(SBとサイドMFのような)2人の関係の時点で連係が取れず簡単にボールをプレゼントする。結局、数的優位は関係なく乾や香川の個で守備を剥がしていき、守備面でも――ここでも数的優位の関係ない――個々の「デュエル」でボールを奪っていく。全体で数的優位でも相手陣内では数的優位ではないので、前線の守備はズレてハマらない。試合開始直後の想定外の事件への組織マネジメントは、完全にコロンビアが上回っていた。
日本の最善策は、コロンビアと紳士協定を結んでダラダラと後ろでボールを回しながら、その協定を裏切る瞬間を探ることだった。1人多い状態で1-0で前半終了ならば、試合前の想定をはるかに上回る結果なのだから。そもそも相手は前半は1-0のままで良いと思っているゲームプランに移行しているのだから、相手が動かない限りリードしているこちらから無理に攻めに行く必要はまったくない。ボールを奪われないことを最優先にし、暗黙の平和条約を結んでボールをゆったり回しながら、ボールを前後ではなく左右に動かして相手の組織を動かして消耗させ、後半の勝負に出るための体力をなるべく奪う。そして、万が一コロンビアが痺れを切らしてプレスに来た場合は平和条約を破棄して仕留めに行く。
具体的に言えば、コロンビアは[4-4-1]で守っているのだから日本の2人のCBは構造的に2対1の数的優位が作れる。なおかつ、コロンビアの真ん中の2ボランチは撤退組織を整えることを優先し前には出てこなかったので、日本の2ボランチの柴崎と長谷部が下がってボールを引き出しに行けばフリーでボールを受けられる状況だ。最前線「1」のファルカオも1人少ないので体力を温存したいのかそれほど追いかけ回しにはこないので、ボランチの1人が落ちて「2CB+ボランチ」vs「ファルカオ」の3対1の状態で永遠にボールを回すことができた。
ボールを保持しながら陣形を整え、攻撃するフリをしてはやめて戻してひたすらボールを回す。ここに痺れを切らしてコロンビアのボランチが食いついてくれば、それが平和条約を破棄する合図であり、試合を終わらせるチャンスだった。ボランチが食いつけば組織のど真ん中、最も危険なエリアに人がいないことになる。そこに速い縦パスを(例えばトップ下の香川あたりに)1本通してしまえば、一気に前線で数的同数で攻撃できる状況ができ上がる。コロンビア全体がコンパクトに組織で前に出てくれば、シンプルに裏を狙い、そのセカンドボールを拾う。それを繰り替えすのが最善策だった。
ペケルマンの英断。バリオス投入の計算
この「1-0で前半を終わらせる談合サッカーをしながら相手ボランチのプレスを攻撃のスイッチにする」というある種の定石を選択せず、数的優位も関係なくひたすら事前のゲームプラン通りに前にボールを運ぼうとしている日本を見て、ペケルマンはボール奪取能力が高い守備的ボランチのバリオスの投入を決断した。
ただでさえ、なぜか前にリスクをかけて縦パスを通そうとする日本に対し、本職でないキンテーロが担っているボランチの位置にボールが奪えてセカンドボールを拾えてシンプルにさばける選手を置けば、日本の縦パスを守備網にかけそのままカウンターに移行できるし、そのセカンドボールを拾って二次攻撃も可能だ。本職でないキンテーロから守備的なバリオスがボランチを務めることになるので、サイドのMFは気を使わずに前から圧力を加えられ、日本のパスワークの中心である柴崎にもプレスをかけやすくなった。

また、ペケルマンの中ではハメスを後半から出すというのはおそらく決定事項であり、この交代はある意味でその準備という面もあったようにも思える。ここで守備能力の高い中盤の選手を置いておけば、後で守備能力で劣るハメスを躊躇なく入れることができる。現状で最も有効な手であり、ある意味では後に勝負所でハメスを投入する布石になっていたわけだ。
ここでコロンビアの攻撃の最大の武器であるクアドラードを下げるという決断を遂行したペケルマンの判断はさすがである。「キンテーロをセットプレーのキッカーとして残しておきたい」「守備の貢献度ではクアドラードが最も劣る」「この試合展開では個で打開するよりも素早くボールを動かせる選手を優先」「人数が少ないのだから個で勝負するより選手間のゾーンがあやふやな個所を狙っていける選手が有効だ」と理屈ではわかっていても、チームの中で最も個の攻撃力がある選手を下げるというのは、大舞台で容易に下せる決断ではない。そして、結果的にこれが功を奏し、コロンビアは同点に追いつくことに成功する。
光った西野采配。ハーフタイムの修正と適切な交代策
後半に入ると、ようやく日本が後方で無理せず回して焦らして縦、セカンドボールを拾って繰り返し、という定石通りのプレーをやり始める。その上で相手のSBを個で崩し、リスクをあまりかけずにチャンスを作り出すことに成功。ハーフタイムでしっかり修正できた証であるが、欲を言えば前半の追いつかれる前の段階から選手同士でコミュニケーションを取ってピッチ内で修正してほしかった。
59分、ペケルマン監督はハメス投入を決断する。攻撃に行くスイッチとしたかったのだろうが、この交代策は裏目に出る。運動量が多くなく、守備時、特にボールを奪われた直後の切り替えの守備に問題のあるハメスを出すのは守備面で大きなリスクがあった。簡単に言ってしまえば、コロンビアはボールを奪えなくなるということだ。結果としては、守備面で大きく劣ってしまい実質11対9.5のようになってしまい、ボールを持って初めて能力を発揮できるハメスにボールを持たせるところまで行けなかった。

運動量が落ちてくるあの時間帯、さらに1人少ないという状況を鑑みれば、ハメスを出すなら1トップ一択だった。もっと言えば、あの試合状況でハメスを出すメリットというのもあまりなかった。だが、名実ともにチームのエースであるハメスはどうしても使わなければいけなかったのだろう。ペケルマンにはクアドラードを下げる勇気はあってもハメスを使わない勇気はなかったいうことだ。
日本はそれを見て、ボールをキープできて局面のインテンシティ(試合のテンポ)を下げることができる本田を投入。本田は試合の時間と状況をよく見極め、スローテンポとボールキープでボールの継続した保持と試合全体のインテンシティを下げることに寄与した。山口蛍の投入は選手へのメッセージにもなり、この試合のMOMである大迫を下げ前線から追いかけ回せる岡崎を投入。また、この試合では日本が数的にも心理的にも(コロンビアにとって日本相手の引き分けは痛い)有利であり、先に動く必要はなかった。ハーフタイムでの修正も含め、相手の交代策を見ながら適切な交代カードを切っていった西野監督の采配は、試合を通して最適なものであったように思える。

「カミカゼ」ではなく「ロジック」が必要
試合を総括すれば、拠りどころとなるゲームモデルがない中で、全員が局面で120%出し切ることにより何とか勝ち切ったという試合であった。運や偶然性に加え、全員が魂を捧げて頑張ったから勝利できた。ある意味で、サッカーという不条理なスポーツの不条理な部分にすべてを捧げたことによる勝ち点3であった。もちろん運だけでは決して勝てなかった。2ゴールを決めたことも、そのゴールに繋がるPKとCKを奪ったのも、紛れもなく日本の実力そのものである。
ただ、次のセネガル戦でも同じ幸運が訪れるというのは考えにくい(何が起こるかわからないのがサッカーなので、訪れる可能性もゼロではないが……)。セネガルは非常に強力な個に加え、欧州のチームと比べても遜色ない組織力がある。組織力の高いアフリカのチームというより、もはや身体能力と個の能力がずば抜けてるアフリカ出身の選手だけを集めたフランスのチームという感じだ。
そんなチームを相手に同じように各々が「孤軍奮闘」しても、難しいと言わざるを得ない。個の力、個の頑張りで言えば、日本はW杯32カ国の中で一番かもしれない。すべての選手が常に120%を出し切り、よく走り、耐え、集中し、球際でも必死に戦う。まさにサムライのような姿であった。そして、次の強敵セネガルと良い勝負に持ち込むには、その「頑張り方」を決めることだ。日本がやるべきことは限られる。ハイプレスをかけてもダメ、引いて守っても耐えられないのならば、自陣から35メートル付近にラインを設定して組織をコンパクトにしながら、ミドルプレスからのショートカウンターを軸にする以外の手段がない。しっかりとした組織作りの中でプレーの原則と決まり事を決め、「頑張り方」を改善しなければならない。正直、コロンビア戦のように全員が120%で頑張り切っても、11人対11人でセネガル相手では厳しい。
個々が独立した局面でがむしゃらに頑張るのではなく、まずは組織として「どう頑張るか」を決めること。次戦までまだ時間はある。全員が「孤軍奮闘」してつかんだ勝利から学び、戮力協心(りくりょくきょうしん)したサッカーでセネガルに立ち向かってほしい。

Photos: Getty Images
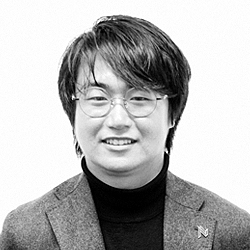
Profile
林 舞輝
1994年12月11日生まれ。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチームのアシスタントコーチを務める。モウリーニョが責任者・講師を務める指導者養成コースで学び、わずか23歳でJFLに所属する奈良クラブのGMに就任。2020年より同クラブの監督を務める。









