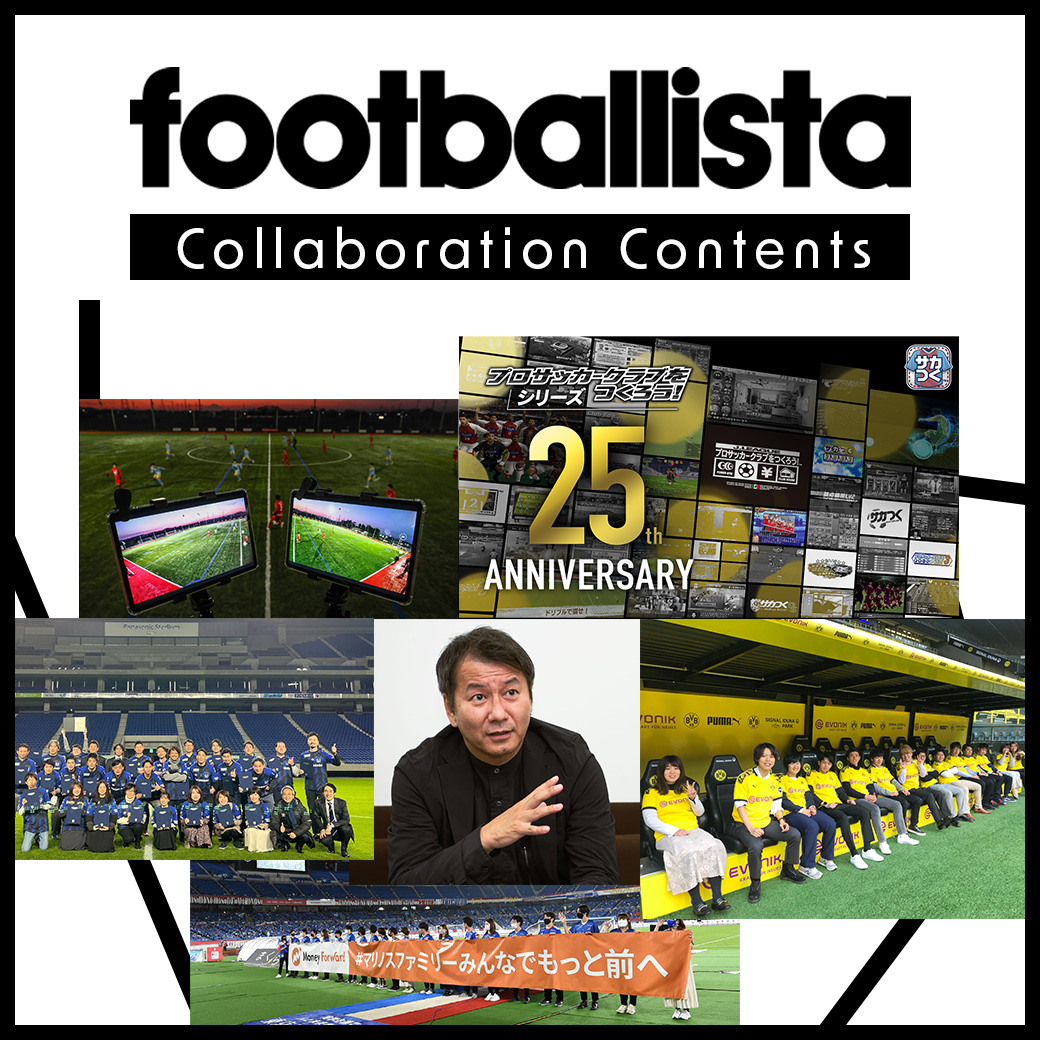「セットプレー革命」の内実#7
ワンチャンスをモノにするフリーキックやコーナーキックなどのセットプレー。プレミアリーグでも専門コーチの存在が脚光を浴びているように、トップレベルの拮抗した試合でも「違い」を作る“飛び道具”に注目が集まっている。その戦術と攻防の最新トレンドから浮かび上がる「革命」の内実とは?
第7回では、セットプレーの中でも回数が最も多いスローインに注目すべく、リバプール、ドルトムント、アヤックスとも働いた「世界初のスローイン専門コーチ」として知られるトーマス・グレネマルクに直撃。昨季の川崎フロンターレでの指導と、町田ゼルビアのロングスローへの対策について教えてくれた。
<トーマス・グレネマルク公式サイトはこちら>
スローイン指導の鍵はパターンではなく原則
――プレミアリーグでも13クラブが雇っているように、近年はセットプレー専門コーチが浸透してきていますが、スローイン専門コーチの需要に変化はありましたか?
「スローイン専門コーチとして働いてもう20年以上になりますが、確かにここ数年間でセットプレーコーチは浸透してきています。私も指導現場でよく一緒に仕事をすることが増えました。ただ、彼らはあくまでもコーナーキックやフリーキックの専門家であって、スローインの専門家ではない。だからこそ私に依頼が来続けています。フリーランスとして母国のデンマークを拠点にリバプール、ドルトムント、アヤックス、ブレントフォード、ウニオン・サンジロワーズ、ミッティラン、イングランド女子代表といった欧州のプロチームはもちろん、それ以外の大陸でも年に6~8のプロチームを指導して計15タイトルの獲得や、昇格や出場権の獲得に貢献してきましたが、私の在籍期間中に彼らがパフォーマンスを向上させたのは偶然ではないですよ」
――4年前にスローイン指導が必要な理由として「1試合でのスローインの数は40〜60回」「ほとんどのチームにおいてスローイン後のボール保持率は50%以下」「90分のうちスローインとスローイン後のプレーに費やされる時間は約15〜20分」という数字を訴えていましたが……。
「あらためて統計を取ったわけではないですが、私の体感では当時からあまり改善されていませんね。実際にプレミアリーグクラブのセットプレー専門コーチの中には、スローイン指導についての助言を私に求めてくる知り合いもいるくらいですから。とりわけスローインはセットプレーの中で回数が一番多く、その中でも毎回のように出し手と受け手、味方と相手の位置が異なります。選手が配置が乱れたままリスタートすることも少なくないのですが、パターンしか落とし込めないセットプレー専門コーチが多すぎるんです。そうした知識の不足に加えて、まだまだスローインを練習する時間も増えていません。質と量ともに課題を抱え続けているのは間違いありませんね」
――本特集ではセットプレー専門コーチのジョバンニ・ビオにもインタビューしていますが、トッテナム時代は「セットプレーには週1回、15~20分という限られた時間しか費やしていなかった」と話していましたね。
「その中で彼らはコーナーキックやフリーキックの練習に焦点を当てて取り組んでいるわけで、そもそもスローインの練習にうまく時間を割けていなかったとしても驚きません。さらに言うならスローインの半分はオープンプレーですが、トップレベルでさえそのトレーニングをするのはプレシーズンだけというチームが少なくないんです。それでは体に染みつかず、シーズンが進むにつれて疎かになってしまいます。年間通して毎週練習していかないと身についていきませんよ」
――昨年は川崎フロンターレも指導されていたんですよね。Xに投稿されていた集合写真が日本で注目を集めていました。
「そうです。私の公式WEBサイトを通じて川崎Fから依頼をいただき、昨年7月の終わりから8月の初めにかけて来日して3日間、そのトップチームを指導しました。もちろんチームを指導する際は、事前にそのチームスタイルやフォーメーションを調べたり、スローインを攻守ともに映像分析して指導内容を考えるのですが、川崎Fはポゼッションを重視するチームなので、私の持つ『長いスローイン』『速いスローイン』『賢いスローイン』というスローインの三原則のうち『速いスローイン』と『賢いスローイン』を優先させて選手たちに落とし込みました」
“This week I had the honor to visit Kawasaki Frontale and coach them in my “Long, Fast and Clever Throw-in Philosophy”
It was my first Japanese club, and I was really impressed by the kindness and professionalism from the staff and players. I felt like a part of the family pic.twitter.com/veJP8fK5xF
— Thomas Gronnemark (@ThomasThrowin) August 4, 2024
――「原則」という呼び方には何か理由があるんですか?
「これは現代サッカーにおける根深い問題の1つですが、誰でもどんな状況でも使える攻略法としてみんなパターンを探していますよね。ただ、そんなものは存在しません。サッカーでまったく同じような状況が起こるなんてことはなく、選手一人ひとりの個性も異なる上に、一つひとつのプレーに監督が指示を出すわけにもいきませんから、ピッチに立つ選手が自分で決断しなければならない。それはスローインも同じで、その判断材料となる投げ方や考え方、そして連携して質の高いスペースを生み出す方法を原則と呼んでいるというわけです」
川崎Fに伝授した「速いスローイン」と「賢いスローイン」とは?
――スローインと聞くとまず思い浮かぶロングスローは、川崎Fには教えていないんですね。……



Profile
足立 真俊
岐阜県出身。米ウィスコンシン大学でコミュニケーション学を専攻。卒業後は外資系OTAで働く傍ら、『フットボリスタ』を中心としたサッカーメディアで執筆・翻訳・編集経験を積む。2019年5月より同誌編集部の一員に。プロフィール写真は本人。Twitter:@fantaglandista