サッカー監督に求められるのは「対話」ではなく「演説」の力

芸術としてのアルゼンチン監督論 Vol.4
2018年早々、一人の日本人の若者がクラウドファンディングで資金を募り、アルゼンチンへと渡った。“科学”と“芸術”がせめぎ合うサッカー大国で監督論を学び、日本サッカーに挑戦状を叩きつける――河内一馬、異国でのドキュメンタリー。
サッカー監督にとって重要なのは、「対話」ではなく「演説」である――と私が感じたのは、いつ頃からだっただろうか。選手(集団)に向かってうまくスピーチができるか、それとも下手くそなスピーチしかできないのか……私は、それ次第で監督のキャリアを左右しかねないとさえ思っている。アルゼンチンに来た理由の一つだ。ビエルサの映像を見て、シメオネの映像を見て、アルゼンチン人選手がロッカールームで選手を鼓舞する映像を見て、「さてはアルゼンチン人、演説(スピーチ)が上手だな?」と思った。その通りだった。
■「説得」で何とかなってしまう社会
アルゼンチンの街を歩いていると、おそらく10歳未満の小さな女の子と、その父と母が前からやって来た。母は赤ちゃんが乗ったベビーカーを押し、隣を歩く女の子の手には風船が握られている。このまますれ違う形になるのか、と思ったところで、風船を握った女の子が両親に向かって「こっちに行きたい」と、指を指して別の道を示している。何を言っているのか初めは聞こえなかったが、どうやら「どうして私はこっちの道を通りたいのか?」両親を説得している様子だった。初めこそ「こっち(元いる道)を行くよ」と言っていた両親だったが、次第に女の子の主張に耳を傾けていく。なぜなら、その小さな女の子は「ダダをこねている」わけではなく、堂々と主張をしているからだ。日本ではあまり見ない光景のように思う。
「説得」とは、子供が感情をのせた言葉で親に語りかけることであって、ダダをこねて親を困らせることではないし、「ダメなものはダメ!」と子供の話を聞こうとしない親では決して成立しないものだ。結果的に、自分が行きたい道を通ることができたその女の子は、満足げに私の前を曲がって行った。これは、年齢や立場が「主張すること」に一切関与してこないアルゼンチンならではの状況なのかもしれない。1度や2度ではなく、何度も似たような状況に遭遇した。これは何も「親と子」の関係のみではなく、「生徒と先生」、そして「選手と指導者」でも、同じような状況であることは容易に想像ができる。アルゼンチンの子供は、平気で大人を説得しにかかるのだ。
子供だけじゃない。そのようなことが当たり前の環境の中で育った大人たちも同じく、とにかく日常生活の中から「人が人を説得する」場面を見ることが多い。アルゼンチン人の友達とスタジアムに試合を観に行った時のことだ。アルゼンチンのスタジアムでは、最低2~3回ボディチェックをされるのだが、その最終関門で、ある警備員が「カメラを持って中に入ることはできない」と私に告げた。そんなに大きなカメラを持っていたわけではないし、これまでもカメラを持って入ったことは何度もある。それを伝えても、頑なに警備員は首を縦に振らない。
すると、様子がおかしいことに気づいた友達が寄ってきて、「こいつは日本から来ているんだよ! もう二度とチャンスは来ないんだ(大嘘)。それでな……」といろいろ理由を重ねて警備員を説得し始めた。「いやいや、何を言ってもダメだったから、俺は諦めるよ」と“日本人”を発揮していた私をよそに、友達は見事警備員を説得してみせたのだった。その「適当さ(人によって何を言うかわからない)」から波及する「説得すればいけるぞ、諦めるな」という空気は、間違いなく国全体に流れている。これが良いか悪いかは置いておいて(多分悪い)、とにかくアルゼンチン人というのは、日頃から「説得を試みること」を通常の発想として持ち合わせているのだ。
この「人を説得する」という習慣は、「人前に出て集団に何かを訴える」という行為に直結しているように思う。アルゼンチン人に何かを訴えられると、心が動くのは日本人である私も同じだ。指導者養成学校の講師たちが話す姿には、何度も感心させられている。堂々とした佇まい、相手に訴えかけようとする姿勢、声の抑揚、身体全体の使い方……。明らかに日本人が持つ空気とは違うものを感じるのだ。
それを最もよく実感したのが、アルゼンチン国内リーグで監督を務めた経験を持ち、国内でも有名なリカルド・カルーソ・ロンバルディの講義を受けた時だ。友人が「彼はVende humoだよ」(ほら吹き・嘘つきのような意)と笑うだけあって、その雰囲気は、なんと言うか「マラドーナみたいなおっちゃん」である。ただ、とにかく陽気で、THE・南米人の彼は「人前に出て集団に何かを訴える力」がずば抜けて凄かった。100%言葉がわかるわけではない私でさえ、なんかこう、言葉にしづらいので想像してもらうしかないのだが、最終的には「これは勝てるな」と思ってしまうような、講義室を飛び出してピッチに走り出したくなるような、そんな想いが込み上げてくるのだ(次ページに「演説」の動画あり)。アルゼンチン人の監督は、伝え方こそ異なるはずだが、突出した人物は間違いなくこの能力を持ち合わせているはずだ。
■「ほら吹き」監督の話術を体感
日本人(私も含めて)は、贔屓目に見ても「スピーチがうまい」という印象はない。なぜなのだろうか。そもそも日本語という言語がスピーチ向きではないとも感じるし、学校教育の問題だと言うこともできるかもしれない。実際アルゼンチンでは子供の頃から、学校でクラスメイトに向けてスピーチをする口頭試験が頻繁に行われるようだ。もしかすると、東洋と西洋の歴史の違いがそうさせているのかもしれない。ローマの皇帝を見ればわかるように、西洋の為政者は民衆に向けてパフォーマンスをする必要があった。古代ギリシャでも、国家が最も上手く機能していた時というのは、非常に優れたリーダーが民衆を演説によって説得し導いていた時だとも言われている。現代史を振り返ってみても、西洋で起こる大きな変化には必ずと言っていいほど天才的な演説が関わっているように思う。
一方で東洋は、中国の皇帝も日本の天皇も将軍も、民衆の目に触れることはなく、演説で民衆に訴えかけるより、逆に距離を離すことで権威を示していたように思う。その歴史の積み重ねによって東洋人の演説が上達していない……というのは少し乱暴かもしれないが、『演説の良し悪しは聴衆によって決まる』というビジネス書があってもおかしくないくらい、西洋人は演説を聞く側の心得を理解している。アルゼンチンの学校で軽いスピーチをする機会があるが、明らかにやりやすいのだ。少しの冗談で笑ってくれたり、「間」で沸いてくれるアメリカ人のスピーチをイメージしてもらえればわかりやすいだろうか。
とまあ、そんなことはどうでもよく、大事なのはサッカー監督にとって「演説」が重要であるということで、そのためには教育がなんだろうが歴史がなんだろうが、後天的にその能力を身につけなければならない。アルゼンチンの指導者養成学校では、幸いその努力もしっかり行われている。次回は、私がこれまで受けてきた授業の内容をもとに、彼らがどのように「人前で話をする職業」の質を上げようとしているのか。その部分について書いていければと思う。
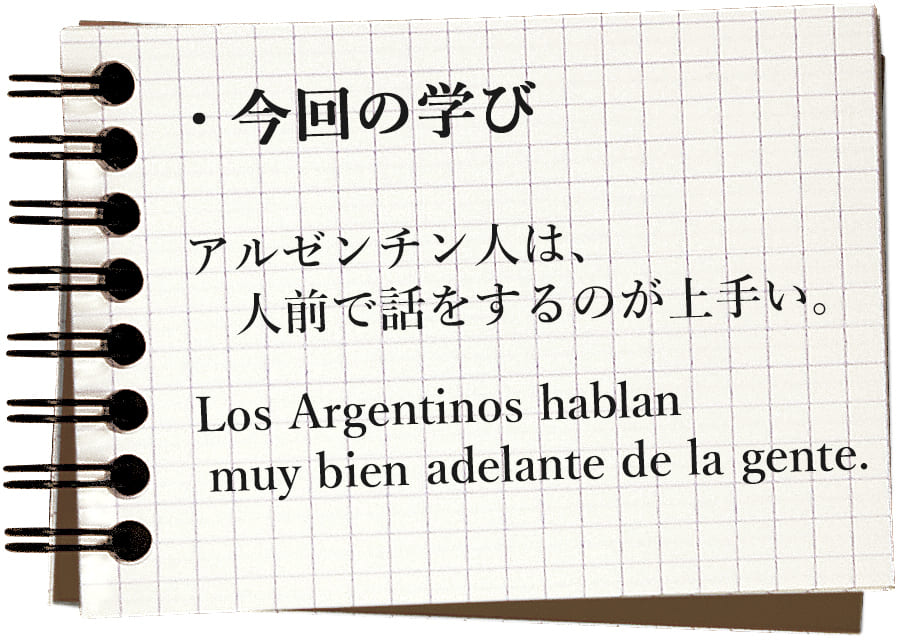
Photo: Getty Images



Profile
河内 一馬
1992年生まれ、東京都出身。18歳で選手としてのキャリアを終えたのち指導者の道へ。国内でのコーチ経験を経て、23歳の時にアジアとヨーロッパ約15カ国を回りサッカーを視察。その後25歳でアルゼンチンに渡り、現地の監督養成学校に3年間在学、CONMEBOL PRO(南米サッカー連盟最高位)ライセンスを取得。帰国後は鎌倉インターナショナルFCの監督に就任し、同クラブではブランディング責任者も務めている。その他、執筆やNPO法人 love.fútbol Japanで理事を務めるなど、サッカーを軸に多岐にわたる活動を行っている。著書に『競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか』。鍼灸師国家資格保持。














