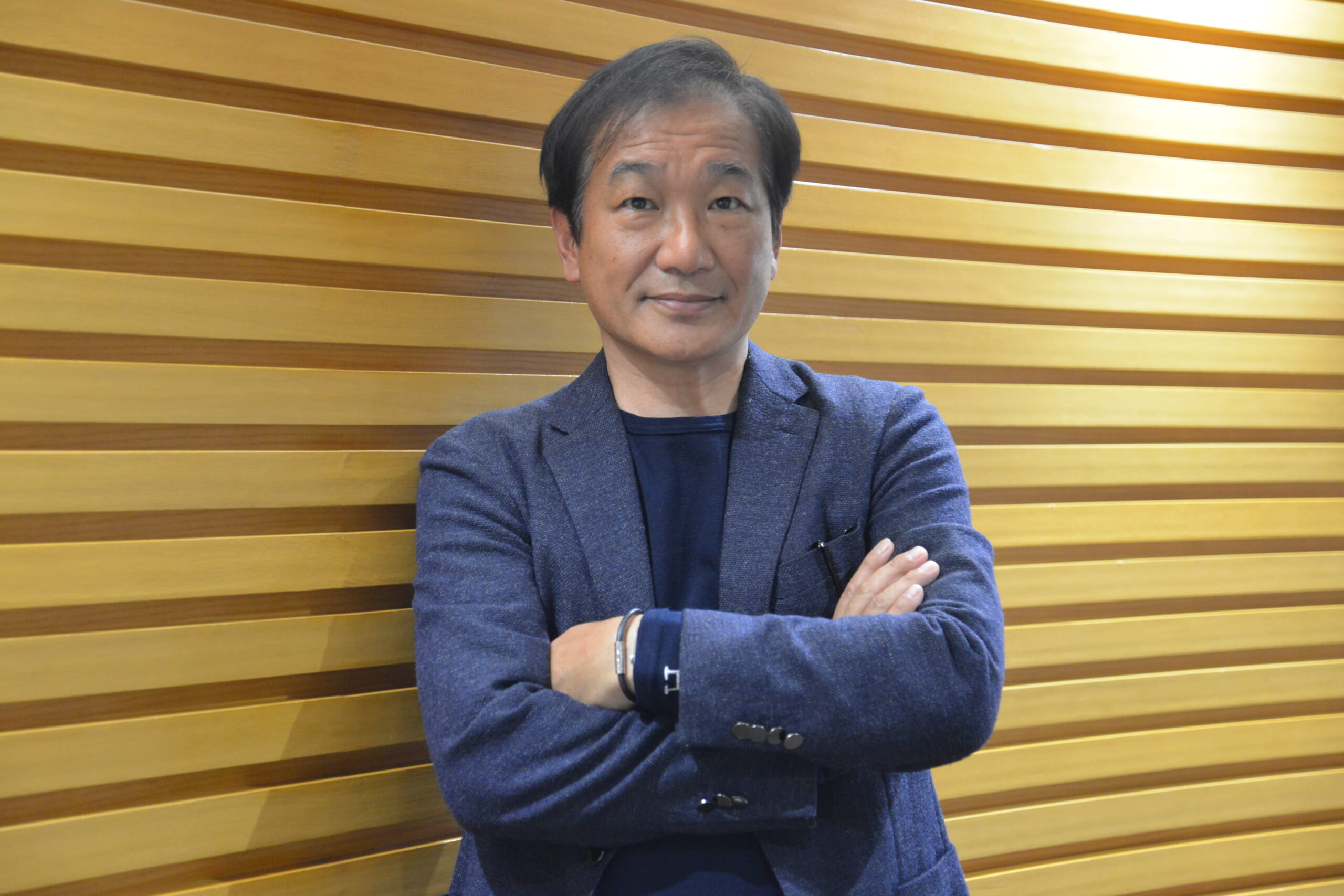アウェイゲームが続いた11月シリーズの北米W杯アジア最終予選第6節、中国を1-3で下した日本代表。ピッチ縮小の表と裏が脚光を浴びたが、その陰で守田英正の温存をはじめとする試行錯誤を重ねていた森保ジャパンの現在地を、『森保JAPAN戦術レポート 大国撃破へのシナリオとベスト8の壁に挑んだ記録』の著者、らいかーると氏が分析する。
過酷な敵地でインドネシアに0-4の大勝を収め、アジア最終予選を無敗の首位で折り返した日本。順位表を見ればライバルたちに7ポイント以上の差をつけていることもあってか、中国とのアウェイゲームでまさかのターンオーバーを解禁する。前節から5人を入れ替えた中で最大のサプライズは守田英正をベンチに置き、左ボランチに田中碧を入れたことだろう。直近の試合で中盤から盤面を変化させていた守田を温存しながら、お馴染みの[3-4-2-1]どのような機能性を見せられるのか。北米W杯出場に向けて余裕のある後半戦は、公式戦で実験を試す貴重な場となっていくかもしれない。
縮小ピッチを最大限活用する中国の[4-3-1-2]
ルーティンのようにキックオフからボールを左サイドに蹴っ飛ばして左CBの町田浩樹を競らせる日本。別のルートを狙うこともあるので、奥の手を隠す意味合いもあるのだろう。セカンドボールを蹴り戻された後に跳ね返しを繋いだ中国のボールを日本が奪うと、この試合で繰り返されたわかりやすい局面がさっそく顔を出した。
/
SAMURAI BLUE
最終予選首位独走体制へ
\中国戦キックオフ
AFCアジア最終予選
中国vs日本
11/19(火)20:00~配信(21:00KO)
#DAZN 今すぐ無料視聴 (登録不要)
無料視聴はこちらhttps://t.co/cqQ5NaHPo9#代表みようぜ#サッカー日本代表
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 19, 2024
中国がボール非保持で敷くミドルブロックの陣形は[4-3-1-2]。日本からすると前回大会で敗れたオマーン戦を思い出すかもしれない。当時に続き敵将としてテクニカルエリアに立っているブランコ・イバンコビッチ監督の「二匹目のドジョウ」だろう。余談だが、現代サッカーで[4-3-1-2]は相手のゴールキックを前から止める配置として標準化されつつある。
試合開始直後あるあるのカオスタイムを必要としなかった根拠は、その役割分担だ。中国のトップ下+2トップの前線3枚は田中、遠藤航のダブルボランチを守備の基準点としながらも、3バックの両脇がボールを持てば中央を消しながらプレッシングをかけるが、真ん中の板倉滉にパスが渡った場合は基本的に放置する。時々、思い出したかのようにハイプレッシングをかけることもあったものの、ボールを受けても落ち着いているGK鈴木彩艶とビルドアップの出口となれる田中を前に、そのリスクとリターンを天秤にかけることを忘れなかった。
中盤3センターとSBの役回りはお互いのコミュニケーションが基盤となっている。例えば右ウイングバック、伊東純也がボールを持った時はSBとインサイドハーフのどちらが右シャドーの久保建英を見て、どちらが伊東を見るかを状況に応じて適宜判断。特に日本の2シャドーはライン間で仕事をしたくても、常に監視されていたくらいだ。拍車をかけたのは中国が地の利を生かして3m狭めたことで注目を集めたピッチの幅だろう。その分、守備側はスライドやカバーの距離が短くなるので、ボールを持たれても消耗は抑えられる。
それでも日本はボールを保持したいが、中国はラフなロングボールを入れてミスを狙っていく。空中戦や裏抜け、失敗してもセカンドボールと3バックに仕掛け続けていく相手に、日本は安全に跳ね返しながら無理矢理に繋ぐことはしなくとも、できるだけボール持つことで中国のプレー機会を最小化する道をこの試合でも選んでいた。
伊東が低い位置でパスを受ける場面が目立つようになると、右CBの瀬古歩夢や町田が高い位置まで出てボールを受けるようになる。ただしインドネシア戦と比べると、攻撃参加を自重しているようだった。おそらくメンバー変更を踏まえて、カウンター対応を考慮した指示があったのかもしれない。
丹念にボールを動かす日本の前に、中盤3枚が根性でスライドして対応し続ける中国。間に合わない場合もすかさずSBがサポートしたり、トップ下が入ったりと織り込み済。数手先まで計算して手当てをしている[4-3-1-2]の採用で中国が前回対戦、7-0の大敗を払しょくしていくかのような立ち上がりの20分だった。
「困った時のセットプレー」は必然だった!
……

Profile
らいかーると
昭和生まれ平成育ちの浦和出身。サッカー戦術分析ブログ『サッカーの面白い戦術分析を心がけます』の主宰で、そのユニークな語り口から指導者にもかかわらず『footballista』や『フットボール批評』など様々な媒体で記事を寄稿するようになった人気ブロガー。書くことは非常に勉強になるので、「他の監督やコーチも参加してくれないかな」と心のどこかで願っている。好きなバンドは、マンチェスター出身のNew Order。 著書に『アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます』 (小学館)。


 𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘
𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘 LINE-UP
LINE-UP