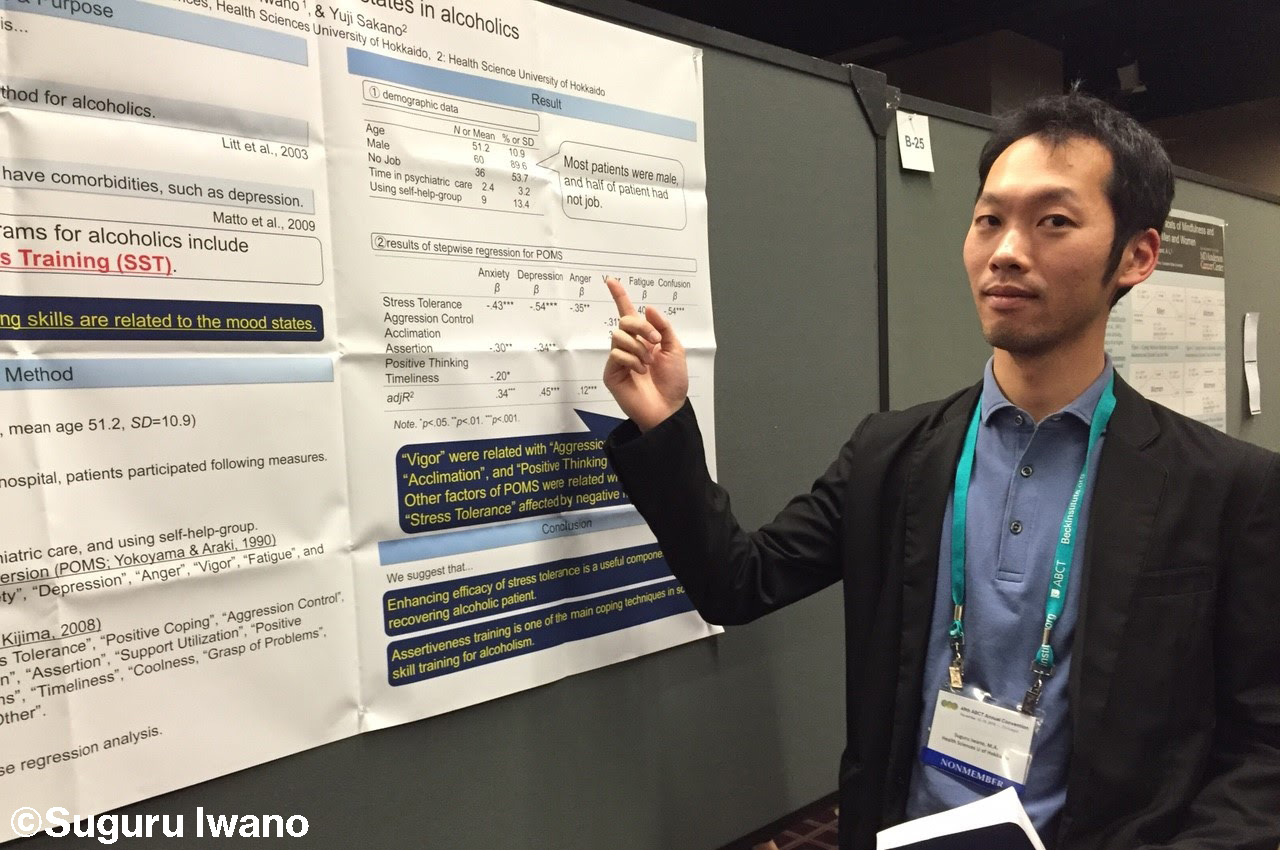悔しさから歓喜のルヴァン制覇へ。「2つの決勝」を闘ったサンフレッチェの2週間

11月、12月開催という異例のW杯イヤーで、天皇杯決勝とルヴァンカップ決勝が2週連続で行われることになった2022シーズン。その両方のカップ戦で決勝まで駒を進めたクラブがある。ミヒャエル・スキッベ率いるサンフレッチェ広島だ。天皇杯決勝はPK戦の末に敗退、ルヴァンカップ決勝は後半ロスタイムの2ゴールで劇的な逆転勝ち。ジェットコースターのような彼らの2週間を密着取材した中野和也が伝える。
天皇杯決勝のPK戦。満田と大迫が背負ったもの
満田誠がボールを持ってPKスポットに近づいた時、止める選手は誰もいなかった。
そう、お前が蹴るんだ。
チーム全員が認めていた。選手たちだけでなく、ベンチも認めていた。
「(満田)マコはPKを蹴るのに適した選手」
ミヒャエル・スキッベ監督はそう判断し、満田に託した。トレーニングでの力を見てのこと。それは選手たちも同様だ。そして何より、今季の彼の活躍を見れば、天皇杯決勝の延長戦でのパフォーマンスを見れば、チームの命運を託すのにふさわしいと誰もが判断した。
天皇杯準決勝の対京都戦前後から、満田と一緒にPKの練習をしていたという大迫敬介は、後ろからずっと祈りを込めて見ていた。が、助走がスタートした時、「やばい、緊張している」と直感したという。
満田の狙いとしたら、低くて速いボール。だが、ボールに力が伝わっていなかった。
止められた。
火の玉のようなプレッシングと強烈なシュートを見せつけ、迷いのないプレーが彼のストロングだったが、この時のPKは確かに満田らしくなかった。それはPK戦の時に見せた強烈なシュートからも、わかる。
日産スタジアムは、なんとも言えない空気に包まれた。4分後、延長後半終了。決勝戦はPK戦に入った。100年を超える天皇杯(全日本サッカー選手権)の歴史の中で、PK戦にもつれ込んだのは1990年の松下電器(現G大阪)対日産自動車(現横浜FM)以来、2度目だ。
実は1964年の決勝で初めて、延長でも決着がつかないという事態になった。その時は古河電工(現千葉)と八幡製鉄、両チームの優勝という結果になっている。個人的にはPK方式での勝ち上がり決定が好きではなく、決勝で決着がつかなかったら1964年のように両チームの優勝でいいじゃないかとも思っていた。サッカーというスポーツとPK戦は、まったくの別物。競技そのものが違うと考えているし、勝ち上がりを決めないといけないトーナメントの方便としてPK戦は存在しているだけ。かつては抽選で勝者が決められたケースもあるし、それよりはまだいいかというくらいの感覚だ。
ただ、今は天皇杯の覇者にACLの出場権が与えられるという事情もあり、なかなか両チーム優勝ということも言えない。それでも、120分の死闘を演じた両チームが、ロシアンルーレットのようなPK戦で雌雄を決することが正しいのか。厳しいし、残酷じゃないか。そう思った。
大迫敬介は過去、公式戦でもPK戦でもPKを止めたことがない。だが若者は、自信を持ってゴール前に立った。直近のトレーニングで何本も味方のキックを止めていたことが、その裏づけだ。
だが、結果は空しかった。
「今、思えば、自分の動き出しが早過ぎた」と大迫は悔やむ。
同期の満田誠のためにも、自分が。
PK戦で決めることができなかった川村拓夢のためにも、自分が。
そういう強い気持ちが、大迫からほんの少し冷静さを奪っていたのか。

表現できなかった「広島らしさ」とは?
いや、そう考えるのは、やめておこう。
甲府のPKはどれも素晴らしかった。そしてそもそも、PK戦にまでもつれ込んだことに、広島がカップを手にできなかった理由がある。ミヒャエル・スキッベ監督が「今季最悪の前半だった」と振り返ったように、立ち上がりから甲府にペースを渡してしまい、デザインされたセットプレーから失点を喫してしまったことが問題だ。
確かに今年の広島は、逆転を何度も繰り返してきた。柏戦では相手に逆転されたところを再逆転。C大阪との対戦ではリーグ戦でも天皇杯準々決勝でも試合をひっくり返した。G大阪戦では2度にわたって先行されながら5点を奪って相手を粉砕している。
だが、サッカーというスポーツは、そう簡単に逆転勝利はできないような構造になっている。手でボールを扱うことができないルールのため、ボールを握っている側にミスが起きやすく、シュートまで持ち込むまでに様々な工夫がいる。だからこそ、ゴールが取れた時のカタルシスは凄まじいのだが、根本的にはサッカーとは得点が入りづらいスポーツだ。
特に日本の場合、カテゴリーによって実力差がかけ離れているわけではない。甲府は実際、天皇杯決勝に進出するまでPK戦に持ち込まずにJ1チームに4連勝している。そういう相手に対して前半に失点してしまっては、苦戦も当然。その要因はもちろん、甲府の素晴らしさもあったが、一方で広島らしさがまったく表現できていなかったことも大きい。
では、広島らしさとは何か。戦術的なことはともかくとして、最も重要なのはやはり勇気だ。勇敢さだ。基軸戦術であるハイプレスは、当然のことながら相手にスペースを与えやすい。ボールに向かって守備をすれば、逆も取られやすい。そういうリスクマネジメントを優先してしまうと、身体は動かなくなる。
スキッベ監督が導入したことで最も意味深いのは、「リスクマネジメント<リスクテイク」の不等式だ。この不等式があるからこそ、チームの戦い方がアグレッシブになり、先鋭的になる。
もちろん、多くの指導者が「リスクを取らないと得点できない」ことはわかっている。だが、それをなかなか試合で表現できないのは、「リスクマネジメント≧リスクテイク」という考え方から脱却できないからだ。その発想を突き詰めると、「負けたくない」に行き着く。現代のサッカーは相手に対する研究が盛んで、だからこそ情報を隠したがる。それもまた、「負けたくない」に通じている。
スキッベ監督も、もちろん負けず嫌いだ。だが、彼の場合は発想が違う。
「リミットを超えていけ」
彼の口癖だ。試合に向かっていく心構えとして、指揮官はまずここを要求する。そして、「リミットを超えて相手と向き合い、闘うからこそ楽しい。そういう試合であれば、自分たちも相手も成長する」とも言っている。
もちろん相手の分析も行うし、試合前日の非公開練習では対策も選手たちに伝える。だが、それが彼のメインとなる考え方でないことは、試合前々日のトレーニングですら、主力組と控え組とを明確に分けないスタイルからもわかる。
先発メンバーの漏洩を防ぐという意味もあるのだろうが、チームのコンビネーションや相手対策の徹底を考えれば、主力は主力としてまとまった時間を取った方がいい。それをやらないのは、相手を基軸に考えるのではなく、自分たちの成長を主軸としているからだ。チームをシャッフルしてやれば、試合に出ない選手たちも含めてお互いの特徴を知ることができるし、やるべきことも浸透しやすい。何よりも自分たちに向かってベクトルを向けやすい。
スキッベ監督が育成畑の人であるからこそ、こういう発想になる。もちろん、相手を徹底的に分析し、丸裸にして、相手対策を中心に試合を組み立てることも否定するものではない。それはそれで、しっかりとしたストラテジーだ。だが、広島の指揮官はアプローチが違う。練習でも言葉でも、「まず自分たちのことをやろう」が徹底している。だからこそ「リスクマネジメント<リスクテイク」の不等式を成立させることができる。
転機は10月19日、今季初の公開練習
甲府戦の前半は、この不等式が成立していなかった。だから負けた。だから指揮官は、準優勝後の最初のトレーニング(10月19日)で、「勇気を持って、勇敢に戦おう」と選手たちに働きかけた。
「俺たちは、何も得ていない。ルヴァンカップも手にしたことがない。だから、失うものなんてないんだ。過去は変えられないが、未来は創ることができるんだぞ」
塩谷司は「その通りだ。前を向かないといけない」と思ったという。他の選手たちも同様だ。だが、それでも完全には吹っ切れない。「もやもやがずっと、胸の中には残っていた」と大迫は言う。ルヴァンカップ決勝は22日。時間はない。いつまでもこのままではいけないと誰もが思う。思うが、それができないのが、人間だ。
野津田岳人もまた、必死で切り替えようとしていた。
「監督も言っていたように、自分たちはそもそも何も掴み取っていなかった。もう一回ゼロからというか。今度は自分たちがつかみにいくっていうような気持ちで、チャレンジャーとしてやっていくしかない。ありがたいことに、この悔しさをリベンジする舞台(ルヴァンカップ決勝)がこんなに早くある。そこを幸せだと思ってやらないといけない」
広島が幸運だったのは、この19日がスキッベ監督就任後初となる、サポーターへのトレーニング公開日だったこと。これは甲府戦の前に決まっていたことだったが、このタイミングでサポーターが練習場に来てくれたことが、特に「切り替え」に向けては大きな力となった。
……



Profile
中野 和也
1962年生まれ。長崎県出身。広島大学経済学部卒業後、株式会社リクルート・株式会社中四国リクルート企画で各種情報誌の制作・編集に関わる。1994年よりフリー、1995年からサンフレッチェ広島の取材を開始。以降、各種媒体でサンフレッチェ広島に関するレポート・コラムなどを執筆した。2000年、サンフレッチェ広島オフィシャルマガジン『紫熊倶楽部』を創刊。以来10余年にわたって同誌の編集長を務め続けている。著書に『サンフレッチェ情熱史』、『戦う、勝つ、生きる』(小社刊)。