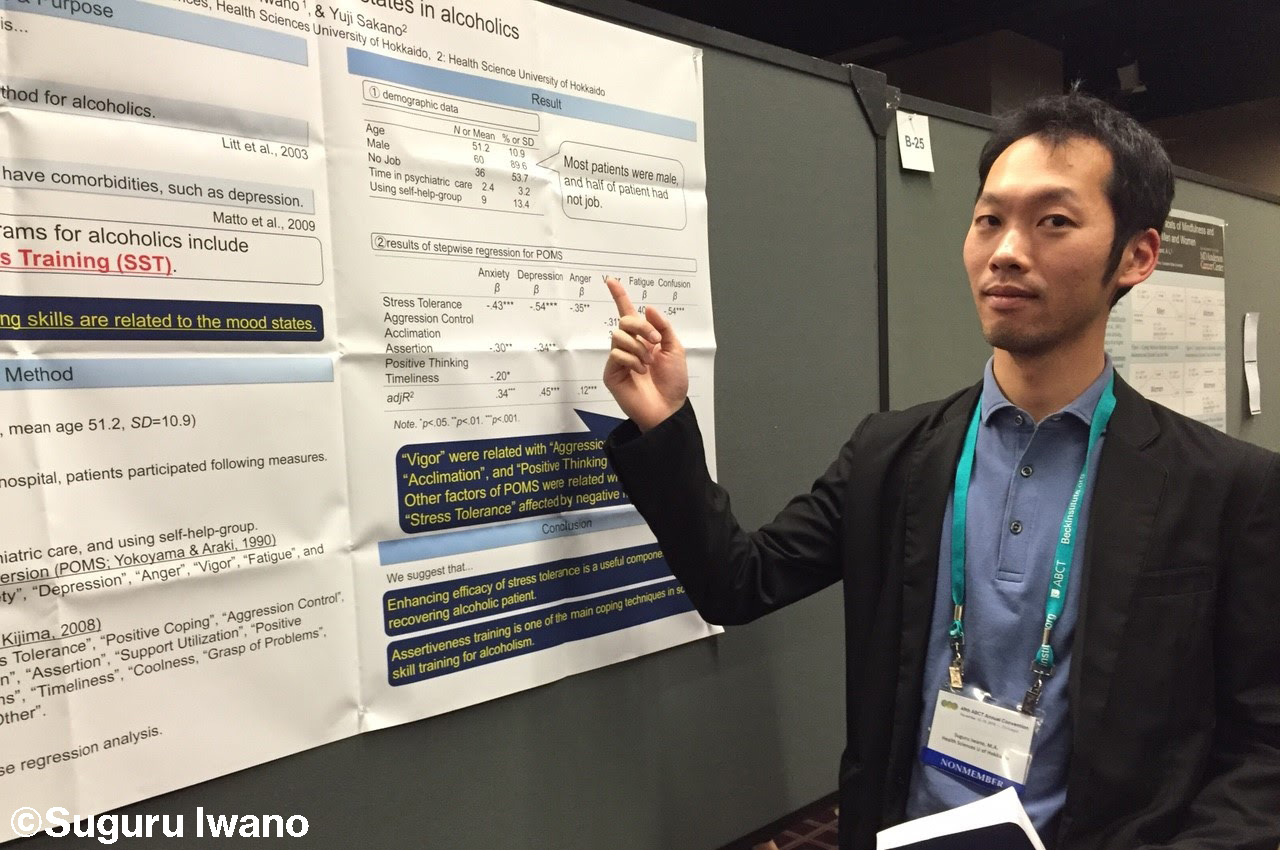オシムも認めた“サッカー大好きおじさん”。「やりたい」ことを貫く元サッカーマガジン編集長・北條聡の今までとこれから

蹴人列伝 FILE.2 北條聡(サッカーライター)
サッカーの世界では、あるいは世間的に見れば“変わった人”たちがたくさん働いている。ただ、そういう人たちがこの国のサッカーを支えているということも、彼らと20年近く時間をともにしてきたことで、より強く実感している。本連載では、自分が様々なことを学ばせてもらってきた“変わった人”たちが、どういう気概と情熱を持ってこの世界で生きてきたかをご紹介することで、日本サッカー界の奥深さの一端を覗いていだだければ幸いだ。
第2回は元『サッカーマガジン』の編集長であり、現在も多数のサッカー媒体に寄稿されているサッカーライターの北條聡氏。“好き”と“仕事”をまさに直結させている究極の『サッカー大好きおじさん』は、どのような過程を経て、形成されていったのか。そのルーツを本人の言葉で辿っていこう。
ポジションは左ウイングだった!
――そもそも北條さんとサッカーとの接点はどういうところだったんですか?
「僕はプロレスも相撲も野球も好きだったんですけど、小学校3年生ぐらいの頃にサッカー部の先輩から『オマエ、足が速いらしいな。サッカーやれ』って言われたんです。そうしたら周りの仲が良い友達もみんな『サッカー部に入る』と言い出して、『じゃあしょうがないな。入ろうかな』って。
当時はサッカー部に入るとアディダスの下敷きと“少年ハンドブック”っていうのをもらうんですよね。サッカーマガジンに入って『ああ、コレはここで作られていたんだ』とわかるんですけど(笑)、そのハンドブックの中で“世界のスーパースター”としてペレ、クライフ、ベッケンバウアー、キーガン、シモンセン、ケンペスが紹介されていて、海外の選手で知っているのはそれぐらいでしたね。ダイヤモンドサッカーも、僕は放送時間がかぶっていた全日本プロレスを見ていたので、全然見ていなかったんですけど、小学校6年生から中学校1年生に上がる直前の第1回目のトヨタカップを見て『面白いな』って。そこから中学校2年生のタイミングでスペインW杯があって、初めてヨーロッパベスト11みたいなイレブンの別冊を買った時に、コンティとかプラティニとか、イアン・ラッシュとか紹介されていて、そこからどっぷりですね」
――ポジションはどこだったんですか?
「左のウイングでした。足が速かったからかな。でも、初めてW杯を見た時に、『あれ? 監督から言われているような選手なんていないな』と思ったんです。当時はちょうどウイングらしいウイングがいなくなってきた時代で、それはのちに“オタク化”していく背景で、その歴史を知っていくんですけど(笑)、『別にウイングが中に斬り込んで点を獲ってもいいんじゃないの? みんな自由にやっているけどな』って。それで監督から言われていたことと全然違うことをやり始めて。『自由が好き』という僕のダメな性格にサッカーが合っちゃったというか(笑)」
――プレーはいつまでやっていたんですか?
「高校の時までです。2年生の時に1回倒れて、親が心配して『やめてくれ』と。でも、その時はもう将来もマガジンかイレブンのようなサッカー雑誌で仕事をしたいと思っていましたから。どうすればなれるのかわからなくて、進路相談に行ったら『マスコミだろ。じゃあ早稲田だな』って先生に言われて、『わかりました』という軽い感じで早稲田大学を志望しました。大学の名前なんて知らなかったら、『早稲田? 国立ですか?』『いや、私立だよ』みたいな感じで、調べたら『いやいや、結構入るの大変じゃん』って(笑)。高校の頃には、将来は週刊プロレスに行くかサッカー雑誌に行くか迷っていましたね。本当はイレブンが本命だったんですけど、のちに週刊プロレスとサッカーマガジンは同じ会社で作っていると知って、『こんないい会社ないだろ』って(笑)」
――サッカー雑誌は普通に近所の本屋さんで買っていたんですよね?
「そうです。確かみんな示し合わせたように発売日が一緒だったんですよ。それで、発売日に本屋に行って、マガジン、ダイジェスト、イレブンと3冊まとめ買いして。まあ、2日ぐらいで読み終わっちゃうんだけど(笑)、それを1カ月間読み込んでいくという作業で、途中からストライカーも入ってくるんですよね。高校生ぐらいからかなあ。近所の本屋は平積みにはなっていなくて、背表紙だけで並んでいたものをゴソッと買ってね」
――じゃあ近所の人はほとんどサッカー雑誌を買えなかったわけですね(笑)
「確かに。僕が全部持っていっちゃうから(笑)」
予備校の本屋で知ったバルデラマの衝撃
――早稲田大学はもちろんマスコミに入りたいから受験したわけですね。
「そうです。ただ、浪人時代が楽しかったんですよね。今になって『蹴球予備校』みたいなことをやっているのも、予備校自体が好き過ぎるからで、メチャメチャ楽しかったんですよ。先生が面白かったんでしょうね」
――予備校は地元の宇都宮ですか?
「いや、代ゼミです。高校3年の時に受験に落ちて、定期で代ゼミに通っていたんですけど、世界史が楽しかったんですよね、サッカーと連動していますし、今のこの性格は世界史好きから来ているんじゃないかなと。地理と歴史が大好きだったので、勉強している感じはなくて、『ああ、カルロス・バルデラマってイギリス人だったら“チャールズ”だったのか』とか(笑)」
――僕は北條さんがバルデラマの存在を知ってから、プレーを初めて映像で見るまで3年かかったっていう、あの話が好きなんですけど(笑)、それはいつ頃の話ですか?
「まさに確か代ゼミの中にあった本屋で、コパ・アメリカの別冊のマガジンを買ったんだと思うんですよ。その中にイギータとバルデラマの衝撃の2ショットが載っていて、『コイツらは何なんだ』と(笑)。その時に編集長だった千野(圭一)さんが現地の記者に聞いて、サンタ・マルタっていうバルデラマが育った地域の海岸でサッカーをやっていると金髪になるっていう、『ええ?』ってエピソードが語られていたんです。それでコロンビアのサッカー自体も『細かいパスの連続だ』というような表現をされていて、ジーコのブラジルやプラティニのフランスみたいな『オレの好きなサッカーかも』って。当時の南米と言ったらブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの3強と、4番手にペルー、パラグアイ、チリが来て、コロンビアはアウトサイダー扱いだったから、そんな国にこんな面白そうなチームがあるんだということで、ハマっていったんですよね」
――それで、1990年のW杯で動いているバルデラマを見るわけですね。
「そうそう。W杯のためにBSチューナーを実家で買ってもらって、ちょうどW杯の期間だけ、大学も普通に授業があるのに、バイトも全部ぶっちぎって1カ月間実家に戻って、ひたすらW杯を見たんです。友達からは『アイツ行方不明になったぞ』って言われていたみたいで(笑)。何かの契約の手違いで開幕戦からは見られずに、初めて試合を見たのがグループリーグ最終戦のコロンビア対西ドイツで、最後にバルデラマの必殺のスルーパスが出て。あれを最初に見たというのもインパクトがありましたね」
マガジン、ダイジェスト、イレブンしか就職活動はしなかった
――ちなみに高校時代や大学時代に、北條さんと同じぐらいの知識を持ってサッカーの話ができる人は周りにいたんですか?
「いない。ゼロですね。そもそもサッカー雑誌を読んでいる人も多くなかったですし、大学時代は周りにラグビー好きが多かったので、サッカーとラグビーの共通項を探したりしていました。ラグビーって後ろの人が前に攻めていくじゃないですか。それがベッケンバウアーっぽいなって思ったり(笑)、プラティニがいなくなった後のフランスにブランがいわゆるリベロとして出てきて、そういう面白い選手がいるぞということを、ラグビー好きの友人に一生懸命話して、『ああ、そうなの』って言われて終わる、みたいな(笑)。とにかくサッカーの話ができるヤツはいなかったですね」
――ひたすら自分の中に知識を蓄えていくと。
「まあ、蓄えていくというか、情報が多くないから、ひたすら同じものを読み込んでいくというか。映像も大学時代にはビデオがあったから、チャンピオンズカップの決勝やトヨタカップを擦り切れるまで見るわけですよ。ミランの試合だったら、まずミランの側から見て、対戦相手の側から見て、選手個別で見て、ポジション別で見てと、視点を変えて何回も1つの試合を見ていくと、『ああ、同じ試合でも違って見えるんだ』って。もう『画面の外からスローインを投げているのはたぶんアイツだな』とか想像できるようになっていくんです。
あとは、ちょうど自分が惚れ込んでいたジーコのブラジルも、プラティニのフランスも、コロンビアも、W杯で勝てないと。『これはなぜなんだ』というところから、強いチームというのはどういうことかと考え出したのはその時代ですね。自分でフォーメーション図を描き出して、戦術やら何やらいろいろ妄想し始めると(笑)。とにかくサッカーの話し相手がいないから、そういうことをやっていた大学生時代だったかな」

――ちなみにベースボール・マガジン社以外に就職活動はしたんですか?
「していません(笑)。しかも、マガジン、ダイジェスト、イレブンの3誌に『試験を受けさせてください』と連絡をして、『いいですよ』と返事が来たのはマガジンだけでした。ダイジェストとイレブンは『公募していません』と。他のところを受けようという気力はなくて、この3誌以外のところに行ってもしょうがないぐらいに思っていたので、周りの友達からは『オマエ、落ちたらどうするんだよ』って。『落ちたらイタリアでも行くよ』とか適当に言っていたら、たまたまマガジンに拾われたんですけどね。
高校3年生になる頃にはもうJリーグができるという話は知っていたから、大学を卒業する頃にはJリーグが始まっているんだなとは思っていたんですけど、結局二浪したので、たまたま大学卒業とJリーグ開幕の時期が合って、ちょうどマガジンも人を増やさなきゃいけないタイミングで、うまく採用されたんです。ベースボール・マガジン社は雑誌もいっぱいあるから、希望の編集部に行けることもなかなかないんですけど、そういう巡り合わせと運が良かったんですよね。同期が一度に3人もマガジンに配属されたんです」
――ベースボール・マガジン社に入社してからは、すぐにサッカーマガジンに配属されたんですよね。
「そうです。ずっと辞めるまでマガジンにいたけど、そういう人はあまりいなかったんじゃないですかね」
マガジンのバックナンバーをひたすらコピーする日々
――頭の中でいろいろ妄想してきたところから、念願のマガジンに入ってみた時に、例えば『やっぱりこの環境は凄い』となったのか、それとも『あれ、やっぱりオレの方が知識はあるんだな』となったのか、どちらだったんですか?
「国吉(好弘)さんがいましたからね。僕は国吉さんの影響を受けている部分があるので、話しかけていろいろなことを教えてもらいましたけど、それ以外の人と比べると『知識としては結構自分の方が知っていることが多いんだな』とは思いました。でも、入ったばかりの頃は役に立たないから、仕事なんて振られない状況の時に、みんなが帰った後にひたすら編集部にあった昔のバックナンバーを引っ張り出して、自分の気になる記事を片っ端からコピーしていって、それがのちに“世界遺産”っていう自分がやる連載に繋がるんですけど、それこそ古本屋で買ったら凄い金額になるぐらいの量があったので、『凄い!全部読めるじゃん』と思って(笑)、昔の連載記事とか、昔の人のコメントとか、自分が知らないようなことを延々と読み込んでいましたね」
――それはもっと知識を増やして、この編集部での居場所を確立したいという想いからですか?
「いや、単に好奇心の方が強かったですね。『知りたい!』っていう欲望が強かったと思います。昔のことを掘っていくと、こういう事情でフォーメーションが変わったり、サッカーのスタイルが変わったりしていくんだって、謎が解けていく感じがあったかもしれないです。『ああ、オレらの時代にウイングが少なかったのは、こういう流れがあったからか』とか、ジーコやプラティニが何であんなにワンタッチパスを使っていたのかとか。あの牧歌的な時代からオランダが登場して、ディフェンスが厳しくなって、そこから敵に捕まる前に止めずに蹴る必要性が高まったことから、ブラジルやフランスのワンタッチフットボールに繋がっていくんだなって。まあ、そんなのは国吉さんぐらいしか話す相手はいなかったけど(笑)、なにかアウトプットする場所はないかなと思って、千野さんに『連載をやらせてくれ』ってお願いして、あの本誌の“世界遺産”という連載になっていくんです。……



Profile
土屋 雅史
1979年8月18日生まれ。群馬県出身。群馬県立高崎高校3年時には全国総体でベスト8に入り、大会優秀選手に選出。2003年に株式会社ジェイ・スカイ・スポーツ(現ジェイ・スポーツ)へ入社。学生時代からヘビーな視聴者だった「Foot!」ではAD、ディレクター、プロデューサーとすべてを経験。2021年からフリーランスとして活動中。昔は現場、TV中継含めて年間1000試合ぐらい見ていたこともありました。サッカー大好き!