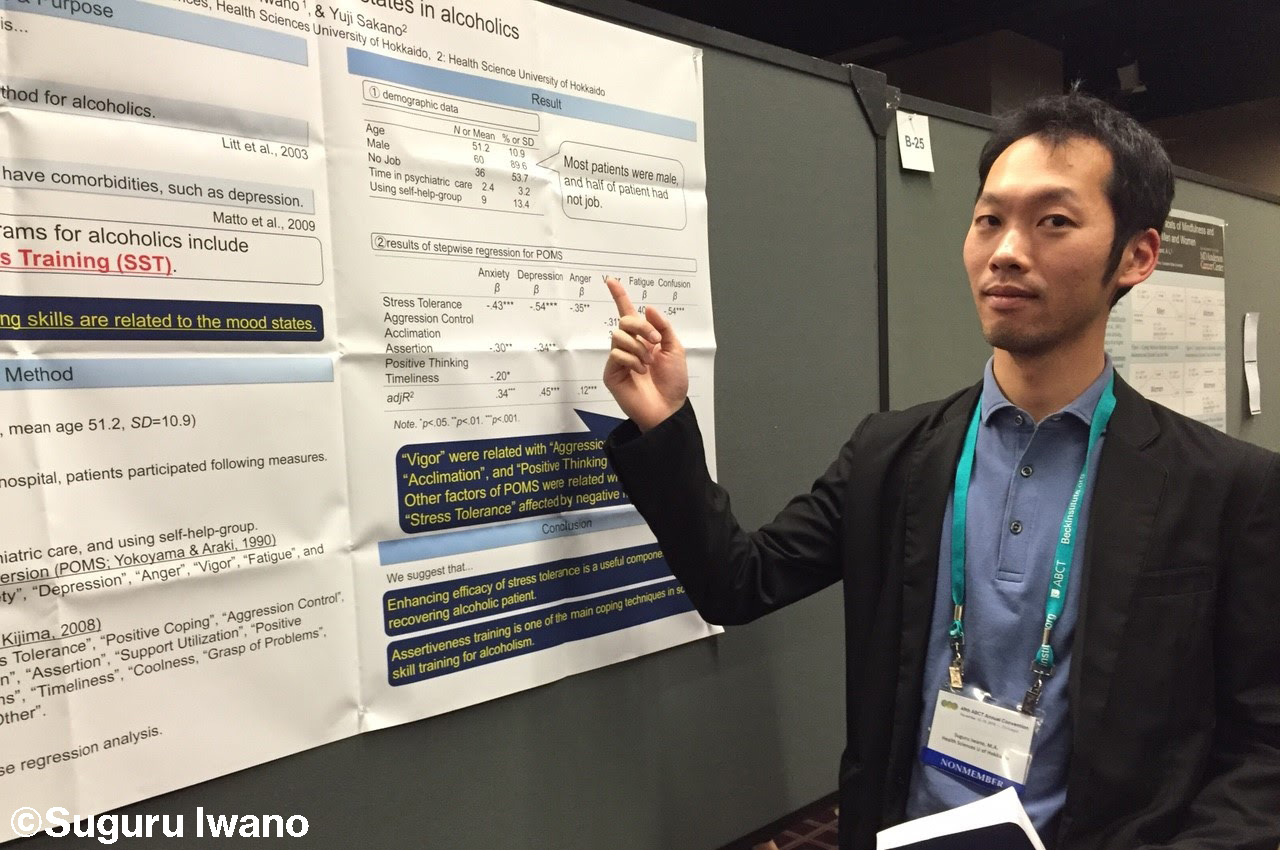【短期集中連載】間瀬秀一のモンゴル冒険譚Part1「0-14@フクアリから始まった未知への旅。そしてオシムの金言」

5カ国でプレーした異色の現役時代を経て、イビチャ・オシムの通訳として指導者キャリアを始めた間瀬秀一。ブラウブリッツ秋田や愛媛FCで監督を歴任し、2021年4月からモンゴル代表監督という新たな挑戦を始めた。残念ながら眼の病気で昨年12月で退任することになったが、クロアチア時代のルームメイトで20年来の仲であるジャーナリストの長束恭行氏を相手に、未知の地での濃厚な冒険譚を聞かせてくれた。
全4回の短期集中連載のPart1は、モンゴル代表監督就任の経緯、ワイヴァンFCで感じた日本の育成年代の課題、そして恩師であるオシムからのアドバイスについて教えてくれた。
ブラウブリッツ秋田退任後に何をしていた?
――まずは2021年4月のモンゴル代表監督就任に至るまでの経緯として、J3ブラウブリッツ秋田の監督を退任してからの動きを教えてください。
「2019年シーズンの秋田は開幕で出遅れましたが、下半期は内容も結果も含めて僕の中では過去最高と思えるサッカーがみんなとできたんですね。1年間のトータルでは8位に終わったものの、グーッと尻上がりに良くなったシーズンだったんです。指導者として過去最高の指揮が執れていただけに『これを先につなげたい』と思っていました。
ところが、2019年から2020年にまたがるシーズンオフは、過去のJリーグの歴史において監督人事の動きがかなり少なかったんです。僕としては『Jリーグクラブで指揮を執りたい』と思っていたのですが、なかなかつながらなくて。しかし、指導者として指揮を執る枠をもっと広げてもいいんじゃないかと。Jリーグの監督の椅子はJ1・J2・J3だけになりますが、世界を見たらもっと枠は広がると思ったんです」
――そもそも間瀬さんは現役時代に日本という枠にとらわれず、海外で揉まれてきた人ですよね。指導者に転身されてからも海外志向はあったのですか?
「いや、『逆輸入』という思いがやっぱり強かったんです。日本では小・中・高・大と有名校で活躍するような経験を積むことなく、大学を卒業してから7年弱の現役生活は5カ国すべてを海外で過ごしました(アメリカ、メキシコ、グァテマラ、エルサルバドル、クロアチア)。そこで自分を高めていろんなものを身につけたことで、逆輸入の形で日本で勝負したいと思い、指導者キャリアはずっとJリーグで築いてきたわけです」
――2003年にイビチャ・オシムの通訳としてジェフに加入し、それからファジアーノ岡山、東京ヴェルディ、ブラウブリッツ秋田、愛媛FCで通算16シーズン、コーチや監督としてJリーグで活動しました。間瀬さんオリジナルのサッカーの追求という面で、2019年のシーズンに1つの到達点にたどりついた感じですか?
「いや、僕は成長とステップアップを続けていると思います。自分の指導の場を海外にも広げることを決め、いろんな人と相談をした時に、JFA公認指導者の海外派遣としてミャンマー代表監督の可能性が浮上してきました。2020年の1月や2月の頃です。まさにその準備をしていたところでコロナ禍が起きまして。ミャンマー国内の騒乱も重なり、結局、この話はオファーになる前に流れてしまったんですね」
――それからどうなったんですか?
「サッカーの人事シーズンが終わってしまったんで、三重県の実家で待機していました。そんな中、愛知県刈谷市のワイヴァンFCというアマチュアクラブに加入しました。つなげてくれた人物が海津英志さん(現・アルテリーヴォ和歌山監督)。僕が暁高校に通っていた頃の体育の先生であり、サッカー部の監督だった方です。すごい経歴の持ち主で、学校教師を辞めてS級ライセンスを取得して、三重県で立ち上がったヴィアティンを県3部からJFLまで引き上げ、その後にワイヴァンに引き抜かれた人なんです。その海津さんの誘いで2020年6月からワイヴァンで働くことになったんです」
――ワイヴァンでは『ポリバレントコーチ』という肩書で働かれていたんですよね?
「そうですね。男女のカテゴリーに関係なく、すべてのチームをサポートしました。そうそうできない経験ですし、日本でも世界でもなかなか存在しない役職ですよね(笑)。幼稚園、小学生、中学生、大学生、トップ……あらゆるカテゴリーの選手を見られたんです。各年代・各年齢で理解できることが違うので、ちゃんとその境目を知ったというのは指導者として大きいですね。
自分は16年間ずっとJリーグのトップチームで働いてきたわけじゃないですか。でも自分が常に思ってきたのは、トップチームのJリーガーといっても、もちろん彼らは完璧ではなくて、一人ひとりの選手がそれぞれの特徴を持ちながらも、やっぱり足りないところがいっぱいあるんですよ。彼らが小・中・高とどういう道筋をたどって、何がどう足りない状態できたのがわかったというか(苦笑)」
――ワイヴァンであらゆるカテゴリーを担当しながら、その流れがわかったということですね。
「そうそう。これは否定的な意味合いだけではなくて、彼らが特徴を培ってきた部分がありながらも、その逆として『なぜこれだけ足りない状態でJリーガーになったのか?』という問題をすごく感じていました」
――それは技術的なところ、もしくはメンタル的なところ?
「もうあらゆるところです。戦う気持ちや技術面、走力や走り方もそう。例えば、ヘディングの基礎が一切ない選手もJリーグにはいるんです。そんな中、僕が一番感じていたのは『見る』能力。それが欠けている選手が本当に多くて。そもそも日本の育成では『見る』ということを教えられることが少なく、もしくは身につけることができないままプロになっているというのが一番の実感なんですね」
日本人に足りない「見る」能力とは?
――いつ頃からそれに気づいたのですか?
「オシムさんの通訳をやり始めた時に『日本の選手は見ることが足りないな』と強く思いました。その後も指導現場を通して『選手には見ることが必要である』『見るためのトレーニングは存在する』と常に思っていて、今までずっと注目して掘り下げてきたテーマです。逆算をして振り返ってみると、海外でプレーしていた頃はそんなに意識していなかったものの、やっぱり自分も『見る』という能力に長けていた部分もあり、同時に足りない部分もあったんだなということに気づいたんです」

――私も帰国してからは日本人の視野の狭さを実感するのですが、海外では外国人として生活している以上、周囲に神経を払いながら状況判断することが自然と鍛えられますよね。
「サッカーもそうですけど、日本人は自分の近くが見えていても、遠くが見えていない場合が多いんですね。海外生活では危険な地域に足を踏み入れたり、車の運転も荒かったりするので、もっと情報を早く察知するために遠くを見ながら生きているんですよ。
これはよく秋田や愛媛で起きたエピソードです。街に大きなショッピングセンターがあると行く場所はみんな同じで。自分は遠くを見て何が起こってるかを把握しながら生活しているから、『あっ、あの選手がショッピングセンターに来ているな』と自分が見つけられる前にこちらが必ず彼らを見つけていました。……



Profile
長束 恭行
1973年生まれ。1997年、現地観戦したディナモ・ザグレブの試合に感銘を受けて銀行を退職。2001年からは10年間のザグレブ生活を通して旧ユーゴ諸国のサッカーを追った。2011年から4年間はリトアニアを拠点に東欧諸国を取材。取材レポートを一冊にまとめた『東欧サッカークロニクル』(カンゼン)では2018年度ミズノスポーツライター優秀賞を受賞した。近著に『もえるバトレニ モドリッチと仲間たちの夢のカタール大冒険譚』(小社刊)。